ここから本文です。
労働力調査に関するQ&A(回答)
A.労働力調査とは
A-1 労働力調査はどのような調査なのですか?
労働力調査は、我が国における就業・不就業の実態を明らかにして、雇用政策等各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行うもので、1946年9月から約1年間の試験期間を経て、1947年7月から本格的に実施しています。
現在、この調査は、全国で無作為に抽出された約40,000世帯の世帯員のうち15歳以上の者約10万人を対象とし、その就業・不就業の状態を調査しています。
この調査から得られる就業者や完全失業者の数、完全失業率等は、雇用情勢の動向を表す重要な指標となっています。
A-2 労働力調査はどんなことを調べるのですか?
労働力調査では、男女別・年齢階級別の就業状態、産業別や職業別の就業者数などを把握するための事項を、毎月、「基礎調査票」により調査しています。
また、全4回※の調査のうち4回目には「特定調査票」を追加して配布し、就業や失業などの状況をより詳細に把握するための事項を調査しています。
※対象となった世帯には、原則、1年目に2か月、2年目の同じ月に2か月の計4回調査します。
基礎調査票(PDF:1.6MB)
男女の別、出生の年月
月末1週間に仕事をしたかどうか
1週間に仕事をした時間、1か月間に仕事をした日数
勤め先の事業の内容、本人の仕事の内容
正規の職員・従業員、パート、アルバイトなどの雇用形態
仕事を探し始めた理由 など
特定調査票(PDF:1.7MB)
仕事時間についての希望
転職の希望の有無
仕事を探している期間
就業の希望の有無
前職の仕事の内容
教育の状況、年間収入 など
(参考)労働力調査の調査事項
A-3 労働力調査の結果はどのように利用されているのですか?
労働力調査の結果は、原則として調査月の翌月末に公表しますが、公表とほぼ同時に総務大臣から内閣総理大臣や厚生労働大臣を始めとする全ての大臣に結果が伝えられ(閣議報告)、必要に応じて速やかに関係施策が立案・実施されます。さらに、政府が毎月発表する月例経済報告においても、雇用面の指標として景気分析に利用されています。
また、各種白書の作成、大学・研究機関等における雇用失業問題の研究などにおいて、重要な資料として利用されています。そのほか、近年では「持続可能な開発目標(SDGs)」達成に向けた日本の取組の現状を確認するためにも活用されています。
(参考) 調査結果の活用事例
A-4 どうしても答えなければいけないのですか?
調査の対象として選ばれた人から漏れなく、正確な調査ができないと正しい統計が作れなくなります。不正確な統計を利用して、私たちの身近な行政施策や将来計画を作ってしまっては、私たちの生活や暮らしが誤った方向に向かってしまうおそれがあります。例えば、本当は200万人の完全失業者がいるのに、不正確な統計が「完全失業者は30万人」という結果を出すと、適切な規模の予算を執行できず、仕事がなくて困っている人々を十分に助けることができなくなることでしょう。
国の重要な統計調査の調査対象者には、正確な報告を得るという目的から、統計法(e-Gov)![]() 第13条に基づく報告義務があります。労働力調査の対象となった世帯にも報告義務がありますので、必ず御回答ください。統計法(e-Gov)
第13条に基づく報告義務があります。労働力調査の対象となった世帯にも報告義務がありますので、必ず御回答ください。統計法(e-Gov)![]() では、これに違反した場合の罰則(第61条)も定められています。
では、これに違反した場合の罰則(第61条)も定められています。
一方、統計法(e-Gov)![]() 第41条では、調査に携わる者(国・都道府県・調査員など)が調査の結果知り得た秘密を漏らしてはならないことが規定されており、これに違反した者に対する罰則(第57条)が定められているなど、プライバシーは保護されます(「D-1 プライバシーは保護されるのですか?」参照)ので、安心して御回答ください。
第41条では、調査に携わる者(国・都道府県・調査員など)が調査の結果知り得た秘密を漏らしてはならないことが規定されており、これに違反した者に対する罰則(第57条)が定められているなど、プライバシーは保護されます(「D-1 プライバシーは保護されるのですか?」参照)ので、安心して御回答ください。
B.調査方法について
B-1 労働力調査はどのように行われるのですか?
労働力調査は、総務省統計局が基本的な計画を立案し、都道府県を通じて実施します。各世帯には、調査員が訪問し、調査票を配布・回収します(インターネットで御回答いただいた場合には、調査票の回収に伺いません。)。
調査対象として選定された世帯には、1年目に2か月、2年目の同じ時期に2か月、基礎調査票(PDF:1.6MB)への御回答をお願いすることになります。
また、2年目の2か月目には、基礎調査票のほか、特定調査票(PDF:1.7MB)への御回答も併せてお願いすることになります。
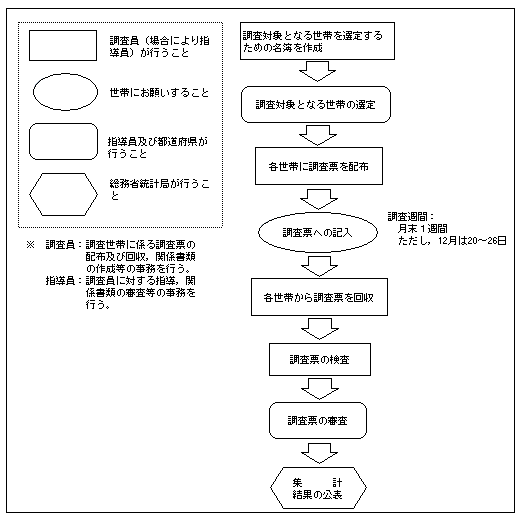
B-2 調査対象はどのように選ばれるのですか?
全国の世帯の中から一部の世帯を統計的な方法によって無作為に抽出します。
具体的には、全国を約50世帯ごとに区切った区域(国勢調査において設定されている区域)の中から労働力調査の調査地域を選定し、さらに、その選定された調査地域内に居住している世帯の中から調査対象となる世帯を選定します。
労働力調査で選定する調査地域は約2,900地域で、調査対象となる世帯は約40,000世帯です。
(参考) 抽出方法の概要図(PDF:265KB)
B-3 なぜ、労働力調査は全数調査ではなく、標本調査として実施しているのですか?
労働力調査は、毎月の雇用・失業の動向を明らかにすることを目的とした調査であり、政府による雇用失業対策や景気動向の判断などのために不可欠な調査です。
毎月、調査結果を適時に提供するためには、調査の実施から結果公表までの一連の作業を迅速に行う必要があります。
仮に、全数調査で行う場合には、調査の実施・集計にかなりの時間を要する上、大きな予算も必要となります。
このため、統計理論に基づいた標本調査として実施することで、正確さを損なわずに迅速な調査を効率的に実施しております。
B-4 調査員はどのような人なのですか?
労働力調査の調査員は、都道府県知事が任命した地方公務員です。
調査員には統計法(e-Gov)![]() という法律に基づく守秘義務がありますので、調査員がお伺いした際は安心して御回答ください。
という法律に基づく守秘義務がありますので、調査員がお伺いした際は安心して御回答ください。
B-5 どのような回答方法がありますか?
回答に際しては、かんたんで便利なインターネットによる回答をお勧めしています。なお、紙の調査票による回答も可能です。
回答に必要な書類(ログイン情報や紙の調査票など)は、調査週間(月末1週間。ただし、12月は20〜26日)の始まる前に調査員が各世帯を訪問して配布します。
◆インターネットで回答する場合
調査員から配布される「インターネット回答のしかた」と入力画面の案内に従って回答します。詳しくは「インターネット回答のご案内」を御覧ください。インターネットで御回答いただくと、調査員が調査票の回収に伺うことはありません。
◆紙の調査票で回答する場合
調査員から配布される紙の調査票に記入して回答します。調査に回答する際は、「調査票の記入のしかた」を御覧ください。記入していただいた調査票は、調査週間後に調査員が改めて各世帯を訪問しますので、その際に提出をお願いします。
B-6 インターネット回答の方法がよく分からないのですが。
動画による御案内を「インターネット回答のご案内」に掲載していますので御覧ください。なお、電話での回答サポートも行っております。「インターネット回答のしかた」裏面に記載の「労働力調査コールセンター」まで御連絡ください。
C.公表時期について
C-1 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
調査結果のうち、基本集計結果(基礎調査票による調査結果)については、原則として調査月の翌月末に公表します。
また、詳細集計結果(特定調査票による調査結果)については、原則として四半期ごとの最終調査月の翌々月に公表します。
(労働力調査結果の公表予定日については、「結果の公表予定」を参照してください。)
D.プライバシーの保護について
D-1 プライバシーは保護されるのですか?
この調査は、統計法(e-Gov)![]() という法律に基づいて行われ、プライバシーは厳重に守られます。
という法律に基づいて行われ、プライバシーは厳重に守られます。
- 統計法(e-Gov)
 第41条に基づき、調査に携わる者(国・都道府県・調査員など)には調査上知り得た事項の秘密を守ることが義務付けられています。
第41条に基づき、調査に携わる者(国・都道府県・調査員など)には調査上知り得た事項の秘密を守ることが義務付けられています。 - 調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。
- 提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、統計を作成した後は溶解処分されます。
- インターネットで回答いただいたデータは、厳重に管理されたサーバに蓄積されますが、調査期間終了後は、速やかに削除されます。多重にファイアウォールが設置されているのはもちろんのこと、不正なアクセスがないかを24時間監視しています。また、回答を送信する端末から回答サイト(政府統計オンライン調査総合窓口)までの通信は、全て暗号化されています。
E.調査結果の利用について
E-1 労働力調査には「基本集計」と「詳細集計」がありますが、雇用者数などは両方の集計で結果が公表されており、年平均結果などの数値が若干異なっています。どちらを利用すればよいのですか?
まず、基本集計は調査区内から選定された約40,000世帯が調査対象となっていますが、詳細集計は基本集計の対象世帯のうち約10,000世帯が対象となっています。
また、両集計の範囲を比べると、刑務所・拘置所等のある区域及び自衛隊区域の施設内の居住者について、基本集計では対象範囲となっていますが、詳細集計では含まれておりません。
このように調査世帯数や集計の範囲の違いなどから、両集計の結果数値が一致しない場合があります。
したがって、通常は基本集計を利用していただき、詳細集計でしか得られない現職(非正規の職員・従業員)の雇用形態についている理由、前職などの数値については詳細集計を御利用ください。
E-2 労働力調査の結果を分析などする際に気を付ける点はありますか?
労働力調査は標本調査であるため、調査結果には標本誤差が含まれることがあります。
標本誤差は、調査項目の種類や標本規模などによって異なりますが、特に標本規模が小さい集計区分では注意が必要になります。
なお、項目ごとの標準誤差率については推定値の標本誤差(PDF:678KB)を御覧ください。
そのほか、労働力調査の結果を分析する際には、Q&Aのほか、結果表の利用に関する参考資料(統計表を見る上での注意)や結果を見る際のポイントを参照してください。
F.就業状態について
(就業状態の定義)
F-1 就業者、完全失業者とは、どのような状態にある人のことですか?
就業者、完全失業者の定義は、次のとおりです。この定義は、他の主要先進国と同様、客観的に就業・失業の実態を把握するため、ILO(国際労働機関)![]() の定めた国際基準に準拠したものです。
の定めた国際基準に準拠したものです。
<基本集計における就業状態※>
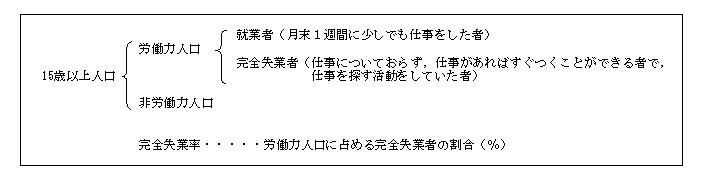
※詳細集計では、2018年から、未活用労働指標の作成を開始したことに伴い、就業状態を未活用労働を含む区分に変更しました。(2017年までは、上記基本集計と同じ区分です。)
詳細は、結果表の利用に関する参考資料(未活用労働指標の解説)を御参照ください。
F-2 ILO基準における、就業者、完全失業者の定義は、どのような考え方により定められているのですか?
就業状態の決定の仕方には、ふだんの状態で把握する「有業者方式」と、一定期間における活動状態を把握する「労働力方式」があります。
有業者方式は、調査の時期や調査時の偶発的状況に影響されることが少ないという利点を持つ一方、定義に曖昧さが残り、回答者の意識に左右される部分が大きいという欠点があります。
これに対して、労働力方式は、調査の時期や調査時の偶発的状況に影響されやすいという欠点を持つ一方、定義が厳密にできるという利点があります。
ILOでは、定義が明確で雇用・失業の把握に適している労働力方式が採択され、その後、さらに定義の厳格化を図り、現在に至っています。
(就業者に関するもの)
F-3 家業を手伝っている人は給与がなくても就業者となるのですか?
日本の労働力調査の家族従業者の定義は、他の主要先進国と同様、ILOの国際基準に準拠したものです。
この定義に従って、家業を手伝っている人は、給与を受け取っていなくても、就業者になります。
F-4 月末1週間に働いた時間がたった1時間の人でも、就業者となるのですか?
日本の労働力調査の就業者の定義は、他の主要先進国と同様、客観的に就業・失業の実態を把握するための定義としてILOの定めた国際基準に準拠したものです。
この定義に従って、月末1週間に1時間でも働いた人は就業者になります。
ILOで定めている就業者の定義は、以下のとおりです。
「就業者」は、短い参照期間(7日間、すなわち1週間)に、給料又は利益を得ることを目的として、財やサービスの生産活動を行った、一定年齢以上の全ての者と定義される。
就業者は、
1 「従業中の」就業者、すなわち、少なくとも1時間の仕事を行った者
2 一時的に仕事を休んでいる、又は就業時間の調整(交代制、フレックスタイム、残業による代休等)のために、「休業中の」就業者
から成る。
なお、労働力調査においては、就業者の就業時間も把握しており、月末1週間の就業時間が1〜4時間の就業者数なども公表しています。また、2013年のILO決議で新たに「未活用労働」が設定され、この中で、「時間関連不完全就業者」(「就業者」に該当しながらも、一定の基準以下の就業時間であり、就業時間の追加を希望し、追加できる者)を把握することとされました。我が国においては、この要件のうち「一定の基準以下の就業時間」を「週35時間未満」としたものを「追加就労希望就業者」として把握し、2018年から労働力調査詳細集計において公表しています。
F-5 月間就業時間は、どのように計算するのですか?
月間就業時間は、月末1週間の就業時間(週間就業時間)等を元に、次のとおり算出しています。
月間就業時間 = (週間就業時間 / 週間就業日数) × 月間就業日数
なお、就業時間については、労働力調査のほかにも、厚生労働省の毎月勤労統計調査から得られる結果もよく用いられています。毎月勤労統計調査では、常時5人以上を雇用する事業所を対象に労働時間等を調査しています。このため、世帯に対して調査を行う労働力調査とは対象が異なることや、1人が複数の事業所で働いている場合の扱いが異なる※ことなどから、両者の結果を比較する際には注意が必要です。
※ 同一の人が複数の事業所で働いている場合、事業所を対象とした毎月勤労統計調査では、それぞれの事業所における労働時間が調査されますが、世帯(個人)を対象とした労働力調査では、複数の事業所で働いた合計の労働時間を調査していますので、その結果に違いがあります。
(完全失業者及び完全失業率に関するもの)
F-6 完全失業率は、どのように計算するのですか?
完全失業率とは、労働力人口(就業者と完全失業者の合計)に占める完全失業者の割合で、次のとおり算出しています。
完全失業率(%) = 完全失業者 / 労働力人口 × 100
F-7 なぜ、完全失業率は、季節調整値を主に公表しているのですか?
労働力調査のような月次統計には、例えば、農業就業者が春から夏にかけて増加し、秋以降減少していくといった、季節的な要因で毎年同じような動きをするものがあり、これを季節変動と呼んでいます。
月次統計を分析する場合に、ちょうど1年前の同じ月と比較する場合には、こうした季節変動を考慮する必要はありませんが、例えば前月や前々月と比較する場合には、その変化が、景気変動によるものなのか、季節変動によるものなのか分かりません。このような季節変動を除去した数値が、季節調整値です。
完全失業率のように、月々の動きを把握することが重要な意味を持つ数値については、季節調整値を主に公表していますが、季節調整する前の原数値も併せて公表しています。
また、人数規模等の水準が重要な意味を持つ数値については、原数値を主に公表していますが、季節調整値も併せて公表しています。(「労働力調査の結果を見る際のポイント No.4 原数値と季節調整値」(PDF:18KB)参照)
F-8 完全失業者とは、公共職業安定所(ハローワーク)に登録している人のことですか?
完全失業者には、公共職業安定所(ハローワーク)に登録して仕事を探している人のほかに、求人広告・求人情報誌や学校・知人などへの紹介依頼による人など、その方法にかかわらず、仕事を探す活動をしていた人が広く含まれます。
F-9 離職しても仕事が見つからず、職探しを諦めた人は、完全失業者なのですか?
労働力調査では、完全失業者の定義は、ILOの国際基準に準拠して、(1)「仕事についていない」、(2)「仕事があればすぐつくことができる」、(3)「仕事を探す活動をしていた」者とされており、仕事を探す活動をしていない人は、完全失業者には含まれません。
ただし、仕事をしたいと思いながら、仕事が見つかりそうもないから仕事を探す活動をしていないなど、経済情勢などの要因によって非労働力人口になっている人の把握も重要ですから、これらの人の実態については、労働力調査(詳細集計、四半期ごとに公表)で把握できるようにしています。例えば、非労働力人口のうち就業を希望し、すぐに就業できる者を「就業可能非求職者」として集計しています。
F-10 早期退職優遇制度を利用して離職し、完全失業者となっている人は、非自発的な離職による完全失業者となるのですか?
非自発的な離職による完全失業者とは、勤め先や事業の都合(人員整理・事業不振・定年等)で前の仕事を辞めたために仕事を探し始めた者のことをいい、一方、自発的な離職による完全失業者とは、自分又は家族の都合で前の仕事を辞めたために仕事を探し始めた者のことをいいます。
通常の退職に比べて有利な条件を提示して企業が退職者を募集する、いわゆる早期退職優遇制度については、これに自ら応募して退職した場合には、自発的な離職による完全失業者になると考えられますが、このような制度やその運用の態様は企業によって様々であり、最終的には、離職者本人の実態を踏まえた回答により、上記のような自発的な離職か非自発的な離職かに区別されることとなります。
(未活用労働に関するもの)
F-11 未活用労働指標とは何ですか?
雇用情勢をより多角的に把握するため、就業者、完全失業者、非労働力人口といった就業状態に加えて、就業者の中でもっと働きたいと考えている者や、非労働力人口の中で働きたいと考えている者などを未活用労働として把握し、詳細集計において、複数の未活用労働に関する指標を公表しています。
未活用労働指標についての詳細は、結果表の利用に関する参考資料(未活用労働指標の解説)を御参照ください。
F-12 完全失業者と未活用労働における失業者は何が違うのですか?
完全失業者は、(1)就業しておらず、(2)1週間以内に求職活動を行っていて、(3)すぐに就業できる者です。
未活用労働における失業者は、(2)の求職期間を1か月に拡大して捉えるものです。
詳細は、結果表の利用に関する参考資料(未活用労働指標の解説)を御参照ください。
G.国際比較
G-1 日本は、他の国に比べ失業者の範囲が狭いのですか?
労働力調査における完全失業者の定義は、他の主要先進国と同様、客観的に就業・失業の実態を把握するための定義としてILOの定めた国際基準に準拠したものです。したがって、他の国に比べて日本の完全失業者の範囲が狭いということはありません。
ILOで定めている失業者の定義は、以下のとおりです。
「失業者」は、
1 就業者でなく、
2 直近の特定の期間に、仕事を探す活動を行っており、
3 仕事があれば現に就業可能である、
一定年齢以上の全ての者と定義される。
(参考) 失業者の国際比較(PDF:419KB)
G-2 日本は、アメリカに比べ完全失業率が低め、又は高めに出る傾向がありますか?
日本の労働力調査は、アメリカと同様に、ILOの国際基準に準拠して行われています。日本でもアメリカでも、完全失業者の定義は、(1)「仕事についていない」、(2)「仕事があればすぐつくことができる」、(3)「仕事を探す活動をしていた」者となっており、相互比較は可能です。ただし、各国の就業事情に合わせて、完全失業者の細かい定義には、若干の違いがあります。
例えば、日本では、過去1週間以内に仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた者のほか、過去の求職活動の結果を待っていた者も含めて「仕事を探す活動をしていた」者と定義していますが、アメリカでは、過去4週間以内に仕事を探していた者のみ(過去4週間より前の求職活動の結果を待っていた者は含めない)としており、一概にどちらの失業率が低め又は高めに出るというような傾向はありません。
なお、2018 年から、「完全失業者」に加え、詳細集計において、求職活動期間を過去1か月に拡大した「失業者」や、これに基づき算出した「未活用労働指標1」の公表を行っています。
H.他調査との比較
H-1 厚生労働省が発表している有効求人倍率と完全失業率には、どのような関係がありますか?
有効求人倍率は、全国の公共職業安定所(ハローワーク)に登録された有効求職者数(前月から繰り越された求職者と新規求職者との合計)に対する有効求人数(前月から繰り越された求人と新規求人との合計)の比率であり、「有効求職者1人当たりに有効求人が何件あるか」を表した指標です。
完全失業率も有効求人倍率も景気の動向に連動して変動すると言われていますが、景気動向指数において、有効求人倍率が景気動向におおむね一致して推移する一致系列に位置付けられているのに対して、完全失業率は景気動向に遅れて推移する遅行系列に位置付けられています。つまり、完全失業率は、有効求人倍率に遅れて推移する傾向があるといわれます。
H-2 労働力調査と、厚生労働省の毎月勤労統計調査には、どのような違いがありますか?
労働力調査は「世帯」を対象としているのに対し、毎月勤労統計調査は「事業所」を対象としています。また、そのほかにも、調査の範囲等、以下のような違いがあります。
なお、両統計の労働時間に係る数値の違いについては、F-5を御参照ください。
|
|
労働力調査 |
毎月勤労統計調査 |
|---|---|---|
| 調査実施省 |
総務省 |
厚生労働省 |
| 調査の目的 |
労働力調査は、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。 |
毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とする。 |
| 調査周期 |
毎月 |
毎月 |
| 調査の対象及び範囲 |
世帯 |
事業所 |
| 標本規模 |
約4万世帯、15歳以上の者約10万人 |
全国調査 約33,000事業所 |
| 調査事項 |
【基礎調査票】 【特定調査票】 |
就業形態別常用労働者数、実労働時間数、出勤日数、現金給与額 など |
| 就業者・常用労働者の定義 |
就業者 |
常用労働者 |
| (参考) |
I.データの所在
I-1 都道府県別の完全失業率はないのですか?
完全失業率などの都道府県別結果については、四半期平均の結果を「モデル推計値」として公表しています。
ただし、労働力調査は、日本全体の就業・不就業の実態とその変化を推計することなどを前提として設計された標本調査であり、都道府県別の推計を前提とした標本抽出を行っておらず、標本規模も小さいことなどにより、全国の結果に比べ結果精度が十分に確保できないとみられることから、結果の利用に当たっては注意を要します。
I-2 完全失業率以外の季節調整値は公表していないのですか?
労働力調査結果の季節調整値は、完全失業率以外にも完全失業者数や就業者数などの系列についても公表しています。
現在公表している季節調整値は、「基本集計」の長期時系列データ ![]() の表1や表8に掲載していますので参照してください。
の表1や表8に掲載していますので参照してください。
I-3 転職者のデータはどこにあるのですか?
労働力調査では、現在就業者である者のうち、前職があり、過去1年間に離職を経験した者を「転職者」として集計しています。
「転職者」のデータは、「詳細集計」の長期時系列データ ![]() の表9や表10に掲載していますので参照してください。
の表9や表10に掲載していますので参照してください。
I-4 転職等希望者のデータはどこにあるのですか?
労働力調査では、現在就業者である者のうち、現在の仕事を辞めてほかの仕事に変わりたいと希望している者及び現在の仕事のほかに別の仕事もしたいと希望している者を「転職等希望者」として集計しています。
「転職等希望者」のデータは、「詳細集計」の結果原表 ![]() の第II-14表などに掲載していますので参照してください。
の第II-14表などに掲載していますので参照してください。
J.その他
J-1 完全失業者について、詳細集計の「前職の離職理由」の結果と基本集計の「求職理由」の結果がありますが、どこが違うのですか?
基本集計の「求職理由」は、仕事を探している者について、仕事を探し始めた理由を明らかにしたものです。この場合、仕事を辞めたために仕事を探す場合のみならず、学校を卒業し、新たに仕事を探す場合などが広く含まれます。
一方、詳細集計の「前職の離職理由」は、以前にしていた仕事(現在、仕事をしている者は、今の仕事の前にしていた仕事)について、仕事を辞めた理由を明らかにしています。
このように、両者には、その目的・内容に違いがあることから、結果をみる際には注意が必要です。
(例えば、育児などに専念するために仕事を辞めた場合、前職の離職理由は「結婚・出産・育児のため」となり、その後、収入が新たに必要になったなどの理由により、求職活動を始めた場合には、求職理由について「収入を得る必要が生じたから」となります。)
J-2 労働力調査では、派遣社員の産業について、「派遣元」と「派遣先」のどちらで捉えているのですか?
労働力調査では、2012年まで労働者派遣事業所の派遣社員は、派遣先ではなく、派遣元(雇われている事業所)に関する内容を記入していただいておりましたが、2013年から、産業別の労働投入量を正確に把握できるようにするため、派遣先(実際に働いている事業所)に関する内容を記入していただくようにお願いしています。
また、これに伴い、派遣社員は2012年までは「職業紹介・労働者派遣業」に分類されていますが、2013年からは派遣先の産業それぞれに分類されています。
J-3 労働力調査では、兼業農家についてどのような扱いをしているのですか?
労働力調査では、調査票に記入していただく際、調査期間中に二つ以上の仕事をした人は、そのうち主な仕事(一番長い時間従事した仕事)一つについて記入していただくようにお願いしています(ただし、就業時間・日数、収入については全ての仕事の合算)。
このため、兼業農家の場合、各世帯員について、農業に一番長い時間従事していた場合は農業へ分類されますが、他の産業の仕事を主な仕事としていれば、その産業へ分類されることになります。
J-4 雇用形態別にみた場合、「請負」はどこに区分されるのですか?
労働力調査における雇用形態は、雇用者を勤め先での呼称により区分したものであり、「正規の職員・従業員」、「パート・アルバイト」、「契約社員」、「嘱託」などが雇用者の雇用形態に該当します。
一方、「請負」は、仕事の発注元の会社とそれを請け負う会社(請負会社)との間の契約の一形態であり、雇用者の雇用形態を表すものではありません。
なお、いわゆる「請負労働者」は、当該請負会社における呼称に基づき区分され、「正規の職員・従業員」や「契約社員」、「嘱託」など様々な雇用形態に分類されることとなります。
J-5 官公と公務の違いについて教えてください。
「官公」とは、従業者規模の区分の一つで、官公庁や国営・公営の事業所に雇われているものを区分しています。「官公」には中央官庁、都道府県庁、市区役所及び町村役場のほか、独立行政法人、国・公立の病院、国・公立の学校などに雇われているものも含まれます。
一方、「公務(他に分類されるものを除く)」は産業分類の区分の一つで、日本標準産業分類に基づき、官公署のうち、本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う事業所に雇われているものを区分しています。
つまり、「官公」に分類される国営・公営の事業所に雇われているものであっても、主に公権力によらない業務を行う事業所、例えば国・公立の病院、国・公立の学校や地方自治体の上下水道局、清掃局、交通局などに雇われているものは、「公務(他に分類されるものを除く)」には含まれず、それぞれの事業に基づく産業分類へ区分されることになります。(例えば、国・公立の病院は「医療,福祉」、国・公立の学校は「教育,学習支援業」にそれぞれ分類しています。)
J-6 完全失業率の実態は政府公表の数値よりも高いと一部にいわれていますが、本当なのですか?
完全失業率は、他の主要先進国と同様、ILOの国際基準に準拠して求めた完全失業者数と労働力人口から計算しています。したがって、経済情勢などから、仕事が見つかりそうもないので仕事を探していなかったという人については、ILOの国際基準に準拠した統計を作成するいずれの国(米国、EU諸国、カナダ、韓国など)においても、失業者に含めるような取扱いはしていません。(「失業者の国際比較」(PDF:419KB)参照)
一方で、国際的に見てもパートタイム労働の増加など雇用形態は多様化し、就業・失業の内容も一様ではなくなるなど、就業・不就業を巡る状況は大きく変化し、従来の指標(完全失業率など)だけでは労働市場の状況を必ずしも十分に計測しきれない場合が出てきています。2013年のILO決議においては、経済が利用可能な人的資源をどの程度活用しているか、別の言い方をすると、経済が人口を最大の可能性まで雇用する機会をどの程度与えているか、について評価するための、未活用労働に関する指標の設定が行われました。これを踏まえ、2018年からは、我が国においても、就業者の中でもっと働きたいと考えている者や、非労働力人口の中で働きたいと考えている者などを把握した上で、6つの未活用労働に関する指標を作成し、労働力調査詳細集計において公表しています(「F-11 未活用労働指標とは何ですか?」参照)。
![]() の項目は、 政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。
の項目は、 政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。
