ここから本文です。
個人企業経済調査に関するQ&A(回答)(2018年度まで)
個人企業経済調査とは
1 個人企業経済調査はどのような調査なのですか?
個人企業経済調査は,「製造業」,「卸売業,小売業」,「宿泊業,飲食サービス業」及び「サービス業」を営む「個人経営の事業所」(*) の経営実態を明らかにして,景気動向の把握や中小企業振興のための基礎資料を得ることを目的として実施しており,個人経営の事業所を対象として国が行う調査としては唯一のものとなっています。
この調査では,次の2つの調査を実施しています。
(1)動向調査(動向調査票による調査)
3か月ごとに事業主による業況判断,売上金額などを調査して,個人経営の事業所の景気動向を早く的確にとらえることを目的として,各四半期ごとに実施する調査
(2)構造調査(構造調査票による調査)
事業主の年齢,後継者の有無,事業経営上の問題点,1年間の営業収支,営業上の資産・負債などを調査して,個人経営の事業所の構造的特質を把握することを目的として,毎年3月(年1回)に実施する調査
(*)「個人経営の事業所」とは,具体的には町工場や八百屋,そば屋,クリーニング店など暮らしに密着した個人経営の商店などのことをいいます。
その事業所数は,全国の民営事業所数(約551万事業所)の約38.4%(約212万事業所),従業者数は,全国の民営従業者数(約5,707万人)の約10.5%(約599万人)となっています。(注1)また,その所得額は,国民所得(約388兆円)の約2.3%(約9.0兆円)を占めています。(注2)
(注1)事業所数及び従業者数は,農業・林業・漁業・公務を除いた数。「平成26年経済センサス-基礎調査結果」(総務省統計局)より
(注2)国民所得は,「2015年度国民経済計算」(内閣府)より
2 個人企業経済調査ではどんなことを調べるのですか?
個人企業経済調査は,個人経営の事業所を対象に,
(1)その景気動向を的確にとらえることを目的とする動向調査票による調査(四半期ごと)
(2)その構造的特質を把握することを目的とする構造調査票による調査(年1回)を実施しています。
それぞれの調査票で把握する項目は,次のとおりです。
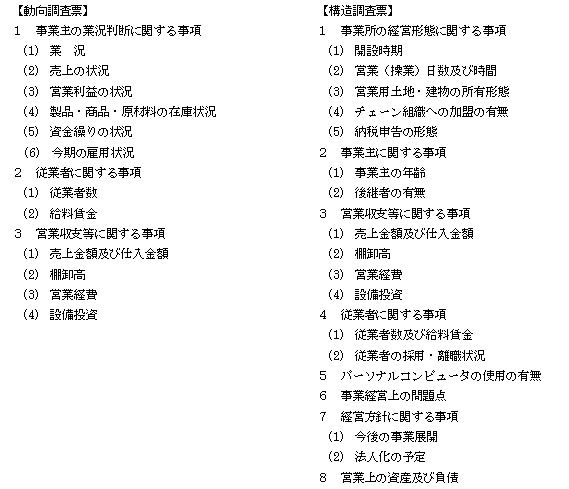
3 個人企業経済調査の結果はどのように利用されているのですか?
個人企業経済調査の結果は,主にGDP(国内総生産)を推計する資料として利用されています。
個人経営の事業所は,全国の民営事業所のおよそ半数を占めており,個人経営の事業所の営業収支や設備投資などの動向は,GDPを推計する上で不可欠な資料となっています。
このほか,中小企業の振興施策の基礎資料,研究機関や金融機関による経済分析・予測などに使用されています。
(参考) 調査結果の活用事例
4 どうしても答えなければいけないのですか?
この調査の基となっている統計法では,報告の義務に関する規定があります。また,報告をしない場合の罰則の規定もあります。
統計調査の趣旨をご理解いただき,調査票への記入をお願いします。
※ 報告義務の規定については「統計法(e-Gov)![]() (平成19年法律第53号)」をご覧ください。
(平成19年法律第53号)」をご覧ください。
5 ほかにも似たような調査があるのではないのですか?
いわゆる「中小企業」といわれる法人組織の事業所を含む中小事業所を対象にした調査はほかにもありますが,「個人」が経営している事業所のみを対象とした調査は,国が行う調査としては,この「個人企業経済調査」のほかにはありません。
個人企業経済調査で調査している項目は,いずれも個人経営の事業所の経済動向や景気動向を把握する上で大切なものとなっており,とりわけ,四半期ごとに公表している個人事業主による景気が「良い」,「悪い」などの業況判断は,この調査でのみとらえることができる項目です。
個人経営の事業所の経営実態を的確に把握し,国の経済施策の基礎資料とするためにも,なくてはならない大切な調査です。
調査方法について
6 個人企業経済調査はどのように行われるのですか?
個人企業経済調査は,総務省統計局が基本的な計画を立案し,都道府県を通じて実施されます。調査事業所には,調査員が訪問し,調査票を配布・回収します。
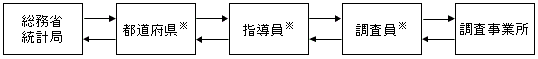
7 調査対象はどのように選ばれるのですか?
個人企業経済調査は,全国の個人経営の事業所の中から,調査対象となる事業所を次のように一定の統計上の抽出方法に基づき抽出します。
(1)全国の市区町村を人口や事業所数などが同じようなグループに分け,各グループの中から調査する市区町村を選びます。
(2)市区町村の中をいくつかの地域に分け,そのうちの一つを調査地域として選びます。
(3)調査地域にある個人経営の事業所の中から,偏りがないように一定の方法に従い,調査対象となる事業所を選びます。
8 別の調査の対象になっていますが,何度も対象とならないように配慮できないのですか?
個人企業経済調査の対象となる事業所は,総務省で整備している「事業所母集団データベース」から選ばれています。事業所母集団データベースには,全国の事業所・企業に関する情報が収められており, 行政機関の行う統計調査の調査対象の抽出に用いられるなど,国や地方公共団体において, 経済統計を正確に作成するための名簿情報の提供及び管理のための重要なインフラとなっています。
このデータベースには,どの事業所が何の調査で対象になったかの履歴も登録されており,できるだけ同じ時期に同じ事業所には調査依頼が重複しないように配慮されています。
しかし,対象となる事業所は,調査の精度を高めるために,地域や事業所の規模のグループ別に選ばれており(これを「層化抽出」といいます。本調査の抽出方法は「抽出方法」をご覧ください。),グループ内で事業所数が少ない場合には,どうしても重複して選ばれることもあります。
以上の趣旨をご理解いただき,調査にご回答くださいますようお願いいたします。
9 調査方法の説明をみると,都道府県を経由して調査を行ったと記載されていますが,具体的には総務省統計局からどのような指示を出して,どのように調査が行われていますか?
調査票記入依頼,取集,検査については,都道府県・指導員の指導により,調査員が行っています。
都道府県・指導員及び調査員のそれぞれの事務の概要は,以下をご参照ください。
都道府県・指導員の主な事務
- 調査員に対する調査方法等の指導(調査員説明会の開催等)
- 調査関係書類・用品の受領及び調査員への配布
- 調査対象事業所の実地確認の指示
- 調査票の内容審査及び統計局への提出
- 調査関係書類の管理
- 安全確保に関する指導
調査員の主な事務
- 調査員説明会への出席
- 調査対象事業所の実地確認
- 調査票の記入依頼(配布)
- 調査票の取集
- 調査票の検査
- 調査票の提出
10 調査員はどのような人がどのような方法で選ばれるのですか?
調査員は,一般の人の中から,次の要件を考慮して選考され,都道府県知事が,特別職の地方公務員として任命します。
- 調査票の配布及び取集,関係書類の作成等の事務を適正に行うことができる者であること。
- 原則として20歳以上の者であること。
- 秘密の保護に関し信頼のおける者であること。
- 税務・警察に直接関係ない者であること。
- 選挙に直接関係ない者であること。
- 企業経理の基本的な知識を有する者であること。
11 前期もこの調査の対象になりました。調査の対象は毎回変わるものではないのですか?
調査の対象となる事業所は,「標本交代」という手法で,四半期ごとに全体の調査事業所の4分の1ずつ交替する方法をとっています。したがって,同じ事業所に対しては,1年間継続するローテーション方式によって調査しています。これは,いっぺんに対象を替えてしまうと,調査の連続性が損なわれてしまうためです。
どうぞ,ご理解の上,本調査にご回答をお願いいたします。
12 調査票には,シャープペンシル又は黒鉛筆で記入しなければならないのですか?
個人企業経済調査は,大量の調査票を短期間のうちに迅速に処理するため,調査票に記入されたマークと数字を機械(光学式文字読取装置)で読み取って統計を作成します。現在のところ,この機械はシャープペンシル又は黒鉛筆で記入しているものが最も確実に読み取ることができますので,シャープペンシル又は黒鉛筆でご記入ください。
13 個人企業経済調査の調査票を調査員からもらいましたが,いつまでにどこに提出すればいいのですか?
ただいま総務省統計局では,個人企業経済調査を実施しております。本調査の趣旨・重要性をご理解いただき,調査員への調査票の提出をお願いいたします。
なお,調査票の記入は,調査書類が入れてある封筒に記載している調査員の訪問日時までにお願いします。(ご都合が悪くなりましたら調査書類が入れてある封筒の連絡先欄に記載している調査員又はお住まいの都道府県の統計主管課までお問い合わせください。)
プライバシーの保護について
14 プライバシーは保護されるのですか?
秘密の保護の徹底
個人企業経済調査は,統計法等の法令規定に基づいて行われます。
調査に従事する人(国・地方公共団体の職員,指導員,調査員)には,調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。また,調査票情報等の利用制限も定められており,秘密の保護の徹底が図られています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され,集計が完了した後は溶解処分されます。
調査員への指導
個人情報の保護を一層徹底させるために調査員用に調査事務マニュアルを作成し,秘密保護等について指導を徹底しています。
調査の結果について
15 調査の結果はいつごろ公表されるのですか?
「動向調査票による調査」の結果は,各調査期の終了月の翌々月中旬に,事業主による業況判断DI(「良い/好転」と回答した割合から「悪い/悪化」と回答した割合を差し引いた値)を「速報」として,また,同下旬に,業況判断DIに加えて,売上高や営業利益などの営業状況や設備投資などの調査結果を「確報」として公表します。
また,「構造調査票による調査」の結果は,動向調査票の1〜3月期の確報結果の公表後,速やかに公表します。
なお,両調査の結果は,公表と同時に統計局ホームページに掲載し,その後報告書を刊行します。
16 統計表に示されている数字は,どうやって計算されていますか? 調査の対象は全事業所ではなく,一部の事業所であり,また,回答しない事業所もあると思いますが,数字に誤差などはありますか?
統計調査の結果には,必ず何らかの誤差が生ずることは避けられません。例えば,標本調査では,調査されなかった調査対象があるので,全数調査を行えば得られたはずの値(これを「真の値」といいます。)と調査結果には差が生じます。全数調査を行わずに標本調査を行ったことにより生ずる差のことを「標本誤差」といいます。
また,全数調査を行ったとしても,例えば誤回答や未回答などによる誤差があり,これを「非標本誤差」といいます。非標本誤差には,調査を行う段階で発生する様々なものがあります。詳細については,以下のリンクをクリックしてご覧ください。
- 回答をしなかったことにより生ずる誤差(これを「非回答誤差」といいます。)
- 集計の際の誤りによる誤差(これを「データ処理による誤差」といいます。)
- 標本が正しく母集団の縮図となっていなかったことによる誤差(これを「カバレッジ誤差」といいます。)
- 調査票のデザイン,回答者のミスなどによる誤差(これらを総称して「測定誤差」といいます。)
標本誤差とは
調査の結果は,標本調査で調査票が回収された標本から得られた推定値なので,標本誤差を含んでおり,全数調査をすれば得られるはずの値(以下「真の値」といいます。)とは必ずしも一致しません。集計結果の推定値には,標本調査による一定の統計的誤差を含んでいます。
「推定値の標準誤差等」に示した「標準誤差率」は,全数調査を行った場合に得られるはずの「真の値」の存在範囲を示す目安となるものです。推定値を中心として,その前後に標準誤差の2倍の幅を取れば,その区間内に真の値があることが約 95%の確率で期待されます(20回のうちおおよそ19回は正しい)。
非標本誤差とは
非標本誤差には,非回答誤差,カバレッジ誤差,データ処理による誤差,回答者の誤りによる誤差などがあり,調査の過程において介在する人間が多くなれば,それだけ非標本誤差も大きくなります。このような誤差は,標本誤差と違って,どの程度の誤差が発生しているのか,数字で評価することができません。したがって,調査の設計の際には細心の注意を払って、なるべく起こらないようにすべきであることから,本調査での取組みを以下のとおり紹介します。
非回答誤差を減らすための取り組み
調査では,集計対象となる調査項目についてはすべて回答してもらうのが原則ですが,必ずしも調査項目がすべて正確に回答されているわけではありません。このような回答誤りや回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい,記入要領による丁寧な説明など,また提出後には回答誤り等の部分の調査員による確認などの方法で,できるだけ減らすように努めなければなりません。
本調査では,非回答を減らすために,次のような方法をとっています。
- 記入要領での説明
記入要領では,できるだけ回答誤り等をなくすために,実際の調査票の上に記入が必要な部分(項目)が明確になるように枠で囲い,さらに記入上の注意点については記入部分に吹き出しを利用して注意喚起をしています。 - 調査員による検査
調査員が調査票を回収した際に,回答漏れをチェックして,その場で再回答をお願いしました。また,回収後に調査員,指導員等により調査票を目視して回答誤り等を発見した場合には,再回答をお願いしました。
データ処理による誤差を減らすための取り組み
非標本誤差のうち,調査票の回答内容を電子化して,これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。
このうち代表的な誤差は,データを電子化(データパンチ)する際にパンチする人間が介在するため,この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。
本調査では,データを電子化する際に人間を介在させずに,調査票に記入されたマークと数字を機械(光学式文字読取装置)で読み取って統計を作成するようにしています。しかし,この機械の読み取りの際にも機械的なエラーが発生する可能性があるため,調査票等配布書類や調査票の記入方法において,機械が読み取りやすいシャープペンシル又は黒鉛筆の使用と,読み取りやすい数字の記入例を示して,できるだけエラーをなくするように努めています。
カバレッジ誤差を減らす取り組み
調査では調べる対象となる「母集団」(これを「目標母集団」といいます。)があり,標本調査の場合は,この母集団に相当する名簿(これを「枠母集団」又は「標本抽出枠」といいます。)から標本抽出(サンプリング)を行いますが,目標母集団と枠母集団が必ずしも一致しているとは限らず,それによって生じる誤差を「カバレッジ誤差」といいます。
個人企業経済調査では,「製造業」,「卸売業,小売業」,「宿泊業、飲食サービス業」及び「サービス業」(調査対象産業の詳細は「調査の対象」を参照)の事業所を母集団とし,標本抽出枠は総務省で整備している「事業所母集団データベース」を用いていますが,この名簿は「経済センサス‐基礎調査」を基に各種行政記録情報等により整備されたものなので,廃業,新設などによるカバレッジ誤差が発生する可能性はありますが,きわめて小さいものと評価できます。
測定誤差を減らす取り組み
もともと測定誤差とは,自然科学の分野で,ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで,その原因は測定機器の不完全さ,測定者の能力による違い,測定条件の変動などによるものです。
調査の分野でも,測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いなどによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤差,測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。
個人企業経済調査では,調査票の作成段階における言葉遣いなどの細心の注意,調査員に対する研修・指導の徹底などを行い,これらの測定誤差をできるだけ減らすように努めています。
17 調査票に回答がなかった場合は,集計の際にどのように処理していますか?また,行政記録情報を利用した補足・訂正は行っていますか?
個人企業経済調査では,調査票がほぼ100%提出されているため,回収率の補正などは行っておりませんが,棚卸高等の一部項目における欠測値や記入内容の矛盾などについては,調査票を集計する前段階で,調査対象事業所への照会をしてもなお欠測値や矛盾が生じた場合は同期同産業の状況をもとに補足・訂正を行いました。
なお,行政記録情報については,本調査で集計する項目で使用できる行政記録情報が存在しないため使用してはいません。
18 調査対象の個人企業の中には,売上高等が大きな個人企業も含まれることもあると思いますが,その場合,そのまま平均値を算出すると実態とはかけ離れた数値になるのではないですか?
個人企業経済調査では,産業別にみて,特に売上高等が大きい場合は,調査客体に対し重点的な確認を依頼し,その確認結果を基に訂正をし,集計を行っています。
19 個人企業経済調査ではわからない大企業や中小企業(法人)の景気動向について知りたい。
次の内容を知りたい場合は,以下の表を参考にしてください。
| 知りたい内容 | 調査名等 |
|---|---|
| 大企業の景気動向 | 日銀短観(日本銀行) |
| 中小企業(法人)の景気動向 | 中小企業景況調査(中小企業庁) |
