ここから本文です。
平成16年全国消費実態調査 調査の概要
1 調査の目的
全国消費実態調査は,国民生活の実態について,家計の収支及び貯蓄・負債,耐久消費財,住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し,全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準,構造,分布などを明らかにすることを目的とした調査である。
この種の調査としては毎月実施されている家計調査があるが,その主な目的が全国平均の家計収支の時系列の動きを明らかにすることにあるため,調査規模が約8,000世帯と小さく,詳細な構造分析を行うことができない。そこで,今回の全国消費実態調査では,家計調査からは得られない詳細な結果を得るために標本数を約59,400世帯(うち単身世帯約5,000世帯)とし,年間収入階級別,世帯主の年齢階級別などの各種世帯属性別あるいは地方別,都道府県別などの地域別に家計の実態を種々の角度から分析している。
特に今回の調査では,急速に進む高齢化の中で,高齢者介護の負担が世帯の経済状況に与える影響が着目されていることから,要介護認定者のいる世帯における家計収支の状況を明らかにするとともに,近年,IT関連機器の普及が急速に進んでおり,インターネットを介した商品の購入も活発になってきている状況を踏まえ,家計の消費におけるインターネット利用の実態を明らかにすることをねらいとしている。
調査の内容は,過去9回の調査と同様に,家計上の収入と支出,主要耐久消費財の所有数量,貯蓄現在高及び借入金残高(昭和44年調査から開始)を調査し,昭和39年調査から昭和59年調査まで調査していた品目の購入先は平成6年調査から再び調査をしている。
2 調査の沿革
全国消費実態調査は,昭和34年の第1回調査以来5年ごとに実施されており,平成16年全国消費実態調査はその10回目に当たる。
3 調査の根拠法令
平成16年全国消費実態調査は,統計法(昭和22年法律第18号)による指定統計調査(指定統計第97号)として,全国消費実態調査規則(昭和59年4月20日総理府令第23号)に基づいて実施された。
4 調査の対象
全国のすべての世帯のうち,総務大臣の定める方法により選定された世帯を対象とし,二人以上の世帯と単身世帯とに分けて調査を実施した。
なお,次に掲げる世帯は,世帯としての収入と支出を正確に計ることが難しいことなどの理由から調査の対象から除外した。
(1)二人以上の世帯
- 料理飲食店又は旅館を営む併用住宅の世帯
- 下宿屋又は賄い付きの同居人のいる世帯
- 住み込みの雇用者が4人以上いる世帯
- 外国人世帯
(2)単身世帯
- 15歳未満の人
- 二人以上の世帯の対象除外(a,b及びd)に該当する人
- 雇用者を同居させている人
- 学生
- 社会施設及び矯正施設の入所者
- 病院及び療養所の入院者
5 抽出方法(調査対象の選定)
調査対象の選定は,二人以上の世帯と単身世帯とに分けて行った。
(1) 二人以上の世帯
a. 調査市町村の選定
市については,平成16年1月1日現在のすべての市(680市)を調査市とし,町村については,平成16年1月1日現在の2,497町村から458町村を選定した。
b. 調査単位区の選定
調査市町村から,合計4,531調査単位区(1調査単位区は平成12年国勢調査の近隣する2調査区)を選定した。
c. 調査世帯の選定
各調査単位区から12世帯を系統抽出し,全国で54,372世帯を選定した。
(2) 単身世帯
単身世帯を,一般の単身世帯(一人で一戸を構えて住んでいる人,間借り又は下宿等の単身世帯及び30人未満の規模の寮・寄宿舎に居住する単身世帯)と30人以上の寮・寄宿舎に居住する単身世帯とに分けて選定した。
a. 調査単位区及び寮・寄宿舎の選定
一般の単身世帯については,二人以上の世帯を調査する全国の調査単位区のうちから選定した。
また,寮・寄宿舎については,全国の30人以上の寮・寄宿舎のうちから100の寮・寄宿舎を選定した。
b. 調査世帯の選定
一般の単身世帯については,4,402世帯,30人以上の寮・寄宿舎に居住する単身世帯については600世帯(一つの寮・寄宿舎から6世帯),合計5,002世帯を選定した。
※ 調査対象の選定方法についての詳細は,「用語の解説」ページの「付7.調査世帯の選定方法と結果の推定式」に示すとおりである。
6 調査事項
調査世帯について,次の事項を調査した。
(1) 家計上の収入と支出に関する事項
収入は,勤労者世帯及び無職世帯についてのみ,その種類と金額を調査するとともに,収入に伴う控除(税金,社会保険料など)についても,その種類と金額を併せて調査した。また,現物収入は,品目ごとに,その入手方法,品名及び見積り金額を調査した。
支出は,すべての世帯について,現金支出,口座自動振替による支払及びクレジットカード,掛買い,月賦による支払いに分けて,品名,用途及び支出金額を調査した。
(2) 品物の購入先に関する事項
購入したすべての品物(サービス料などを除く)について,その購入先の販売形態別(一般小売店,スーパー,コンビニエンスストア,百貨店,生協・購買,ディスカウントストア・量販専門店,通信販売(インターネット),通信販売(その他),その他)に調査した。なお,購入先は11月のみ調査した。
(3) 主要耐久消費財等に関する事項
耐久消費財は,家具類,冷暖房用器具,一般家事用品,教養娯楽用品,自動車など約40品目について所有数量を,うち約20品目については,取得時期(過去1年以内,過去1年〜5年以内,過去5年を超える時期)について調査した。
(4) 年間収入及び貯蓄・借入金残高に関する事項
年間収入は,世帯主,世帯主の配偶者,その他の世帯員(65歳以上,65歳未満)について,過去1年(平成15年12月〜16年11月)の収入を種類別に調査した。
貯蓄は,預貯金(郵便局,銀行,社内預金など),生命保険掛金などの払込総額,信託,株式及び債券などの有価証券について,種類ごとに平成16年11月末の現在高を調査した。なお,個人営業世帯などの貯蓄には,家計用だけでなく営業のための分も含めて調査した。
借入金残高は,月賦・年賦の未払残高,住宅の購入・建築・増改築,土地の購入のための借入金残高及びそれ以外の借入金残高について,平成16年11月末の現在高を調査した。
(5) 世帯及び世帯員に関する事項
世帯員については,氏名,世帯主との続き柄,性別,年齢,就業・非就業の別のほか,産業及び職業を,在学者の場合は就学状態などを調査した。
このほか,世帯員以外の家族の不在理由,要介護認定者の有無,世帯主の子の住んでいる場所,単身世帯については,単身赴任,出稼ぎなど世帯の形態について調査した。
(6) 現住居及び現住居以外の住宅・宅地に関する事項
現在住んでいる住居については,住居の構造,延べ床面積,建て方,所有関係,設備,地代の有無(持ち家のみ),敷地面積(持ち家のみ),建築時期(持ち家のみ)及び入居時期(持ち家以外)を,現在住んでいる住居以外の住宅・宅地については,用途,住居の建築時期,延べ床面積,構造,所在地,敷地面積を調査した。
7 調査の時期及び調査の方法
二人以上の世帯については,平成16年9月,10月及び11月の3か月間,単身世帯については,10月及び11月の2か月間調査を実施した。
「6 調査事項」の「(1) 家計上の収入と支出に関する事項」については,二人以上の世帯では9月1日〜11月30日の3か月間,単身世帯では10月1日〜11月30日の2か月間,調査世帯が1か月1冊の家計簿に毎日の収入(勤労者世帯及び無職世帯のみ)と支出を記入し,調査員がこれを集めた。
なお,家計簿は,収入と支出を記入する「家計簿A」と収入と支出のほかに「6 調査事項」の「(2) 品物の購入先に関する事項」を記入する欄を設けた「家計簿B」の2種類を用い,9月,10月(単身世帯は10月のみ)は「家計簿A」,11月は「家計簿B」により調査した。
「6 調査事項」の「(3) 主要耐久消費財等に関する事項」については,調査世帯が「耐久財等調査票」に10月末現在で記入し,調査員がこれを集めた。
「6 調査事項」の「(4) 年間収入及び貯蓄・借入金残高に関する事項」については,調査世帯が「年収・貯蓄等調査票」に11月末現在で記入し,調査員がこれを集めた。
「6 調査事項」の「(5) 世帯及び世帯員に関する事項」,「(6) 現住居及び現住居以外の住宅・宅地に関する事項」については,二人以上の世帯は9月1日現在で,単身世帯は10月1日現在で調査世帯が「世帯票」に記入し,調査員がこれを集めた。
| 調査票の種類 | 調査事項 | 調査期日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二人以上の世帯 | 単身世帯 | ||||||||
| 家計簿A |
|
9月,10月の2か月間 | 10月の1か月間 | ||||||
| 家計簿B |
|
11月の1か月間 | |||||||
| 耐久財等調査票 | 主要耐久消費財(40数品目)に関する事項 | 10月末日現在 | |||||||
| 年収・貯蓄等調査票 | 年間収入,貯蓄現在高,借入金残高などに関する事項 | 11月末日現在 | |||||||
| 世帯票 | 世帯,世帯員及び住宅・宅地に関する事項 | 9月1日現在 | 10月1日現在 | ||||||
※調査票は,調査票のページに示すとおりである。
8 調査の流れ
調査は,次の流れにより,調査員が調査世帯ごとに調査票を配布,取集及び質問することにより実施した。
総務大臣 ― 都道府県知事 ― 市町村長 ― 指導員 ― 調査員 ― 調査世帯
個人収支簿による調査の概要
1 調査の目的
近年の所得水準の向上,国民生活の多様化及び個人意識の高まり等により,世帯において個人の自由にできる収入及び支出が増加して,家計簿のみでは世帯におけるすべての消費実態を把握することが困難になってきている。
そこで,家計簿に加えて「個人収支簿」を導入し,世帯員ごとに個人の自由裁量による収支を記入してもらうことにより,使途不明のこづかい等の内訳を解明するとともに,消費構造の詳細な把握,個計化の状況把握のためのデータを得ることを目的とする。
2 調査の範囲
(1) 調査市町村
平成16年9月1日現在で家計調査の対象となっている168市町村。
(2) 調査単位区
上記の調査市町村のうち,平成16年3月,4月及び5月に家計調査を開始した単位区において調査した。
(3) 調査世帯
それぞれ8月,9月及び10月に家計調査の家計簿の記入が終了した二人以上の世帯で,調査単位区ごとに6世帯のうち1世帯を抽出し,全国で673世帯について調査した。
3 調査の期間
平成16年9月〜11月。
「個人収支簿」及び「家計簿C」(個人収支簿による調査世帯用)に記入してもらう期間は,家計調査の家計簿記入終了月の翌月1か月間。
4 調査事項及び調査の方法
(1) 調査事項
「個人収支簿」及び「家計簿C」により,次の事項を調査した。
「個人収支簿」は,各調査月の1日現在で18歳以上の世帯員(家計簿記入者を除く。)について,個人的な収支の内訳とその金額。
「家計簿C」は,家計のこづかいに関する支出のみの内訳とその金額。
| 調査票の種類 | 調査事項 | 調査期日 |
|---|---|---|
| 個人収支簿 | 18歳以上の世帯員(家計簿記入者を除く。)の個人的な収支 | 9月〜11月のうち1か月間 |
| 家計簿C | 家計のこづかいに関する支出 | 9月〜11月のうち1か月間 |
※調査票は,調査票のページに示すとおりである。
(2) 調査の方法
「個人収支簿」及び「家計簿C」は調査世帯員及び調査世帯の自計申告により調査した。
「個人収支簿」は調査世帯員が密封し,「家計簿C」と共に全国消費実態調査員が収集した。
(注) 個人的な収支とは,個人の自由裁量による収支のことをいう。
個人収支項目分類については,「用語の解説」ページの「付2.個人収支項目分類表」に示すとおりである。
調査の変遷
今回の調査の概念,定義について,過去の調査(昭和34年,39年,44年,49年,54年,59年,平成元年,6年,11年)からの変遷は以下のとおりである。
1 調査対象
(1) 昭和47年5月に本土復帰した沖縄県は,昭和49年調査から調査地域に加えた。
(2) 昭和44年調査以前の調査では,農林漁業を営む世帯は調査の対象から除外していたが,昭和49年調査から世帯主が専ら又は主として農林漁業を営む世帯についてのみ不適格世帯とし,兼業農家は調査の対象とした。昭和59年の調査からは,農林漁業を営む世帯を含むすべての世帯を調査の対象とした。
(3) 昭和39年調査以前の調査では,単身世帯は人口5万以上の市の勤労者世帯のみを調査の対象としていたが,昭和44年調査から調査市町村の範囲を人口5万未満の市及び町村に拡大するとともに,勤労者世帯以外の世帯も調査した。
(4) 単身世帯は昭和34年以降昭和54年調査まで10月及び11月の2か月間調査したが,昭和59年調査では,11月の1か月間のみ調査した。平成元年調査からは昭和54年調査までと同様,10月及び11月の2か月間調査し,平成16年調査も10月,11月の2か月間調査した。
2 調査事項
(1) 家計支出について,昭和44年調査以前の調査では,個々の品目ごとに支出金額等を調査していたが,昭和49年調査から一部の品目でまとめて支出金額を調査する方法を採用した。 平成16年調査では,個々の品目ごとに支出金額等を調査した。
昭和59年調査以前の調査では,固定項目以外の各品目ごとに購入した数量を金額とともに記入することとしていたが,平成元年調査から数量の記入を廃止した。
また,平成元年調査で調査項目から除外した家計簿11月分の購入先調査を平成6年調査から再び調査し,平成16年調査も購入先を調査した。
(2) 年間収入,貯蓄及び負債現在高と住宅・土地の取得計画に関する事項は,昭和44年調査から調査した。 また,住宅・土地の取得実績については,昭和49年調査から調査した。 平成元年調査以降,住宅・土地の取得計画及び取得実績を調査事項から除外し,現住居以外に所有している住宅・宅地については,延べ床面積等を調査した。
(3) 主要耐久消費財については,昭和49年調査まで調査していた衣料品を,昭和54年調査以降は調査品目から除外した。 また,昭和59年調査に調査した主要耐久消費財の購入形態(月賦・クレジットカードによる購入)を平成元年調査以降は除外した。 昭和59年調査に調査した主要耐久消費財の購入動機(新規購入,買い替え,買い増し)は平成元年調査で除外したが,平成6年調査では新規・買い増し,買い替えの項目で調査した。 また,平成元年調査で調査した取得時期を,平成6年調査では過去1年間の取得数量の項目で調査した。 平成11年調査では約40品目のうち約20品目について取得時期を過去1年以内,過去1年〜5年以内,過去5年を超える時期の項目で調査し,平成16年調査も同様の項目で調査した。
3 分類基準
(1) 都市階級,4大都市圏
各地域に含まれる調査市町村を過去9回の調査と今回調査とで比較すると,次のとおりである。
調査市町村数
| 昭和 34年 |
39年 | 44年 | 49年 | 54年 | 59年 | 平成 元年 |
6年 | 11年 | 16年 | |
| 全国 | 797 | 814 | 866 | 997 | 1,081 | 1,112 | 1,191 | 1,150 | 1,142 | 1,138 |
| 全都市 | 544 | 559 | 565 | 643 | 647 | 652 | 656 | 664 | 671 | 680 |
| 人口5万以上の市 | 260 | 273 | 299 | 337 | 382 | 405 | 424 | 436 | 447 | 450 |
| 大都市 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| 中都市 | 48 | 63 | 85 | 103 | 110 | 116 | 118 | 123 | 127 | 132 |
| 小都市A | 206 | 203 | 207 | 226 | 262 | 278 | 295 | 302 | 309 | 304 |
| 小都市B | 284 | 286 | 266 | 306 | 265 | 247 | 232 | 228 | 224 | 230 |
| 町村 | 253 | 255 | 301 | 354 | 434 | 460 | 535 | 486 | 471 | 458 |
| 関東大都市圏 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 164 |
| 京浜葉大都市圏 | − | − | − | − | − | − | − | 161 | 165 | − |
| 京浜大都市圏 | − | 90 | 106 | 123 | 135 | 138 | 147 | 153 | 157 | − |
| 中京大都市圏 | − | 30 | 46 | 57 | 63 | 63 | 65 | 64 | 63 | 65 |
| 京阪神大都市圏 | − | 65 | 81 | 90 | 92 | 95 | 101 | 96 | 108 | 102 |
| 北九州・福岡大都市圏 | − | 15 | 25 | 33 | 39 | 43 | 42 | 46 | 47 | 44 |
(2) 住居の所有関係
過去9回の調査と今回調査の分類を比較すると,次のとおりである。
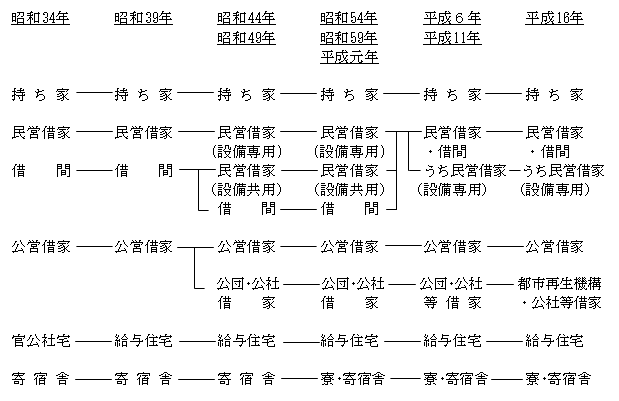
昭和44年及び昭和49年調査の住宅の所有関係別の表の一部では,「民営借家(設備共用)」と「借間」をまとめて「民営借家(設備共用)・借間」として,昭和44年調査の表の一部では「公営借家」と「公団・公社借家」をまとめて「公営・公団・公社借家」として表章した。 昭和54年から平成元年までの調査では,「民営借家(設備共用)」と「借間」をまとめて「民営借家(設備共用)・借間」として表章した。
平成6年調査からは,「民営借家(設備専用)」,「民営借家(設備共用)」及び「借間」をまとめて「民営借家・借間」として表章し,そのうち「うち民営借家(設備専用)」を表章した。 一部の表では「公営借家」と「公団・公社等借家」をまとめて「公営借家,公団・公社等借家」として表章している。
また,昭和44年調査からは,二人以上の世帯で「寮・寄宿舎」に居住する場合は「給与住宅」に含めている。
平成11年調査から表の一部では,「持ち家」を「持ち家(世帯主又は家族の名義)」,「持ち家(世帯主又は家族以外の名義)」と名義別に表章している。
(3) 世帯類型(子供構成)
昭和44年調査では,4人以上の世帯については,すべての子供の年齢,就学状態により世帯を区分したが,昭和49年調査からは,長子の年齢,就学状態により世帯を区分した。 なお,昭和54年調査から,子供構成を世帯類型に,平成11年調査からは,世帯類型のうち「片親と子供の世帯」を「男親又は女親と子供の世帯」に名称変更した。
