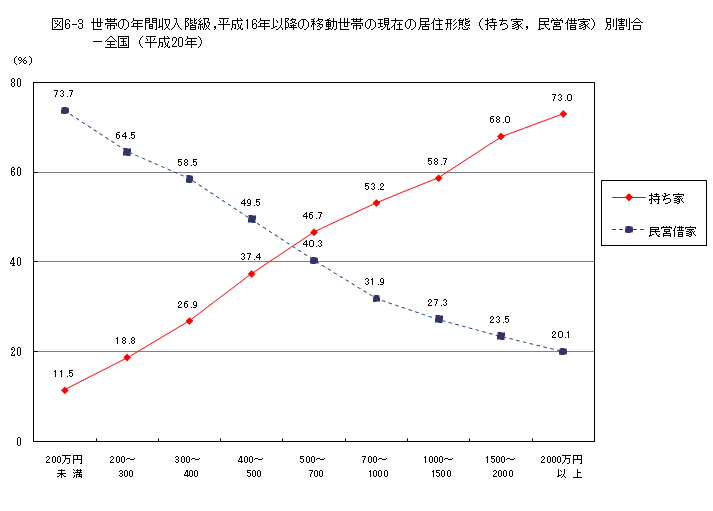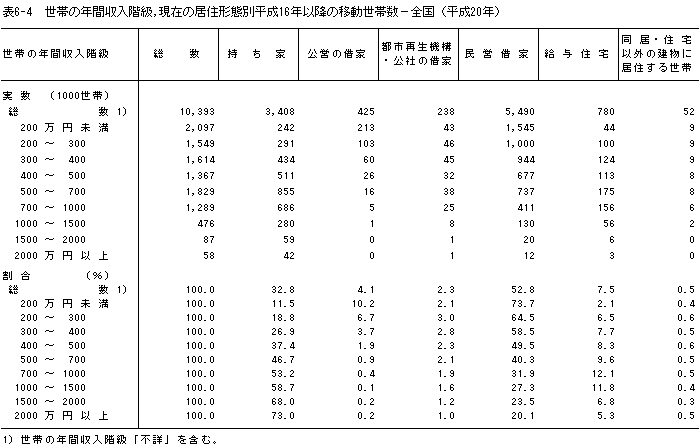ここから本文です。
6-1 入居時期
普通世帯の半数以上が昭和56年以降に現住居に入居
普通世帯を家計主の現住居への入居時期別にみると,「昭和25年以前」が283万世帯で全体の5.7%,「昭和26年〜35年」が205万世帯(4.1%),「昭和36年〜45年」が309万世帯(6.2%),「昭和46年〜55年」が525万世帯(10.5%),「昭和56年〜平成2年」が530万世帯(10.6%),「平成3年〜12年」が763万世帯(15.3%),「平成13年〜17年」が758万世帯(15.2%),「平成18年〜20年9月」が677万世帯(13.6%)となっており,普通世帯の半数以上が昭和56年以降に現住居へ入居している。
<表6−1>
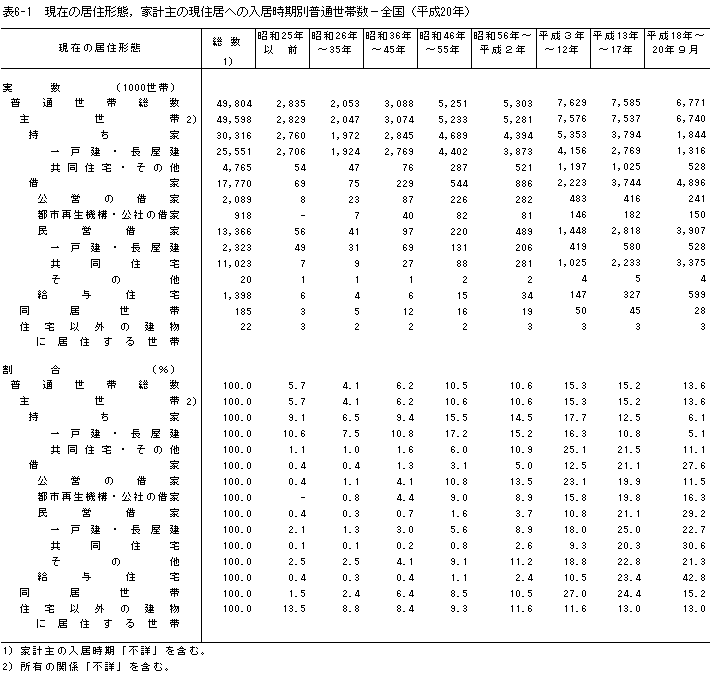
平成13年以降に入居した世帯の割合は持ち家よりも借家が高い
家計主の現住居への入居時期を現在の居住形態別にみると,持ち家に居住する世帯は「昭和46年〜55年」が469万世帯で普通世帯全体の15.5%,「昭和56年〜平成2年」が439万世帯(14.5%),「平成3年〜12年」が535万世帯(17.7%),「平成13年〜17年」が379万世帯(12.5%),「平成18年〜20年9月」が184万世帯(6.1%)などとなっている。これに対し,借家に居住する世帯は「昭和46年〜55年」が54万世帯(3.1%),「昭和56年〜平成2年」が89万世帯(5.0%),「平成3年〜12年」が222万世帯(12.5%),「平成13年〜17年」が374万世帯(21.1%),「平成18年〜20年9月」が490万世帯(27.6%)などとなっており,入居時期が平成12年以前では持ち家が,平成13年以降では借家がそれぞれ高くなっている。
「平成18年〜20年9月」の2年9か月間に入居した世帯の割合を借家の内訳別にみると,給与住宅が42.8%と最も高く,次いで民営借家(共同住宅)が30.6%,民営借家(一戸建・長屋建)が22.7%などとなっているが,公営の借家は11.5%,都市再生機構・公社の借家は16.3%と,公共の住宅で低い割合となっている。
<表6−1>
移動率は昭和48年以降低下
平成16年以降(調査前4年9か月間)に現住居へ入居した普通世帯(以下「平成16年以降の移動世帯」という。)は1039万世帯で,普通世帯全体に占める割合(移動率)(注)は20.9%となっている。移動率の推移をみると,昭和48年の38.7%から低下を続けており,平成20年は15年(24.1%)に比べ3.2ポイント低下している。
<図6−1>
(注)移動率とは,普通世帯全体に占める調査前4年9か月間に現住居へ入居した普通世帯の割合をいう。
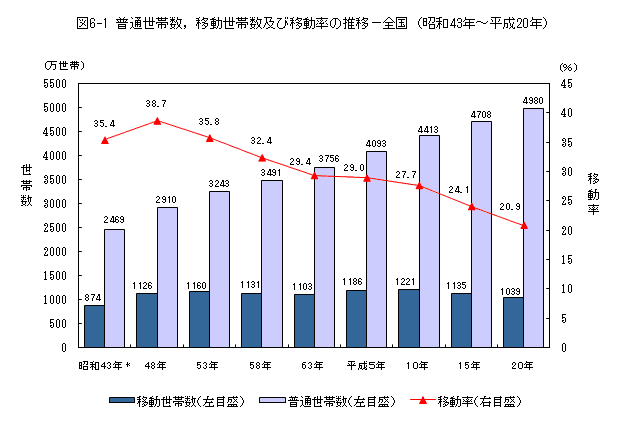
移動率は年齢階級が高くなるほど低下
平成16年以降の移動率を家計主の年齢階級別にみると,「25歳未満」が63.3%と最も高くなっているのに対し,「60歳以上」は7.5%と最も低くなっており,年齢階級が高くなるほど低下している。
平成15年と比べると,全ての年齢階級で低下しており,「25歳未満」が6.9ポイント,「25〜29歳」が7.1ポイント,「30〜39歳」が3.8ポイント低下などとなっている。
また,従業上の地位別にみると,「自営業主」は13.5%,「無職」は15.0%となっているのに対し,「雇用者」は33.3%と倍以上になっている。平成15年と比べると,いずれも低下している。
<表6−2>
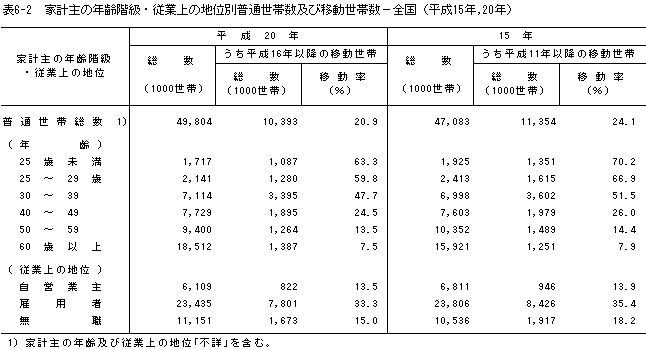
年齢,収入が高い世帯は持ち家へ移動する割合が高い
平成16年以降の移動世帯を現在の居住形態別にみると,持ち家は341万世帯で平成16年以降の移動世帯全体の32.8%,公営の借家は42万世帯(4.1%),都市再生機構・公社の借家は24万世帯(2.3%),民営借家は549万世帯(52.8%),給与住宅は78万世帯(7.5%)などとなっており,平成16年以降の移動世帯のうち半数以上が民営借家に移動している。
現在の居住形態別割合を家計主の年齢階級別にみると,持ち家は「25歳未満」が1.7%と極めて低くなっているが,「40〜49歳」が44.2%,「50〜59歳」が43.8%,「60歳以上」が44.6%と年齢階級が高くなるほど高い傾向にある。一方,民営借家は「25歳未満」が87.6%と約9割となっており,「25〜29歳」が71.4%,「30〜39歳」が51.3%など,年齢階級が高くなるほど低くなっている。
<図6−2,表6−3>
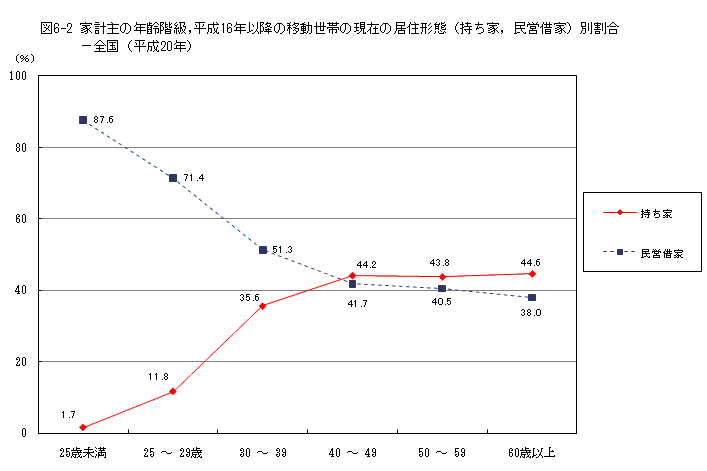
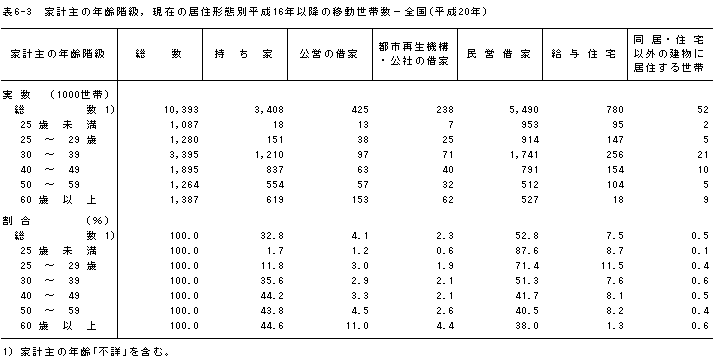
現在の居住形態別割合を世帯の年間収入階級別にみると,500万円未満の各階級は民営借家が最も高く,500万円以上の各階級は持ち家が最も高くなっている。持ち家は「200万円未満」の11.5%から収入が高くなるほど割合が高くなっており,「2000万円以上」では73.0%と7割を超えている。一方,民営借家は「200万円未満」の73.7%から収入が高くなるほど割合が低くなっている。
<図6−3,表6−4>