ここから本文です。
平成23年社会生活基本調査への期待
| 慶應義塾大学経済学部教授 津谷 典子 |
| わが国の生活時間調査である社会生活基本調査は、昭和51年以来実施されており、今回の調査は第8回目に当たります。わが国をはじめとするポスト工業化社会に生きる人々の多くは、睡眠時間を除く1日の大半を仕事と家庭生活に費やしています。時間は限りある資源であり、特に時間に追われる現代社会では仕事と家庭のバランスをとることが難しくなってきています。社会生活基本調査により示される「仕事と家庭のインターフェイス」は、ポスト工業化社会における我々の生活の質(Quality of Life)を探るうえで重要な手がかりを与えてくれます。 社会生活基本調査により収集される男女の就業時間と家庭内労働時間のデータは、国際的に注目されるジェンダー統計でもあります。例えば、女性のエンパワーメントに関する国連の出版物においても、社会生活基本調査によって収集された時系列データがたびたび取り上げられ、国際比較分析に用いられています。その一方で、国際比較に相応しい生活時間に関する長期の時系列データは数少ないこともまた事実です。アメリカやイギリスやノルウェーなど少数の先進国では比較的長期にわたる時系列データが存在しますが、それらは概ね10年かそれ以上の長い間隔で収集されたものであり、1976(昭和51)年以来5年毎に実施されているわが国の社会生活基礎調査は、国際的にも非常に貴重なものであると言えましょう。 さらに、家事、育児、介護・看護などに費やす時間により測定される家庭内労働時間における男女分担パターンは、家庭内ジェンダー関係を示す指標としても重要です。わが国の男性の家庭内労働分担割合はOECD加盟国の中でも最も低い水準にあり、伝統的家庭内ジェンダー関係が根強く残っていることが示唆されます。近年の女性の高学歴化や雇用労働力化を背景として、この伝統的色彩を色濃く残す家庭内ジェンダー関係は、急速に進行する未婚化と歯止めのかからない少子化の主な要因となっているのではないでしょうか。この意味でも、今回の社会生活基本調査は、今後のわが国の少子化対策やワーク・ライフ・バランス推進のための施策のために貴重な情報を提供することが期待されます。 回答者および調査員の方々の負担は大きいとは思いますが、わが国および国際的政策にとってのみならず、我々の生活と今後の日本社会にとっても今回の調査は有用かつ重要であることをご理解頂き、調査にご協力くださるようお願い致します。 |
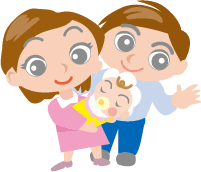 |
