ここから本文です。
「社会生活基本調査」の社会的意義
| 東京大学社会科学研究所准教授 佐藤 香 |
| 私たちの生活,というよりも人生を豊かにする資源は,大きく分けて3つある。第一は経済的資源,いわゆる経済力,第二は人間的資源,家族や友人・知人のネットワークである。第三は時間的資源で,ゆとりのある暮らしかたを可能にするものである。高度経済成長の終了後,第一の資源だけでは「生活の豊かさ」を計測できないことが明らかになった。そこで注目されたのが第二,第三の資源であった。 第一・第二の資源は,人によって保有量が異なる。経済格差が問題になるのは,保有量,すなわち利用量が異なるため生活に大きな違いが生じるためである。ところが,第三の時間的資源は他の資源とは違い,誰でも一日24時間の等しい量を保有している。保有量が等しいため人びとが格差に気づくことは少ないが,保有量は同じであるのに利用のありかたで生活が大きく異なる。睡眠時間を削って働く人とワーク・ライフ・バランスのある生活をしている人とでは,生活の質や豊かさは大きく異なる。 こうした格差ともいえる生活実態を明らかにするためには,時間的資源の利用についての詳細な調査が不可欠である。ここに焦点をあてた「社会生活基本調査」の意義について広く社会的な理解が得られることが望まれる。 |
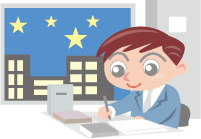 |
