ここから本文です。
平成23年社会生活基本調査に期待すること
| 名城大学経済学部教授 勝浦 正樹 |
| 昭和51 (1976) 年の第1回調査以来5年毎に実施されてきた社会生活基本調査は,今回の平成23 (2011) 年調査で8回目を迎えます。 社会生活基本調査は,国民の生活時間と余暇活動を調査する大規模な標本調査で,調査時点の国民生活の状況を把握するための構造統計としての性格が 強いのですが,35年という非常に長い間継続して調査され,その結果が蓄積されているので,国民生活がどのように変化してきたのかをみるとともに, 今後の生活像を予想するための重要な情報源として役に立つと思います。 低下するスポーツの行動者率たとえば,国民の健康を守ることは国家として当然のことですが,高齢化などに伴う昨今の医療費の増大は大きな問題で,医者にかからずに健康を保つようにすることも大切です。 そのためには,スポーツなどの余暇活動を広く国民が実施することもポイントになりますが,その実施状況は社会生活基本調査の結果からみることができます。 ところがスポーツの実施率(社会生活基本調査では行動者率と言います)をみると,年々低下しているのです。平成18年調査でのスポーツの行動者率は約65%で, 平成13年調査よりも約7ポイントもの低下を示しました。この低下の原因は何でしょうか。 国民のスポーツ離れはしばしば指摘されますが,それは社会生活基本調査の年齢別のデータからわかります。実際,高齢者のスポーツの行動者率はそれほど低下していませんが, 若者,特に10代のスポーツの行動者率は,近年,大きく低下しています。これは,年齢別データあるいは出生年代が同じグループ(コーホートと言います)のデータの時間変化をみれば明らかです。 とはいえ,同じ調査年でみれば,高齢者よりも若者の方がスポーツの行動者率は高いので,全体としてのスポーツの行動者率の低下を防ぐための最も有効な対策の1つは, 若者のスポーツの行動者率の低下を防ぐことであることがわかります。塾やゲームなどの影響による子供のスポーツ離れや, スポーツ系の部活動への参加が少なくなっていることがその原因でしょうから,こうした問題を重点的に改善するような方策を考えれば,長い目で見て広く国民の健康を保つことにつながるでしょう。 35年間にわたって継続してきた社会生活基本調査の結果は,こうした問題に対する基礎データを与えてくれます。 調査結果が明らかにする県民性と地域性また最近は,県民性や地域性が注目され,テレビなどで盛んに取り上げられています。総務省統計局の「家計調査」によって宇都宮市や浜松市のギョーザの消費の多いことが明らかになり, それがまちおこしにつながっていることは有名ですが,社会生活基本調査の都道府県別データも様々な場面で取り上げられるようになりました (都道府県別データが存在するのも,社会生活基本調査が大規模な調査だからです。ちなみに家計調査は,あくまでも県庁所在地や政令指定都市のデータです)。 たとえば,石川県では茶道や華道を習う人が全国一であるとか,鳥取県や滋賀県ではボランティアが盛んであるといった結果です。また, 就寝時刻・起床時刻ともに最も早いのが青森県であるとか,パチンコ発祥の地,愛知県のパチンコの行動者率(男)は最も高いといったデータもあります。 このように都道府県別データを眺めることは興味深く,なぜそのような結果が得られたのかを考えてみることは,とても楽しいものです。統計というと堅苦しく考えられがちですが, そんなことはありません。データを眺めるだけでなく,都道府県別に順位をつけるとか,高い順に並べ替えるなどは,今はパソコンで簡単に自分でできます。 社会生活基本調査の集計結果は総務省統計局のホームページからダウンロードできますから,こうした作業をしてみると,楽しめると思います。 このように社会生活基本調査には,ざっとみただけでも面白いデータがたくさん含まれていますので,私も大学の授業でそのデータを大いに活用させてもらっています。 今回の調査でも,このように楽しめるデータが与えられることを期待しています。 |
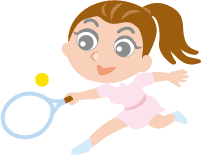 |
