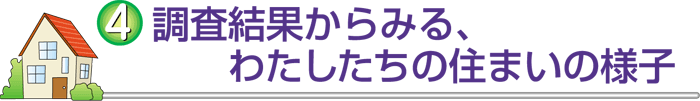
|
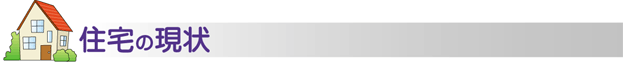
|
<建て方>
|
共同住宅の割合は、引き続き拡大
|
住宅の建て方別割合の推移をみると、一戸建の割合が昭和48年の64.8%から平成10年の57.5%へ縮小し、また、長屋建も昭和48年の12.3%から平成10年の4.2%へと大きく縮小しています。これとは反対に、マンションなどの共同住宅は、昭和48年の22.5%から平成10年には37.8%と大幅に拡大し、住宅の集合化が引き続き進んでいることがわかります。
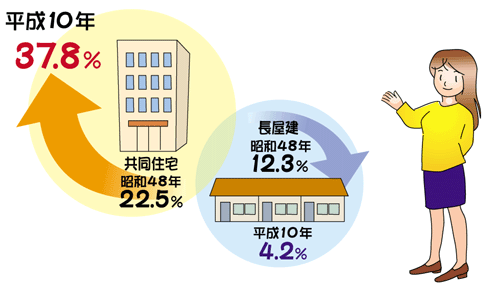
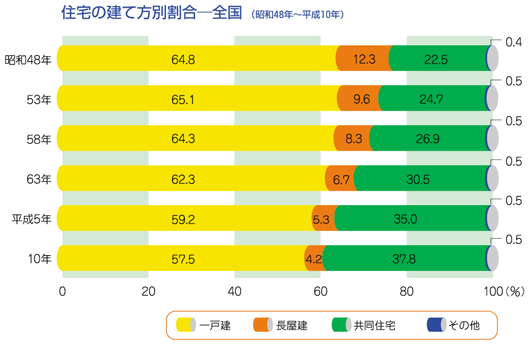
|
一戸建は富山県の 82.4%、
長屋建は大阪府の 10.3%、共同住宅は
東京都の 66.6%がそれぞれ一番 割合が高い
|
住宅の建て方の割合を都道府県別にみてみると、一戸建は富山県が82.4%、長屋建は大阪府が10.3%、共同住宅は東京都が66.6%とそれぞれもっとも高くなっています。
また、一戸建は大都市圏を擁する各県とも全国平均(57.5%)を下回っており、長屋建は西日本の各県で高く、共同住宅は一戸建とは反対に大都市圏を擁する各県で全国平均(37.8%)を上回って高い結果となっています。
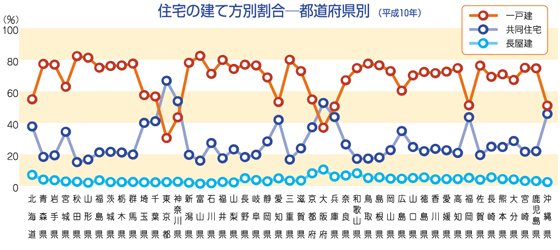
|
<構 造>
|
住宅の約3割は鉄骨・鉄筋コンクリート造
|
住宅を構造別にみると、木造は年々低下し、逆に鉄骨・鉄筋コンクリート造などの非木造は一貫して上昇しています。昭和48年には、木造が住宅全体の約9割を占めていましたが、平成10年には6割台にまで低下し、非木造が約4割を占めるにいたっています。
さらにその内訳をみると、木造のうち防火木造の割合が上昇を続け平成10年には約5割を占め、また、非木造では約9割が鉄骨・鉄筋コンクリート造で、近年におけるマンション建築の著しい増加傾向があらわれています。
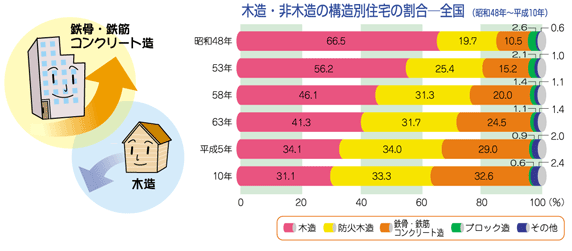
|
マンションなどの共同住宅の高層化が進む
-共同住宅の約7割を占める3階建以上の住宅数-
|
平成10年のマンションなどの共同住宅の内訳をみると、1・2階建の住宅が共同住宅全体の31.8%、3〜5階建の住宅が43.8%、6階建以上の住宅が24.3%と、3階建以上の住宅で約7割を占めています。
これを平成5年から5年間の増加率でみると、1・2階建6.2%増、3〜5階建14.2%増、6階建以上38.3%増と高層になるにつれて増加率も高くなっており、今後もマンションなどの高層化がさらに進行するものと思われます。
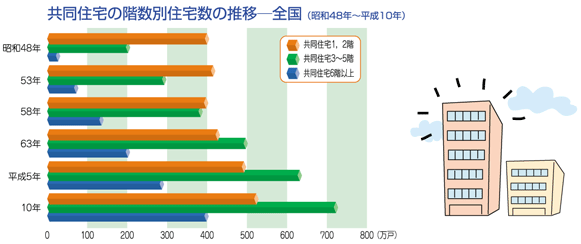
|
<建築時期>
|
日本の住宅の約5割は築18年以内
|
住宅の建築時期をみると、戦後生まれの住宅は4119万戸、住宅全体の約9割を占めています。
その内訳は、終戦時〜35年に建築された住宅が260万戸(5.9%)、36年〜45年が548万戸(12.5%)に対し、46年〜55年が1149万戸(26.2%)と1000万戸を超え、56年〜平成2年が1197万戸(27.3%)となっています。これ以降は平成3年〜7年は631万戸(14.4%)、8年〜10年9月が334万戸(7.6%)となっており、昭和56年以降の18年間に建築された住宅は住宅全体の約5割を占めています。
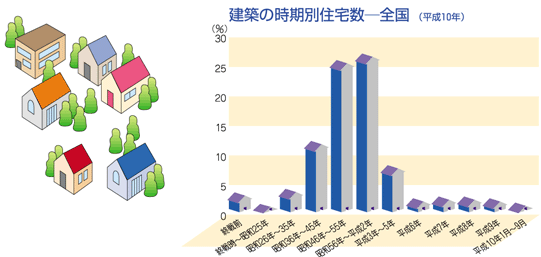
|
<住宅の広さ>
|
住宅規模の大きい日本海側の各県
|
 都道府県別に住宅の広さを1住宅当たりの延べ面積でみると、富山県が151.70平方メートルと最も広くなっています。次いで、福井県137.08平方メートル、秋田県135.27平方メートル、山形県133.59平方メートル、新潟県131.17平方メートルの5県が130平方メートルを超え、全国平均の88平方メートルを大幅に上回っています。また、1住宅当たり平均100平方メートル以上となる県の数は、平成5年では21県でしたが、平成10年には24県となっています。 都道府県別に住宅の広さを1住宅当たりの延べ面積でみると、富山県が151.70平方メートルと最も広くなっています。次いで、福井県137.08平方メートル、秋田県135.27平方メートル、山形県133.59平方メートル、新潟県131.17平方メートルの5県が130平方メートルを超え、全国平均の88平方メートルを大幅に上回っています。また、1住宅当たり平均100平方メートル以上となる県の数は、平成5年では21県でしたが、平成10年には24県となっています。
一方、大都市を含む東京都、大阪府ではそれぞれ59.43平方メートル、68.93平方メートルといずれも全国平均を下回り、住宅規模が大きい日本海側の各県と明らかな対照をみせています。
|
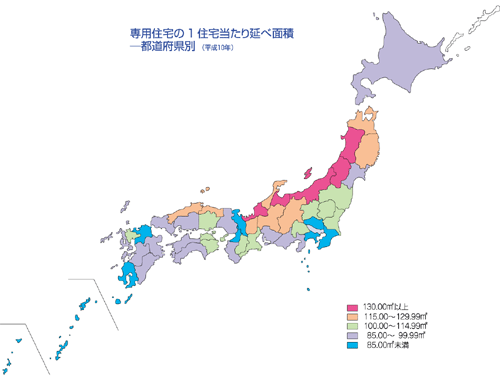
|
住宅の広さは拡大傾向
|
住宅の広さの移り変わりを見てみると、1住宅当たり延べ面積は平成10年まで一貫して拡大していますが、1住宅当たりの室数は昭和63年まで一貫して増加してきたものの、平成5年からは、ほぼ横ばいとなりました。リビングとダイニングやキッチンを広くした間取りの普及などのライフスタイルの多様化などによるものと考えられます。
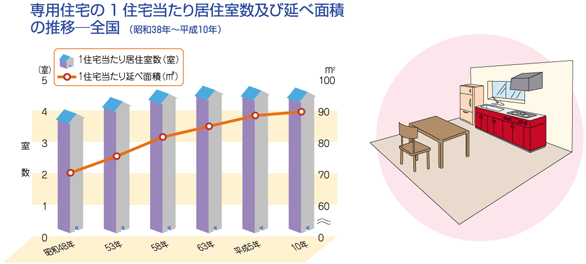
|
建売住宅・分譲マンションの購買は
100平方メートル程度の広さで約5割を占める
|
平成6年以降に建築された建売住宅、分譲マンションの新築購入では3LDKクラスの70〜99平方メートルの広さが約5割と、約半数を占めています。また、「建て替え」では100平方メートル以上で約8割を占めています。
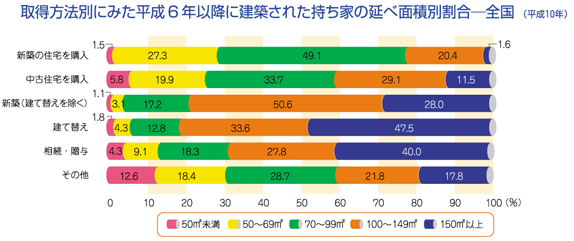
|
<設 備>
|
台所が二つ以上ある住宅は160万戸
|
少子・高齢社会の本格的到来を目前に、二世帯住宅の普及状況を、良質の住宅の実態をみるため、“住宅には台所はいくつあるか”を前回の調査ではじめて調査しました。それによると、台所が2か所以上の住宅は全国で160万戸、住宅総数の3.6%となっています。さらに、どういった住宅に2か所あるのかを広さ別にみると「150−199平方メートル」では11.4%、「200−249平方メートル」では16.5%、「250平方メートル以上」では22.8%と、広い住宅で高い割合となっています。
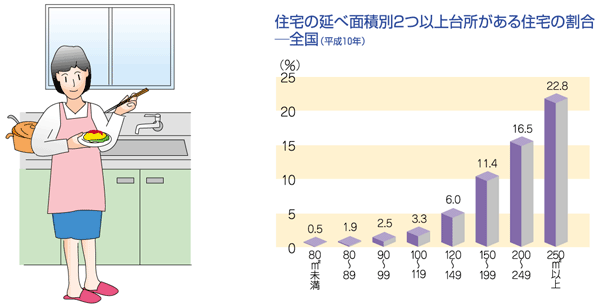
|
5年間で増改築をした持ち家住宅は
約300万戸で、持ち家全体の約1割
|
平成6年以降に増改築した持ち家住宅は、約300万戸で、持ち家全体の約1割を占めています。また、増改築した箇所では、居住室が約6割と最も多くなっています。また、その住宅の築年数は築30年前後の住宅で増改築の割合が高くなっています。
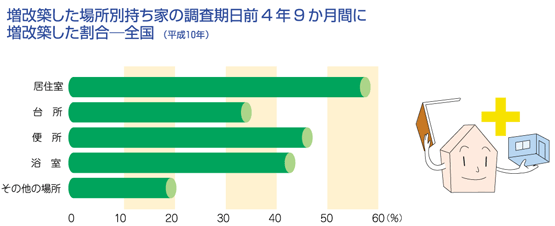
|
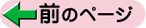 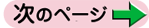
|