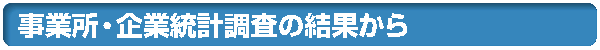
我が国の経済は、戦後の混乱期、復興期を経て、昭和30年代、昭和40年代の高度経済成長期を迎えました。その後、第1次、第2次の石油危機、昭和61年からのバブル景気、その崩壊を経て今日に至っています。その中で事業所数と従業者数の推移をみてみると、事業所数は、時々の経済情勢に左右されながらも増加してきましたが、バブル経済が崩壊した平成3年〜平成8年で初めて減少し、平成8年〜平成13年においても減少となっています。従業者数は、平成8年までは増加してきましたが、平成8年〜平成13年では初めての減少となっています。
| ○事業所数の推移(昭和47年〜平成13年)
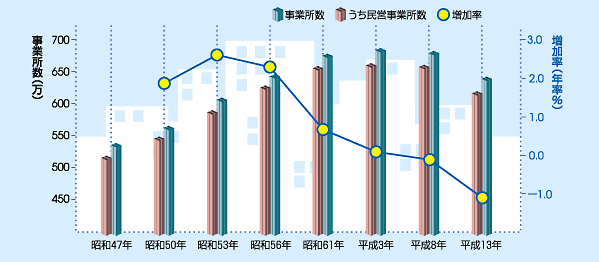
○従業者数の推移(昭和47年〜平成13年)
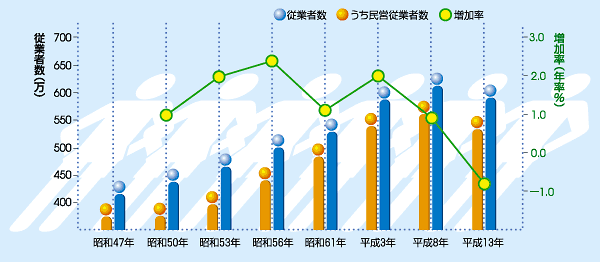
|
近年、詳細な地域別の結果が求められています。都道府県別に事業所数の増加率をみると、平成8年に比べ平成13年には、すべての都道府県で減少しています。また、従業者数については、ほとんどの都道府県が減少しています。
○都道府県別事業所数の増加率〈民営〉(平成8年〜平成13年)
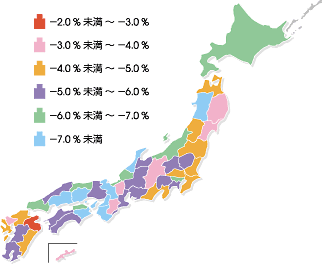
○都道府県別従業者数の増加率〈民営〉(平成8年〜平成13年)
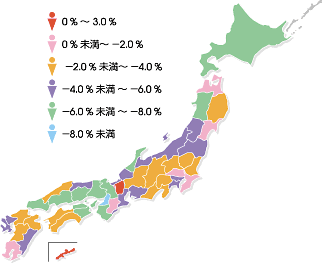
近年、雇用形態の多様化が注目されています。民営事業所について、平成13年の結果から従業上の地位別に従業者数をみると、雇用者は全体の85.1%となっています。平成8年と比べると、常用雇用者のうち、パート・アルバイトなど正社員・正職員以外の従業者が30.1%増と大幅な増加となっています。
○従業上の地位別従業者数の構成比〈民営〉(平成8年〜平成13年)
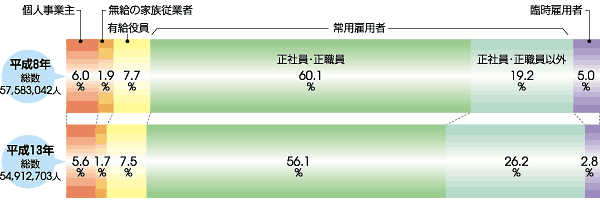
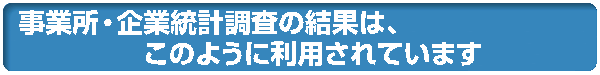
事業所・企業統計調査の結果を通じて、我が国の事業所及び企業の産業、従業者数規模などの基本的構造が全国及び地域別に明らかにされることから、国はもとより都道府県、市区町村におけるさまざまな行政施策の計画立案の際の基礎資料として利用されています。
大都市においては、事業所の過密化や人口のドーナツ化現象などに伴い、住宅、交通、環境の問題や、震災などの災害に対する保安対策、電気・ガス・水道の供給計画、ゴミ処理対策などさまざまな問題が発生しています。
本調査の結果は、これらの対策立案の基礎資料として利用されています。
地方都市においては、(1)企業誘致、地場産業の育成などの産業振興策を通じた雇用機会の拡充、(2)経済のソフト化・サービス化に伴う対事業所サービス産業などの育成、誘致、(3)高齢化、情報化、国際化など、諸計画の基礎資料として利用されています。
現在の経済を反映して若年層の就職難や中高年のリストラが顕著になり、労働者の需要と供給を的確に結び付けることが重要な課題となっています。また、パート・アルバイトなどの短時間労働者の増加や人材派遣業の進展などにより、さまざまな雇用問題も生じてきています。本調査の結果は、これらの基礎資料として利用されています。
本調査は、全数調査であるため、市区町村などの地域単位の集計が可能です。このため、地域におけるきめ細かな統計資料として利用されます。
また、毎月勤労統計調査、雇用動向調査、賃金構造基本調査、民間非営利団体実態調査、企業活動基本調査、通信利用動向調査、特定サービス産業実態調査、全国企業短期観測調査など事業所や企業を対象とする各種統計調査の母集団情報として利用されています。
|