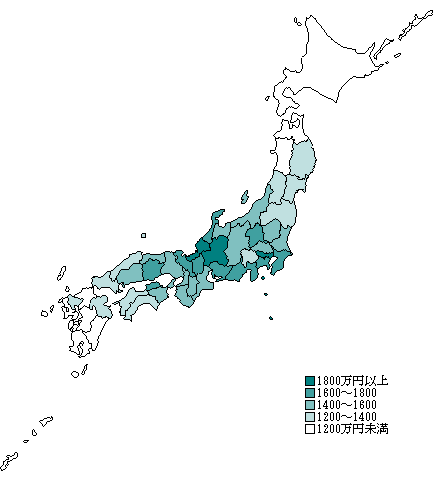ここから本文です。
平成11年全国消費実態調査 二人以上の一般世帯の家計収支 及び貯蓄・負債に関する結果(要約)
平成12年12月26日速報公表
1.1世帯当たり消費支出は1か月平均335,114円で,調査開始以来初の減少
- 全世帯の平成11年9月〜11月の1か月平均消費支出は1世帯当たり335,114円。
- 前回調査(平成6年)と比較すると名目で(-)2.6%減,消費者物価の上昇分を除いた実質で(-)4.1%減となり,調査開始以来初めての減少となった。
- 1世帯当たり世帯人員は,平成6年の3.59人から11年は3.40人に減少。1人当たりの消費支出に換算すると,実質で(+)1.2%の増加。
図1 1か月平均消費支出の対前回増加率の推移(全世帯)
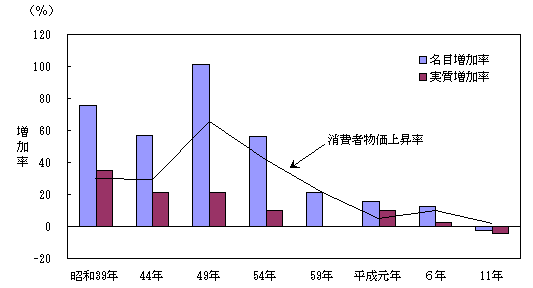
表1 1か月平均消費支出の推移(全世帯)
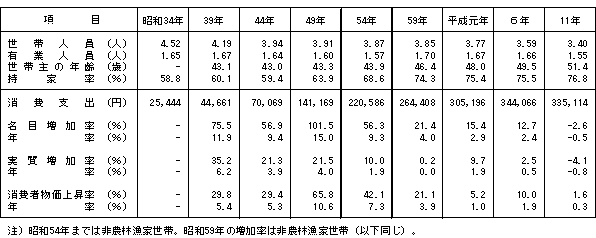
2.高齢化の進行に伴い所得格差はやや拡大
- 年間収入の世帯間格差をジニ係数でみると平成11年はやや上昇して0.301。
- 消費支出の所得階級間格差を擬ジニ係数でみると,平成元年(0.166)まで上昇し,6年(0.164)は低下したが,11年(0.166)は再び上昇し,平成元年と同水準。
- 世帯主の年齢階級別に平成6年と比較すると,年間収入のジニ係数及び消費支出の擬ジニ係数は,30歳未満の若年層でやや上昇。60歳代及び70歳以上の高年齢層では低下。
- 高齢化による世帯主の年齢構成の変化の影響を除くと,年間収入のジニ係数,消費支出の擬ジニ係数はいずれも平成6年をやや下回る。
注)ジニ係数とは分布の集中度あるいは不平等度を表す係数で,0に近づくほど平等,1に近づくほど不平等となる。擬ジニ係数とは所得の順位に並べてジニ係数と同じ計算方法を適用し,所得階級間格差を測る係数である。
表2 年間収入及び消費支出の(擬)ジニ係数の推移(全世帯)
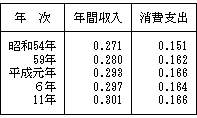
表3 世帯主の年齢階級別年間収入及び消費支出の(擬)ジニ係数(全世帯)
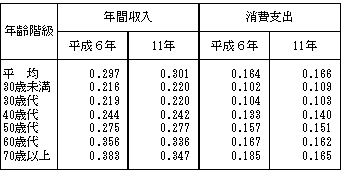
表4 世帯主の年齢分布を調整した場合の年間収入及び消費支出の(擬)ジニ係数(全世帯)
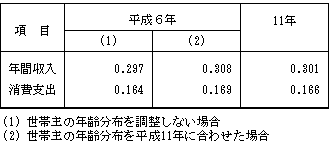
3.情報通信関連支出は大幅な増加。パソコン・ワープロの購入費の格差は縮小,電話通信料及び放送受信料は拡大
- パソコン・ワープロの支出金額は平成6年と比較すると(+)161.3%増,電話通信料は(+)53.4%増,放送受信料は(+)26.2%増と大幅増加。
- 年間収入五分位階級別にパソコン・ワープロの購入費をみると,第I階級と第V階級の格差(第V階級/第I階級)は4.76倍。平成6年(6.11倍)と比較すると格差は縮小。
- 電話通信料の支出金額をみると,第I階級と第V階級の格差は1.75倍。平成6年(1.57倍)と比較すると格差は拡大。
- 電話通信料を固定電話通信料と移動電話通信料に分けると,第I階級と第V階級の格差はそれぞれ1.69倍,1.97倍。
- 放送受信料の支出金額をみると,第I階級と第V階級の格差は1.56倍。格差は平成元年以降拡大。
- 放送受信料の内訳をみると,NHK放送受信料の第I階級と第V階級の格差は1.22倍と小さいのに対し,CATV受信料は3.23倍,他の受信料は3.75倍と大きい。
表5 年間収入五分位階級別パソコン・ワープロの購入費の推移(全世帯)
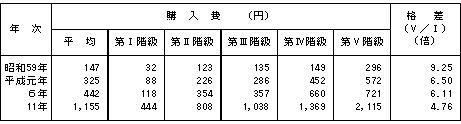
表6 年間収入五分位階級別電話通信料の推移(全世帯)
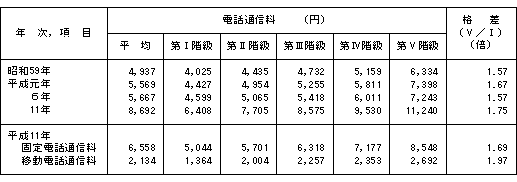
表7 年間収入五分位階級別放送受信料の推移(全世帯)
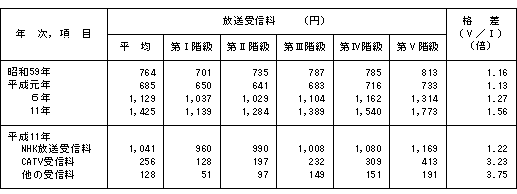
4.夫婦共働き世帯の実収入は実質(+)2.0%の増加。世帯主だけが働いている世帯では実質(-)0.7%の減少
- 夫婦共働き世帯の1か月平均実収入は620,567円で,平成6年と比較すると実質(+)2.0%の増加。
- 実収入の内訳は,世帯主の勤め先収入が409,788円(実収入に占める割合66.0%),世帯主の配偶者の勤め先収入が140,252円(同22.6%)など。
- 世帯主だけが働いている世帯の実収入は,平成6年と比較すると実質(-)0.7%の減少。夫婦共働き世帯との差が拡大。
- 1か月平均消費支出は383,775円で,平成6年と比較すると実質(-)1.2%減少。世帯主だけが働いている世帯の消費支出を100とすると121.4となり,その差は平成6年(118.7)と比較すると拡大。
- 消費支出に占める費目別割合をみると,夫婦共働き世帯は,世帯主だけが働いている世帯と比較すると,交際費などの「その他の消費支出」,交通・通信,教育の支出割合が高く,住居,食料,教養娯楽などが低い。
表8 夫婦共働き世帯と世帯主だけが働いている世帯の1か月平均実収入及び消費支出の推移(勤労者世帯)
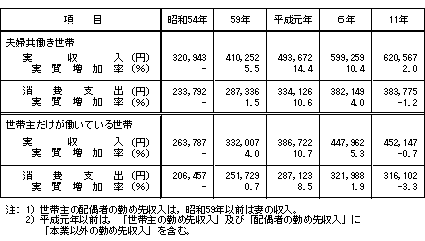
図2 夫婦共働き世帯と世帯主だけが働いている世帯の1か月平均消費支出の費目構成(勤労者世帯)
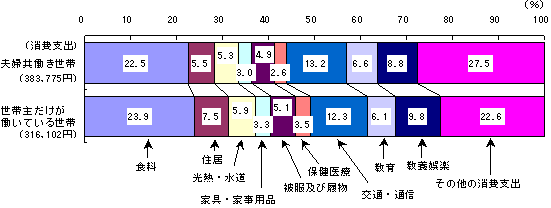
5.40歳代以下の各年齢階級で負債現在高が大幅増加,30歳代では負債が貯蓄を上回る
- 1世帯当たりの貯蓄現在高は1485万円で,平成6年と比較すると(+)8.9%増,負債現在高は567万円で,(+)16.6%増。
- 世帯主の年齢階級別貯蓄現在高は,年齢階級が高くなるほど多く,30歳未満で373万円,70歳以上で2268万円。負債現在高は,40歳代が845万円と最も多い。
- 平成6年と比較すると,貯蓄現在高は40歳代以下の各年齢階級で減少。負債現在高は70歳以上を除く各年齢階級で増加。特に30歳未満,30歳代及び40歳代では(+)30%以上の増加。
- 30歳代では,調査開始以来初めて負債現在高が貯蓄現在高を上回る。
- 年間収入五分位階級別に負債現在高をみると,第I階級が145万円,第V階級が989万円で,第I階級と第V階級の格差は6.80倍。
- 負債現在高の推移をみると,平成元年に第V階級で大幅に増加したが,その後は,第II〜IV階級の増加率が第V階級を上回っており,平成11年は第II〜第IV階級で(+)20%を上回る増加。第I階級は(+)3.2%,第V階級は(+)4.2%と増加率が小さい。
図3 世帯主の年齢階級別貯蓄・負債現在高(全世帯)
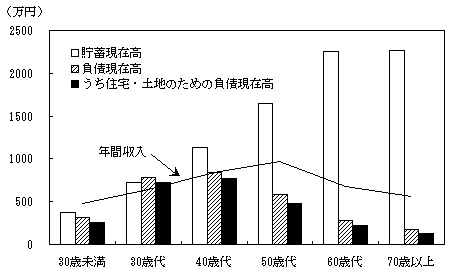
図4 年間収入五分位階級別負債現在高の推移(全世帯)
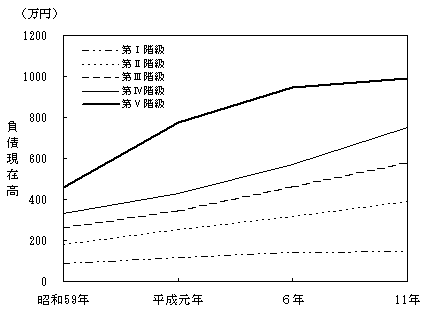
6.住宅ローンのある世帯の平均消費性向は,住宅ローンのない世帯と比較すると低下幅が大きい
- 住宅ローンのある世帯の可処分所得及び消費支出は,平成6年と比較すると,それぞれ実質(+)0.4%増加,(-)5.0%減少。住宅ローンのない世帯((+)0.9%,(-)1.2%)の実質増加率を下回っている。
- 平均消費性向は,住宅ローンのある世帯が73.4%,住宅ローンのない世帯が80.7%。平成6年と比較すると,それぞれ(-)4.2ポイント,(-)1.7ポイントの低下と,住宅ローンのある世帯の低下幅が大きい。
- 住宅ローンのある世帯の住宅ローン返済額は64,646円で,住宅ローン返済割合(可処分所得に占める住宅ローン返済額の割合)は12.9%。平成6年と比較すると,住宅ローン返済額は(+)18.0%増加,住宅ローン返済割合は(+)1.7ポイント上昇。
- 住宅ローンのある世帯の金融資産純増率(可処分所得に占める金融資産純増額の割合)は9.5%。平成6年と比較すると(+)1.3ポイント上昇。一方,住宅ローンのない世帯の金融資産純増率は14.4%,(-)0.1ポイントの低下。
表9 住宅ローンの有無別1か月平均実収入及び消費支出(勤労者世帯)
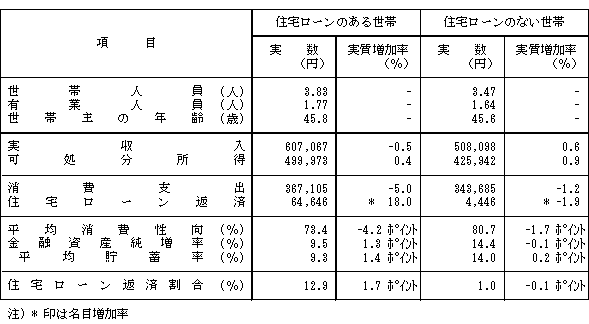
住宅ローンのある世帯とは,平成11年11月末日現在で1万円以上の住宅・土地のための借入金残高のある世帯とし,それ以外を住宅ローンのない世帯とする(以下同じ)。
7.若年層では住宅ローン返済割合の上昇幅が大きい
- 世帯主の年齢階級別に住宅ローンのある世帯の割合をみると,40歳代までは持家率との相関がみられ,いずれも年齢階級が高くなるほど上昇。50歳以上では,持家率は85%前後で概ね一定しているが,住宅ローンのある世帯の割合は年齢階級が高くなるほど低下。
- 住宅ローンのある世帯の住宅ローン返済額は各年齢階級とも6〜7万円程度で年齢による差は比較的小さい。
- 住宅ローン返済割合は,可処分所得の水準の違いも影響するため,年齢による違いが大きく,若年層は17%前後と高い。
- 住宅ローン返済割合を平成6年と比較すると,すべての年齢階級で上昇しており,70歳以上及び若年層で住宅ローン返済割合の上昇幅が大きい。
図5 世帯主の年齢階級別持家率及び住宅ローンのある世帯の割合(勤労者世帯)
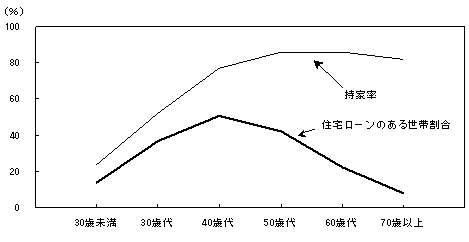
図6 世帯主の年齢階級別住宅ローンのある世帯の住宅ローン返済割合(勤労者世帯)
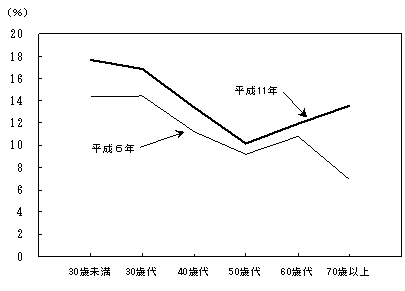
8.一般小売店,百貨店での購入割合が低下,スーパー,コンビニエンスストア,ディスカウントストアなどでの購入割合が上昇
- サービス料金などを除く消費支出について,購入先別の支出割合をみると,一般小売店が34.8%と最も高く,以下,スーパー34.6%,百貨店9.4%,生協・購買5.5%,ディスカウントストア4.9%,通信販売1.7%,コンビニエンスストア1.6%となっている。
- 購入先別の支出割合の推移をみると,一般小売店での購入は一貫して低下,逆にスーパーでの購入は一貫して上昇しており,一般小売店とスーパーの割合はほぼ同じとなった。百貨店は,昭和54年に10%を超えた後,低下が続いている。生協・購買は昭和44年から平成6年まで上昇が続いていたが,11年はわずかに低下。コンビニエンスストア,ディスカウントストア及び通信販売は平成6年と比較すると上昇。
表10 消費支出に占める購入先別支出の推移(全世帯)
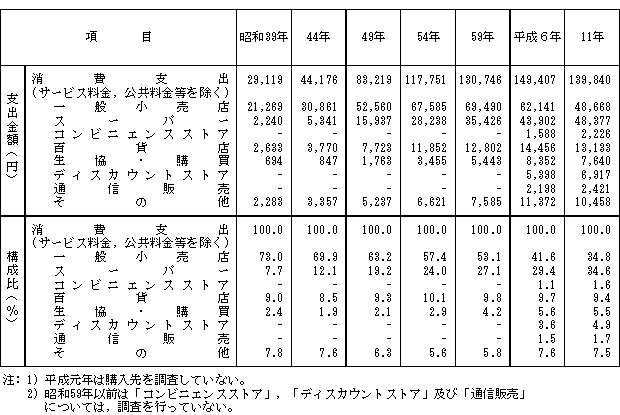
9.食料,被服及び履物では百貨店での購入割合が上昇
- サービス料金などを除く消費支出のうち,食料は,一般小売店での購入が一貫して低下。逆に,スーパーでの購入は一貫して上昇。百貨店での購入も上昇傾向。生協・購買での購入は平成6年まで一貫して上昇していたが11年は低下。コンビニエンスストアでの購入は上昇。
- 家具・家事用品は,一般小売店での購入は一貫して低下。百貨店での購入も低下傾向。一方,スーパーでの購入は,平成6年にわずかに低下したのを除くと上昇傾向。ディスカウントストアでの購入も上昇しており,他の費目と比較すると,ディスカウントストアでの購入割合が高い。
- 被服及び履物は,一般小売店での購入の低下が続いている。百貨店での購入は,平成6年に低下したが,11年は再び上昇。スーパーでの購入は,昭和54年まで上昇傾向で推移し,その後低下が続いたものの,11年は再び上昇。ディスカウントストアは上昇。通信販売は低下。他の費目と比較すると百貨店での購入割合が高い。
表11 費目,購入先別割合(全世帯)
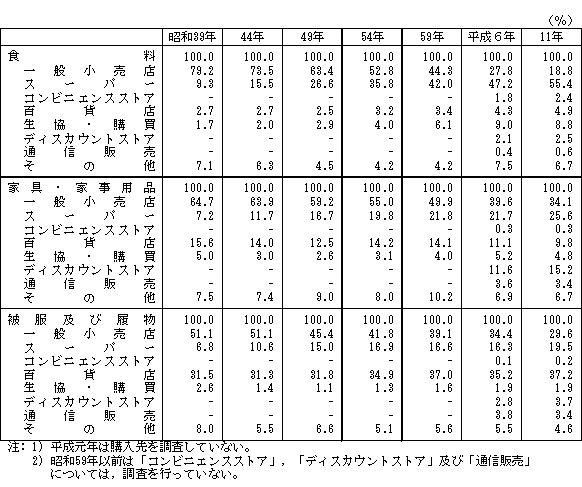
10.大都市,中都市,京浜葉大都市圏,京阪神大都市圏などでスーパーが一般小売店を上回る
- サービス料金などを除く消費支出について,都市階級別に購入先別割合をみると,一般小売店は,人口規模が大きな都市階級になるほど低くなる傾向がある。逆に百貨店は,人口規模が大きな都市階級になるほど高くなる。生協・購買,通信販売も人口規模が小さい都市階級でやや低い。コンビニエンスストアは,大都市でやや高く,他の都市階級ではほぼ同じ割合。スーパー及びディスカウントストアは,中都市と小都市Aが大都市を上回っている。
- 京浜葉大都市圏では,百貨店,ディスカウントストア,コンビニエンスストア,通信販売での購入割合が高い。中京大都市圏では一般小売店,京阪神大都市圏ではスーパー,生協・購買が高い。
- 平成6年と比較すると,一般小売店は,全ての都市階級・大都市圏で4〜9ポイントの低下,スーパーは,全ての都市階級・大都市圏で4〜8ポイントの上昇となり大都市,中都市,小都市A,京浜葉大都市圏,京阪神大都市圏でスーパーが一般小売店を上回った。百貨店は,小都市B,京阪神大都市圏で若干上昇している一方で,京浜葉大都市圏,中京大都市圏で0.5ポイントを超える低下。
表12 都市階級,大都市圏別消費支出の購入先別割合(全世帯)
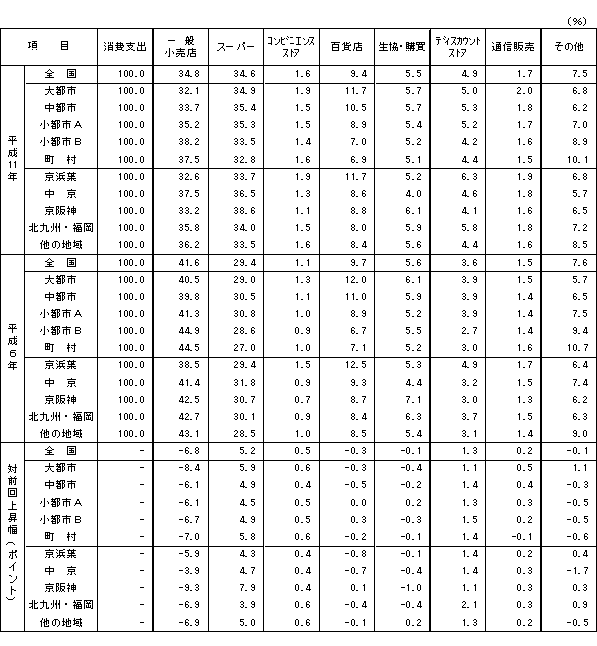
11.日曜日の支出割合が上昇,土曜日,平日の支出割合が低下。食料,家具・家事用品などは日曜日の支出が土曜日を上回る
- 曜日別消費支出について,曜日全体の平均(祝日を除く)を100とした支出金額指数でみると,土曜日が114.7で最も高く,日曜日が112.8,平日の平均が94.5。
- 平日に支出している割合は,月曜日から金曜日まで合計すると67.5%と,約2月3日を占める。
- 曜日別支出金額指数の推移をみると,平成元年から6年にかけて,土曜日の支出金額指数が高まる傾向がみられたが,11年は日曜日の支出金額指数が高まる傾向がみられる。平日の支出金額指数は低下が続いているが,低下のテンポは鈍化。
- 費目別にみると,食料,家具・家事用品は,平成6年では土曜日の支出が日曜日よりも多かったが,11年では土曜日よりも日曜日の支出が多くなっている。
図7 消費支出の曜日別支出金額指数(全世帯) 曜日全体の平均(祝日を除く)=100
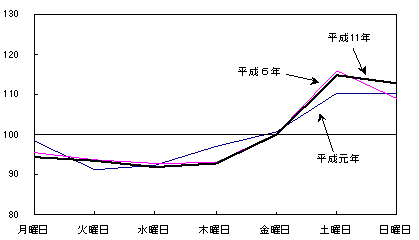
図8 食料の曜日別支出金額指数(全世帯) 曜日全体の平均(祝日を除く)=100
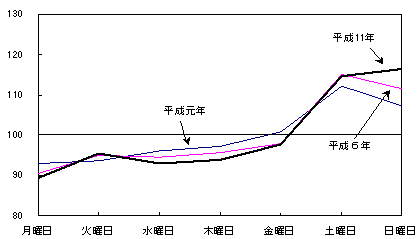
12.土日の支出割合が上昇した夫婦共働き世帯,土日の支出割合が低下した勤労者以外の世帯
- 夫婦共働き世帯,その他の勤労者世帯及び勤労者以外の世帯別に曜日別支出金額指数をみると,夫婦共働き世帯は土曜日,日曜日と平日の差が大きく,勤労者以外の世帯では差が小さい。
- 平成6年と比較すると,夫婦共働き世帯では,平日が低下,土曜日,日曜日が上昇。その他の勤労者世帯では,平日,土曜日が低下,日曜日が上昇。勤労者以外の世帯では,平日が上昇,土曜日,日曜日が低下。
図9 世帯主の職業・世帯主の配偶者の就業状態別消費支出の曜日別支出金額指数 曜日全体の平均(祝日を除く)=100
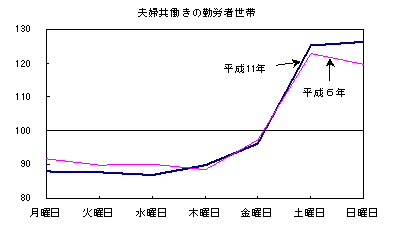
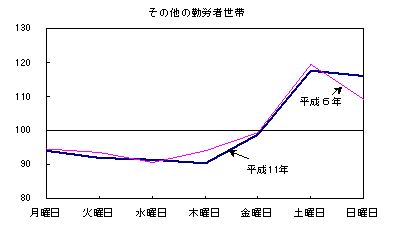
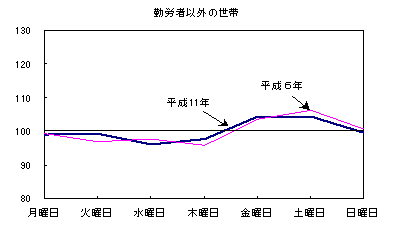
13.消費支出の都道府県間格差は縮小傾向。北海道,東北,四国地方で名目増加,関東,近畿地方は水準の低下が続く。
- 全世帯の1世帯当たり消費支出を都道府県別にみると,全国平均を100とした場合,富山県が119.3で最も高く,以下,茨城県,石川県,神奈川県,岐阜県,福井県と続いている。一方,最も低いのは沖縄県の75.4で,以下,宮崎県,鹿児島県,熊本県,青森県,高知県と続いている。
- 1世帯当たり消費支出の都道府県間格差を,全国平均を100とした指数の標準偏差(ばらつき)でみると平成6年の9.8から11年は8.9と格差は縮小した。
- 1世帯当たり消費支出を地方別にみると,全国平均を100とした場合,北陸地方が108.2で最も高く,以下,関東,東海,近畿地方と続いている。一方,最も低いのは沖縄地方の75.4で,以下,九州,北海道,四国地方と続いている。
- 平成6年と比較すると,北海道,東北,四国地方で,それぞれ,(+)1.1%,(+)1.3%,(+)1.2%の増加(名目)。一方,他の地方は減少(名目)となっており,特に近畿地方は(-)5.2%と最も減少率が大きい。
- 全国平均を100とした各地方の消費支出の水準について,平成元年以降の推移をみると,平成元年から6年にかけて,関東,東海,近畿及び四国地方で低下となっていたが,11年は,関東及び近畿地方のみ低下。
表13 1か月平均消費支出の標準偏差の推移(全世帯)
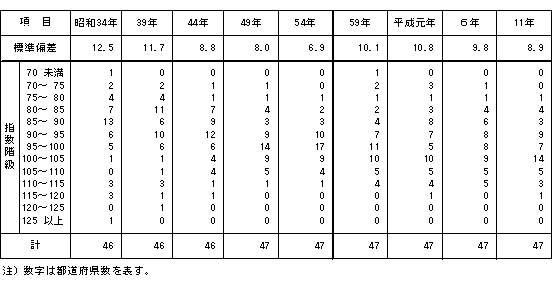
図10 地方別消費支出の水準の推移(全世帯) 全国平均=100
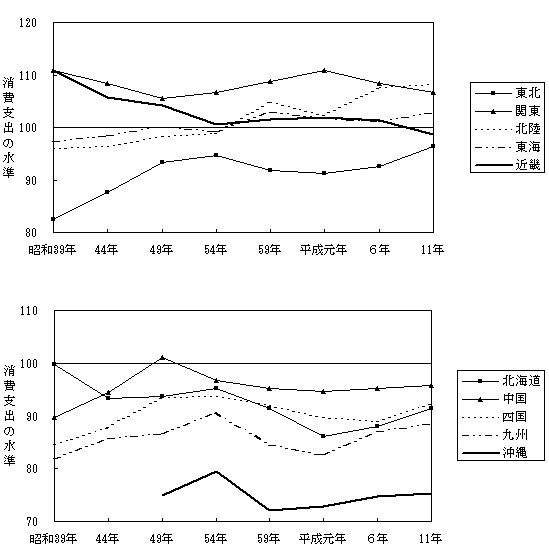
14.大都市圏で多くなったパソコン・ワープロの購入費。大都市圏以外の地域で多くなった外国パック旅行費
- 地方別にパソコン・ワープロの購入費をみると,近畿地方,中国地方,関東地方,東海地方で全国平均を上回っている。一方,東北地方,沖縄地方,九州地方,四国地方,北海道地方,北陸地方は全国平均を下回っている。
- 平成6年は,地方別のパソコン・ワープロ購入費の差は小さかったが,平成11年では,京浜葉(関東地方),中京(東海地方)及び京阪神(近畿地方)の3大都市圏を含む地方などでパソコン・ワープロの購入費が多い傾向がみられる。
- 地方別に外国パック旅行費をみると,関東地方が最も多く,以下,東海地方,近畿地方などとなっており,3大都市圏を含む地方で多くなっている。一方,最も少ないのは九州地方で,以下,沖縄地方,東北地方,北海道地方などとなっている。
- 外国パック旅行費は,平成元年から6年にかけて,3大都市圏を含む関東,東海,近畿地方で大幅に増加したが,6年から11年は,これらの地方の伸びが小さくなったのに対し,北海道,東北,中国,四国,沖縄地方で大幅に増加している。
図11 地方別パソコン・ワープロの購入費(全世帯)
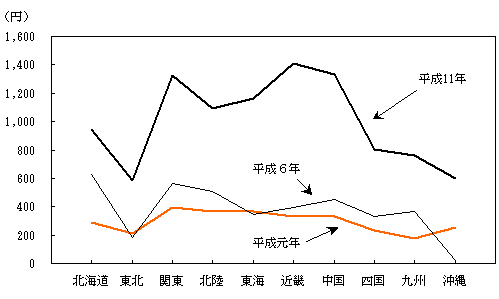
図12 地方別外国パック旅行費(全世帯)
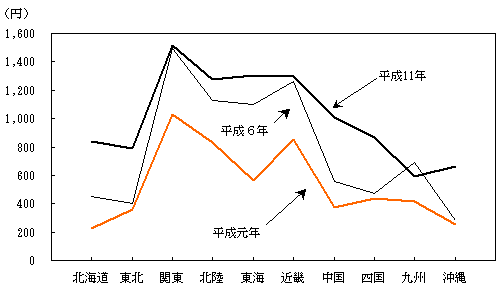
15.貯蓄現在高は福井県が1945万円で最も多い
- 都道府県別に1世帯当たり貯蓄現在高をみると,福井県が1945万円で最も多く,以下,東京都,岐阜県,石川県,神奈川県,香川県と続いている。一方,最も少ないのは沖縄県の579万円で,以下,青森県,秋田県,宮崎県,鹿児島県,熊本県と続いている。
図13 都道府県別貯蓄現在高(全世帯)