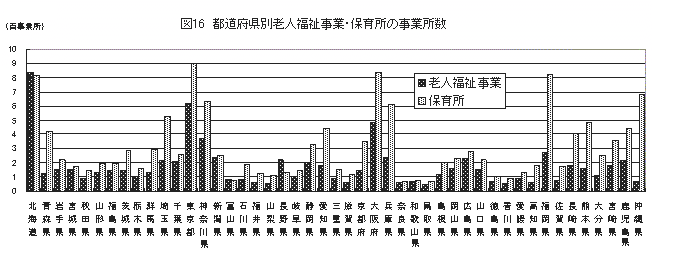ここから本文です。
平成12年11月15日
総務庁統計局
平成11年サービス業基本調査 結果の概要(要約)
I 全国の結果
1 サービス業全体の事業所数及び従業者数
事業所数は10年間で12.2%の増加だが、最近5年間は増加が鈍る
平成11年7月1日現在の民営サービス業の事業所数は149万9千事業所(家事サービス業、病院及び学校の一部を除く。「調査の概要」参照。以下同じ。)で、第1回調査の平成元年と比較すると12.2%の増加となっている。これを平成6年と比較可能な営利的業種でみると、10年間の増加率は11.5%となるが、元年から6年にかけての増加率が9.3%であったのに対し、6年から11年にかけての増加率は2.1%と低くなっている。
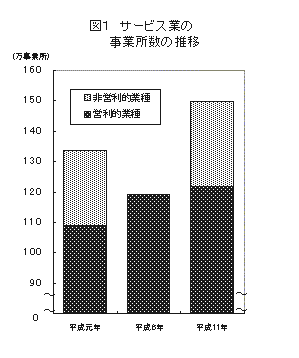
従業者数は10年間で37.9%の増加
平成11年7月1日現在の従業者数は1171万7千人で、元年と比較すると37.9%の増加となっている。平成11年の従業者数を従業上の地位別にみると、「個人業主・無給家族従業者」が91万6千人(全従業者数の7.8%)、「有給役員」が86万6千人(同7.4%)、「常用雇用者」が944万9千人(同80.6%)、「臨時雇用者」が48万6千人(同4.1%)となっている。
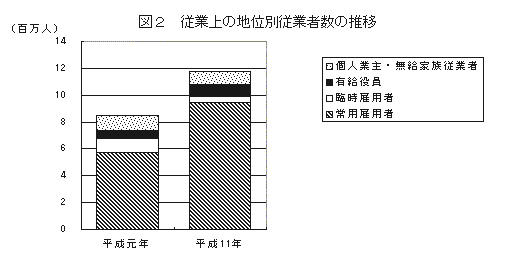
2 産業分類別事業所数
事業所数の27.2%を占める「洗濯・理容・浴場業」
産業中分類別の事業所数をみると、「洗濯・理容・浴場業」が40万8千事業所(全事業所数の27.2%)と最も多く、次いで、土木建築サービス業や個人教授所などの「専門サービス業」が31万5千事業所(同21.0%)、「宗教」が9万5千事業所(同6.3%)となっている。
産業小分類別の事業所数をみると、「美容業」が17万3千事業所と最も多く、次いで「個人教授所」が13万9千事業所、「理容業」が12万5千事業所となっている。
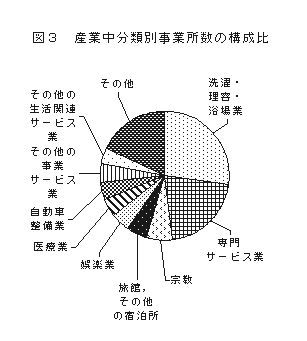
習い事は、種類が変わりつつも盛ん
10年間の増加事業所数が最も多い「専門サービス業」(6万1千事業所増)のうち「個人教授所」についてみると、平成元年から6年にかけて大きく増加した「学習塾」は6年から11年には減少に転じ、代わって増加数が拡大したのは「音楽個人教授所」及び英会話教室などの「その他の個人教授所」である。一方、「生花・茶道個人教授所」及び「そろばん個人教授所」は平成6年から11年には減少しており、習い事の種類は変わりつつあることがわかる。
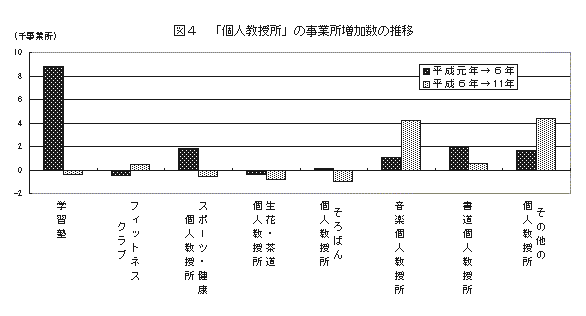
企業はアウトソーシングへ
10年間の増加事業所数が2番目に多い「その他の事業サービス業」(2万事業所増)についてみると、平成元年から6年にかけての増加は6千事業所であったが、6年から11年にかけては、人材派遣業などの「他に分類されない事業サービス業」の急増及び「建物サービス業」,「民営職業紹介業」や「警備業」の増加により1万4千事業所と大きな増加となっており、企業におけるアウトソーシング化の実態を表している。
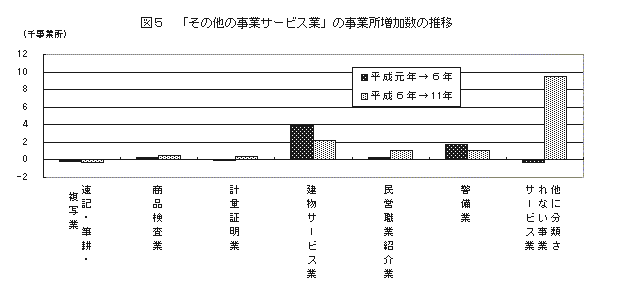
人口高齢化とともに増加した「療術業」と「老人福祉事業」
10年間の増加事業所数が次いで多い「医療業」及び「社会保険、社会福祉」の内訳を産業小分類でみると、「医療業」の増加事業所数1万5千の71.0%を「療術業」が、「社会保険、社会福祉」の増加事業所数1万2千の43.4%を「老人福祉事業」が占めており、人口高齢化に対応したサービス産業の増加がうかがえる。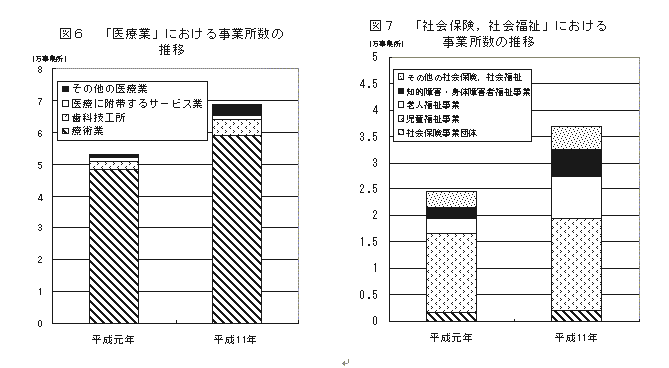
3 収入金額
サービス業の収入金額は201兆7152億円、「娯楽業」の割合は19.1%
サービス業全体の収入金額は201兆7152億円で、その内訳を産業中分類別にみると、「娯楽業」が38兆4807億円(サービス業全体の19.1%)、「社会保険、社会福祉」が21兆3597億円(同10.6%)、「専門サービス業」が19兆4407億円(同9.6%)となっている。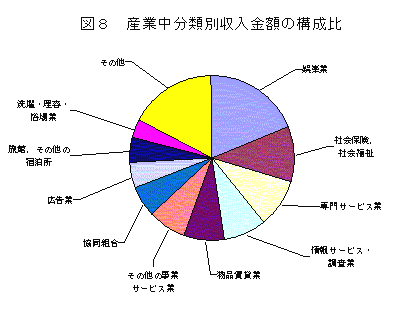
1従業者当たりの収入金額が最も高いのは「広告業」
サービス業の1従業者当たりの収入金額は、1722万円となっている。これを産業中分類別にみると、1従業者当たりの収入金額が最も高いのは「広告業」で6639万円、次いで「物品賃貸業」が5165万円、「放送業」が4798万円となっている。一方、1従業者当たりの収入金額が低いのは「洗濯・理容・浴場業」(560万円)、「駐車場業」(591万円)、「医療業」(674万円)などとなっている。
1従業者当たりの収入金額を平成元年と比べると、「学術研究機関」及び「協同組合」がそれぞれ29.2%及び27.3%の減少となっており、この2産業を除く22産業すべてが増加となっている。
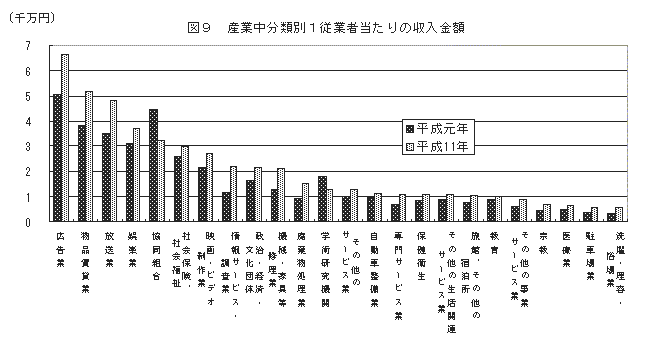
従産業からの収入割合は1割弱
サービス業全体について、従産業(産業小分類ベース)の収入金額割合は9.9%となっているが、そのうち、「卸売・小売業、飲食店」及び「サービス業」に属する部分が大部分を占めている。
「旅館、その他の宿泊所」は従産業の73.5%が「卸売・小売業、飲食店」、「物品賃貸業」は31.8%が「卸売・小売業、飲食店」、「情報サービス・調査業」は75.4%が「サービス業」となっている。
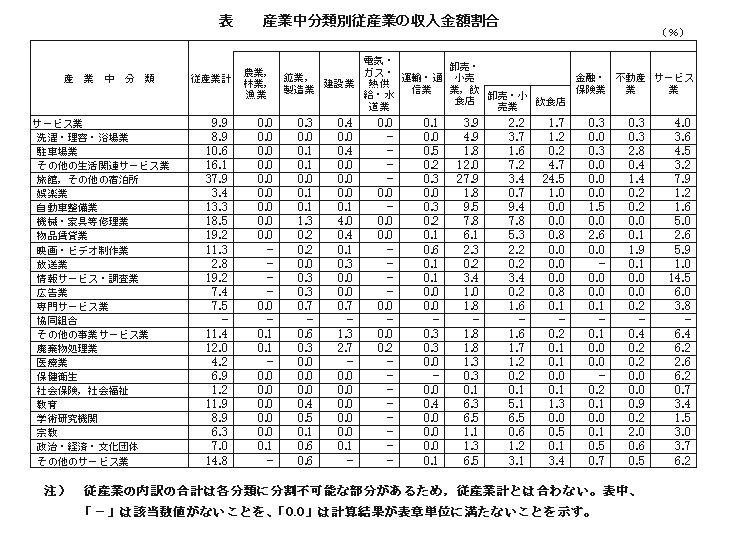
官公庁からの収入割合が高い営利的業種は「廃棄物処理業」と「専門サービス業」
サービス業の主産業の収入金額について、収入を得た相手先をみると、個人(一般消費者)からの収入が41.5%、企業・団体からの収入が46.6%、官公庁からの収入が11.9%となっている。
官公庁からの収入金額割合が最も高い産業は「その他のサービス業」で50.8%となっており、次いで「社会保険、社会福祉」が44.4%、「保健衛生」が31.9%と、非営利的業種が官公庁からの収入割合が高い。営利的業種で官公庁からの収入割合が高い業種は、「廃棄物処理業」(24.0%)、「専門サービス業」(22.9%)などとなっている。
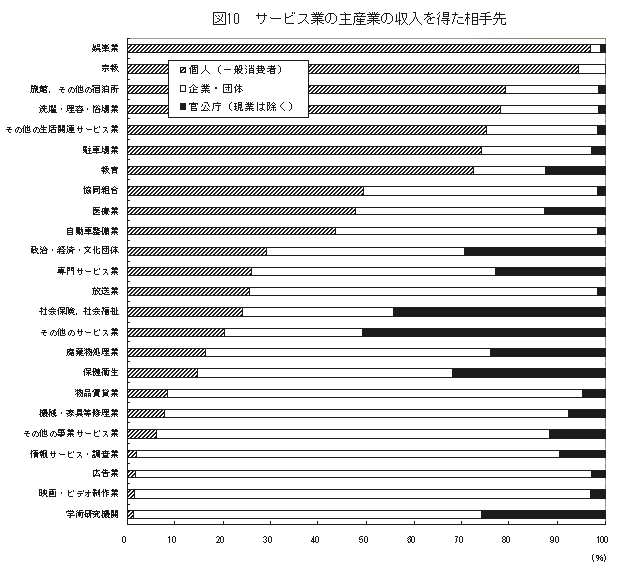
4 1雇用者当たりの給与支給総額
給与水準が高い情報関連産業
1雇用者当たりの給与支給総額を産業中分類別にみると、「放送業」が844万円と最も高く、次いで「学術研究機関」が684万円、「広告業」が628万円、「情報サービス・調査業」が616万円、「機械・家具等修理業」が579万円となっており,情報関連産業で給与水準が高くなっている。一方、1雇用者当たりの給与支給総額が最も低い産業は「宗教」で221万円となっており、次いで「駐車場業」で254万円、「洗濯・理容・浴場業」が271万円、「娯楽業」が310万円となっている。
元年から11年にかけて1雇用者当たりの給与支給総額の増加率が最も高い産業は91.2%増加した「その他のサービス業」、次いで「情報サービス・調査業」(75.3%)、「宗教」(66.3%)となっている。
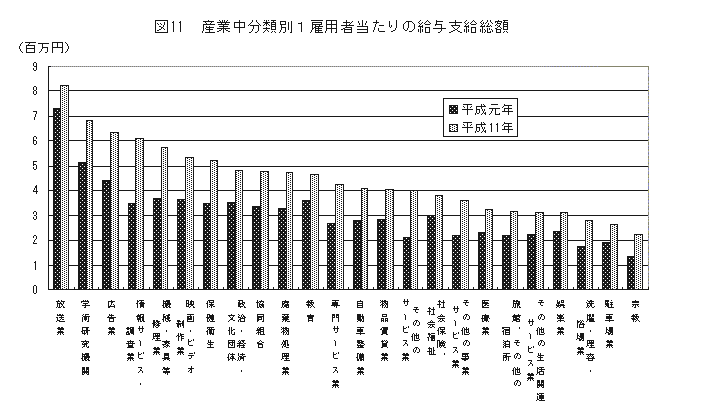
II 都道府県別の結果
サービス業事業所の1割強が東京
サービス業の事業所数を都道府県別にみると、東京都が17万事業所と全国の11.3%を占めており、次いで大阪府が10万7千事業所、愛知県が7万9千事業所となっている。これを産業中分類別にみると、24中分類中19中分類は東京都が最も多く、東京都以外の道府県で事業所数が最も多い産業は「駐車場業」「宗教」(ともに大阪府)、「旅館、その他の宿泊所」(長野県)、「協同組合」(北海道)、「廃棄物処理業」(埼玉県)となっている。
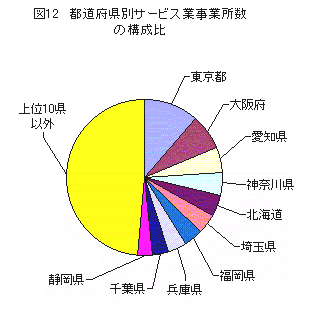
理美容業の分布
事業所数は東京都や大阪府などの都市部において多いが、人口千人当たりの事業所数では秋田県、山形県など東北地方の各県で多くなっている。
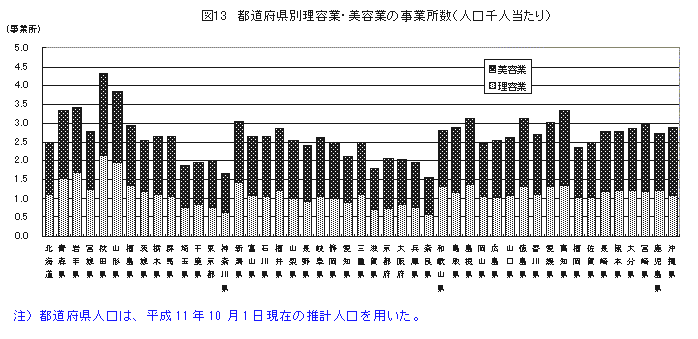
旅館の分布
観光地を有する長野県や静岡県の事業所数が多いが、ビジネス向けホテルの多さで東京都が第5位となっている。
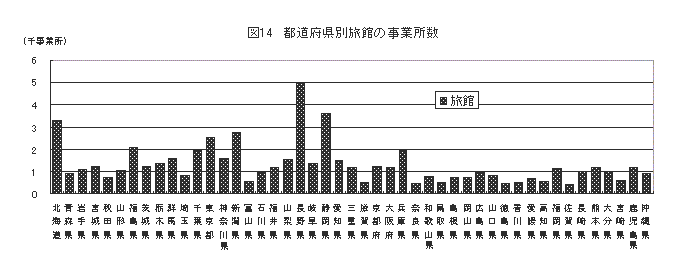
廃棄物処理業の分布
廃棄物処理業の事業所は、大都市が所在する都道府県に多く分布しているが、首都圏の場合は東京都より埼玉県及び神奈川県の方が多くなっている。
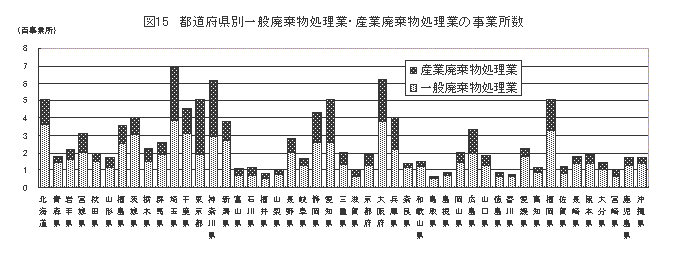
保育所及び老人福祉事業の分布
北海道は「老人福祉事業」「保育所」ともに多い。また、大都市が所在する都道府県及び九州の各県は「保育所」の数が多い。