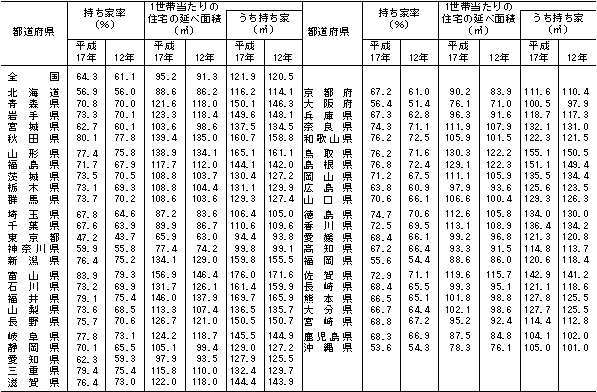ここから本文です。
IV 変化する世帯の姿


1一般世帯の1世帯当たりの人員は2.60人とさらに減少
平成17年における一般世帯(注)数は4822万世帯,世帯人員は1億2524万人で,1世帯当たり人員は2.60人となっている。このうち,「単独世帯」(一人暮らし世帯)は1333万世帯で,一般世帯全体の約3割(27.6%)を占めている。
一般世帯数の推移を昭和60年以降についてみると,一貫して増加が続いているが,平成12年以降は増加率が低下している。また,一般世帯の1世帯当たり人員の推移をみると,一貫して減少を続けており,平成12年の2.67人から2.60人と更に減少している。(表4-1,4-2,図4-1)
(注) 一般世帯とは,「施設等の世帯」以外の世帯をいう。「施設等の世帯」とは,学校の寮・寄宿舎の学生・生徒,病院・療養所などの入院者,社会施設の入所者,自衛隊の営舎内・艦船内の居住者,矯正施設の入所者などから成る世帯をいう。
表4-1 一般世帯数,一般世帯人員及び施設等の世帯人員の推移
- 全国(昭和60年~平成17年)
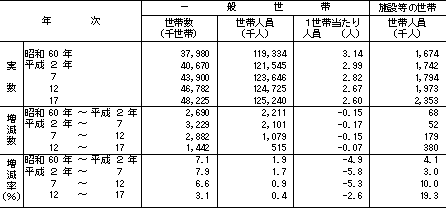
図4-1 一般世帯数,一人暮らし世帯数及び1世帯当たり人員の推移
- 全国(昭和60年~平成17年)
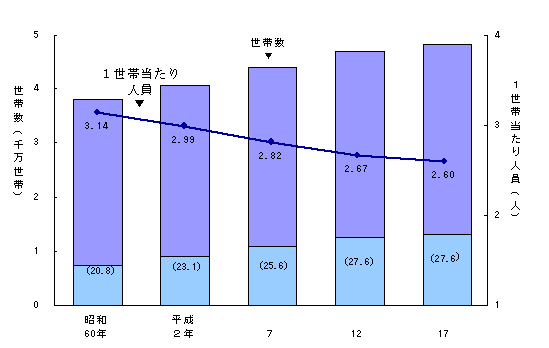
(注) ( )内の数値は,一般世帯全体に占める一人暮らし世帯の割合(%)。
表4-2 世帯人員別一般世帯数の推移 - 全国(昭和60年~平成17年)
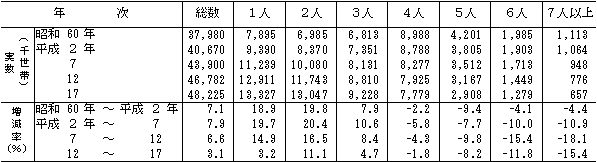
一般世帯数を都道府県別にみると,東京都が569万世帯と最も多く,次いで大阪府が352万世帯,神奈川県が348万世帯などとなっており,鳥取県が20万世帯と最も少なくなっている。平成12年と比べると,沖縄県が7.9%増と最も増加率が大きく,次いで東京都が6.0%増,滋賀県が5.7%増などとなっており,これらを含む12都道県で全国平均(3.1%増)を上回っている。
1世帯当たり人員を都道府県別にみると,福井県が3.13人と最も多く,次いで山形県が3.09人,佐賀県が3.02人などとなっており,これらを含む34県で全国平均(2.60人)を上回っている。一方,最も少ないのは東京都で2.17人,次いで鹿児島県が2.31人,北海道が2.33人などとなっている。平成12年と比べると,すべての都道府県で1世帯当たり人員は減少している。(表4-3,図4-2)
図4-2 都道府県別1世帯当たり人員 (平成17年)
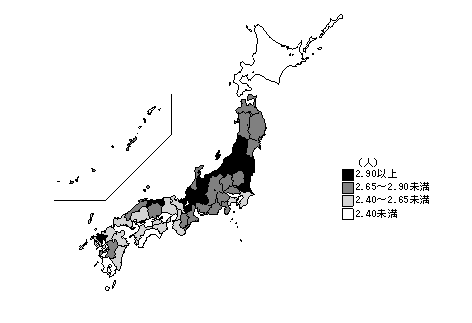
表4-3 一般世帯数及び1世帯当たり人員 - 都道府県(平成12年,17年)
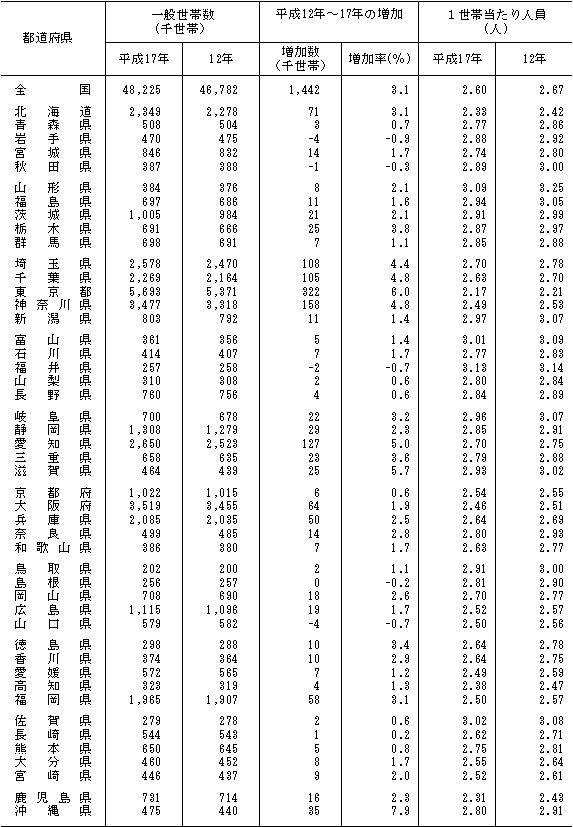
2「夫婦と子供から成る世帯」は減少,「夫婦のみの世帯」は増加
一般世帯数を家族類型別にみると,「夫婦のみの世帯」は966万世帯(一般世帯数の20.0%),「夫婦と子供から成る世帯」は1464万世帯(同30.4%),「ひとり親と子供から成る世帯」は410万世帯(同8.5%),「その他の世帯」は650万世帯(同13.5%),「単独世帯」(一人暮らし世帯)は1333万世帯(同27.6%)となっている。
これらの推移をみると,「夫婦のみの世帯」と「ひとり親と子供から成る世帯」は高い増加率が続いており,平成12年~17年は「夫婦のみの世帯」が9.3%の増加となり,「ひとり親と子供から成る世帯」が14.7%と大幅な増加となった。一方,「夫婦と子供から成る世帯」は平成2年~7年には0.9%,7年~12年には0.8%の減少となっており,12年~17年は1.9%と更に減少している。また,一人暮らし世帯は,平成2年~7年には19.7%と高い増加率となっていたが,7年~12年は14.9%増,12年~17年は3.2%増と,増加率は低下している。(表4-4,4-5,図4-3)
表4-4 世帯の家族類型別一般世帯数の推移 - 全国(平成2年~17年)
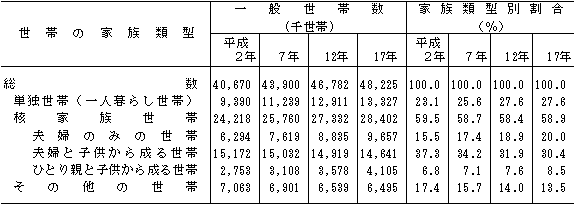
表4-5 世帯の家族類型別一般世帯数の増減数及び増減率の推移 - 全国(平成2年~17年)
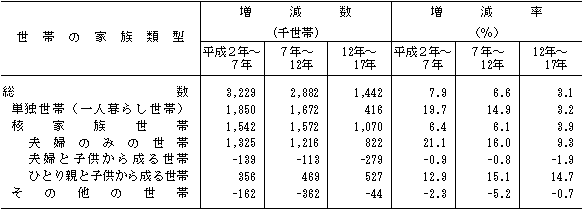
図4-3 一般世帯の家族類型別割合の推移 - 全国(平成2年~17年)
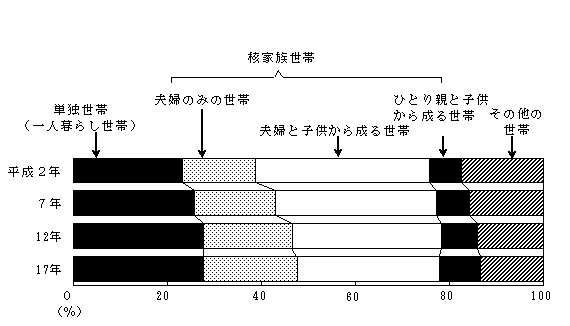
一般世帯数のうち6歳未満親族のいる世帯は504万世帯(一般世帯数の10.4%)となっている。6歳未満親族のいる世帯の一般世帯数に占める割合の推移をみると,平成2年以降減少が続いており,少子化の進行が反映している。(表4-6)
表4-6 6歳未満親族のいる一般世帯数の推移 - 全国(平成2年~17年)
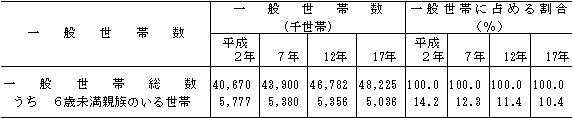
3「一人暮らし高齢者」は100万人以上増加し,400万人を超える ~高齢男性の10人に1人,高齢女性の5人に1人が一人暮らし~
(注) 「一人暮らし高齢者」とは,65歳以上の一人暮らしをいう。
65歳以上親族のいる一般世帯数は1798万世帯で,平成12年と比べると,294万世帯(19.5%)増となっている。一般世帯に占める割合は,平成7年の29.1%から12年には32.2%,17年には37.3%となっており,高齢化の進行を反映している。
65歳以上の親族のいる一般世帯数を家族類型別にみると,「核家族世帯」が875万世帯と最も多く,次いで65歳以上の者が子供夫婦や孫などと同居しているなどの「その他の世帯」が519万世帯となっており,「一人暮らし高齢者」は405万人となっている。
65歳以上親族のいる一般世帯の家族類型別割合の推移をみると,「核家族世帯」と「一人暮らし高齢者」の割合が急速に増加している。(表4-7,図4-4)
表4-7 世帯の家族類型別65歳以上親族のいる一般世帯数の推移 - 全国(平成7年~17年)
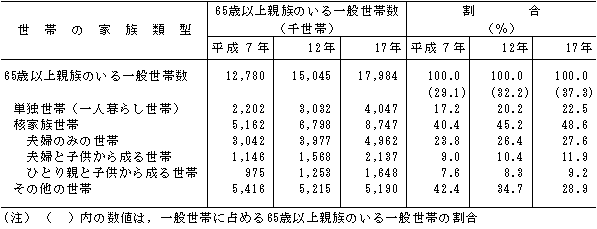
図4-4 65歳以上親族のいる一般世帯の家族類型別割合の推移 -全国(平成7年~17年)
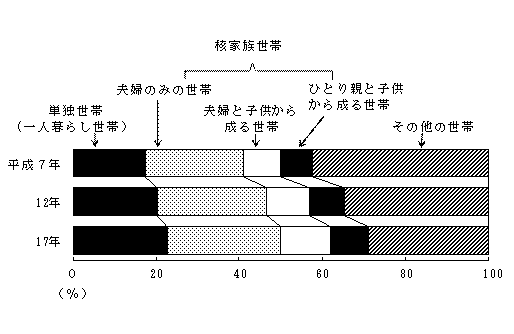
「一人暮らし高齢者」(405万人)は,平成12年と比べると,102万人(33.5%)増となっており,また,65歳以上人口に占める割合も15.1%と,12年(13.8%)と比べると1.3ポイント上昇している。
これを男女別にみると,男性が113万人,女性が292万人で,女性が男性の2.6倍になっている。また,「一人暮らし高齢者」の65歳以上人口に占める割合は,男性が9.9%,女性が18.9%となっており,高齢男性の10人に1人,高齢女性の5人に1人が一人暮らしとなっている。(表4-8)
表4-8 男女別「一人暮らし高齢者」数の推移 - 全国(平成7年~17年)
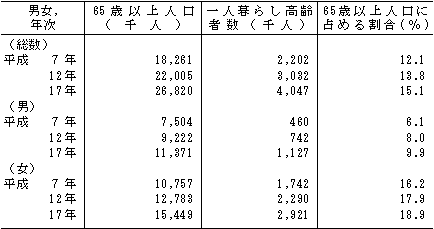
4持ち家率は64.3%に上昇し,1世帯当たりの住宅の延べ面積は95.2㎡に拡大 ~持ち家率,1世帯当たりの住宅の延べ面積共に富山県が最大~
住宅の所有の関係別に一般世帯数(注)(4743万世帯)をみると,「持ち家」が3048万世帯(住宅に住む一般世帯数の64.3%)と最も多く,次いで「民営の借家」が1212万世帯(同25.5%),都道府県営住宅や市町村営住宅の「公営の借家」が206万世帯(同4.3%),社宅や公務員宿舎などの「給与住宅」が138万世帯(同2.9%),「都市再生機構・公社の借家」が95万世帯(同2.0%)などとなっている。
一般世帯数に占める持ち家の割合(持ち家率)を平成12年と比べると,3.2ポイント上昇している。(表4-9)
(注)住宅の所有の関係別の一般世帯数は,住居以外(寄宿舎・寮や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所など)に居住している世帯を除く。
表4-9 住宅の所有の関係別一般世帯数の推移 - 全国(昭和60年~平成17年)
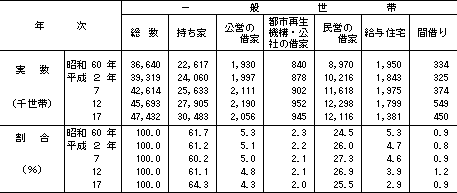
1世帯当たりの住宅の延べ面積は95.2m2となっており,平成12年の91.3m2を3.9m2上回っている。これを住宅の所有の関係別にみると,「持ち家」が121.9m2と最も広く,次いで「給与住宅」が60.6m2,「公営の借家」が52.5m2,「都市再生機構・公社の借家」が50.2m2,「民営の借家」が44.4m2などとなっており,持ち家と持ち家以外との間には約2~3倍の開きがある。(表4-10)
表4-10 一般世帯の住宅の所有の関係別1世帯当たりの住宅の延べ面積
- 全国(平成7年~17年)
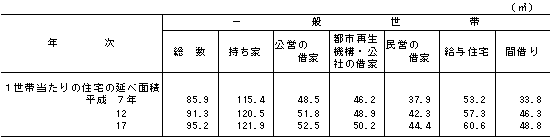
持ち家率を都道府県別にみると,富山県が83.9%と最も高く,次いで秋田県が80.1%,三重県が79.4%などとなっている。一方,最も低いのは東京都で47.2%,次いで沖縄県が53.6%,福岡県が55.6%などとなっている。平成12年と比べると,沖縄県を除く都道府県で持ち家率は上昇している。(表4-11)
1世帯当たりの住宅の延べ面積を都道府県別にみると,富山県が156.9m2と最も広く,次いで福井県が146.0m2,秋田県が139.4m2などとなっている。一方,最も狭いのは東京都で65.9m2,次いで大阪府が76.1m2,神奈川県が77.4m2などとなっており,最も広い富山県と最も狭い東京都との間には2.4倍の開きがある。平成12年と比べると,すべての都道府県で1世帯当たりの住宅の延べ面積は拡大している。(表4-11,図4-5)
図4-5 都道府県別一般世帯の1世帯当たりの住宅の延べ面積(平成17年)
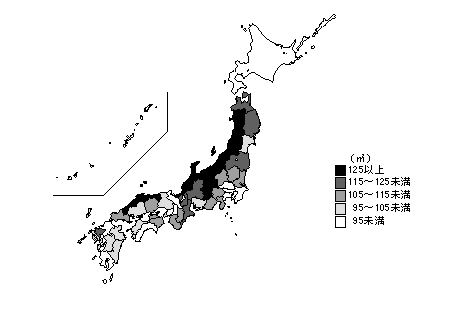
表4-11 一般世帯の持ち家率及び1世帯当たりの住宅の延べ面積
- 都道府県(平成12年,17年)