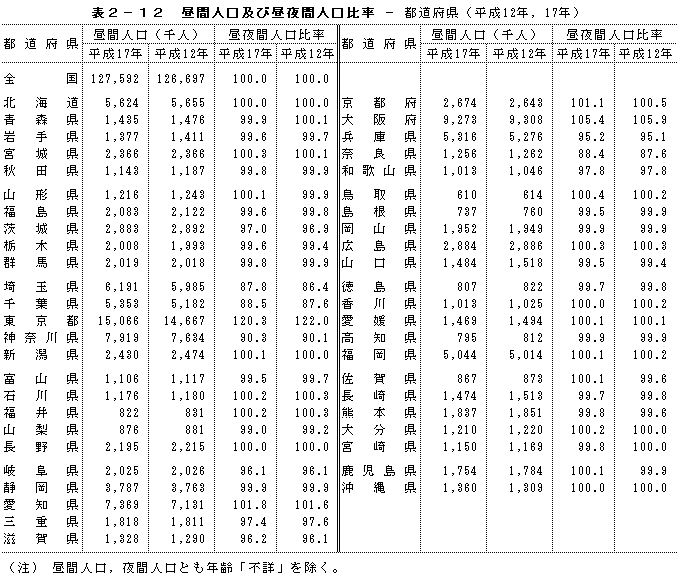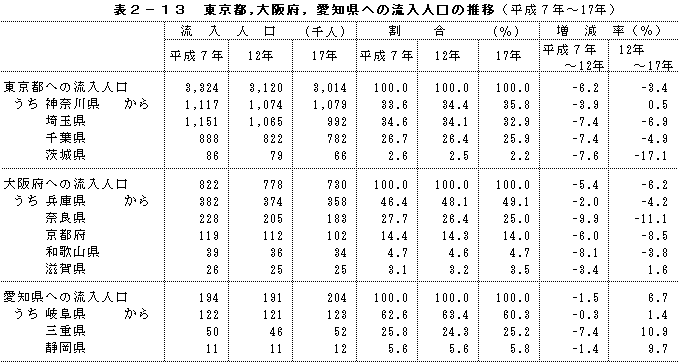ここから本文です。
II 就業面から見た人口の変化


1 労働力人口は引き続き男性で減少,女性で増加
〜女性の労働力率は30〜34歳で大きく上昇〜
15歳以上人口(1億1019万人)の労働力状態をみると,労働力人口(就業者及び完全失業者)は6546万人で,平成12年と比べると,64万人(1.0%)減となっている。一方,非労働力人口(家事従事者,通学者,高齢者など)は4132万人で,平成12年と比べると,93万人(2.3%)増となっている。
労働力人口を男女別にみると,男性は3833万人,女性は2713万人で,平成12年と比べると,男性が92万人(2.3%)減,女性が28万人(1.1%)増となっている。
男女別労働力人口の推移をみると,男性は平成7年をピークに引き続き減少,女性は引き続き増加している。
労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は59.4%で,平成12年と比べると,1.7ポイントの低下になっている。これを男女別にみると,男性が72.2%,女性が47.5%で,平成12年と比べると,男性が2.6ポイント,女性が0.7ポイント低下している。(表2-1)
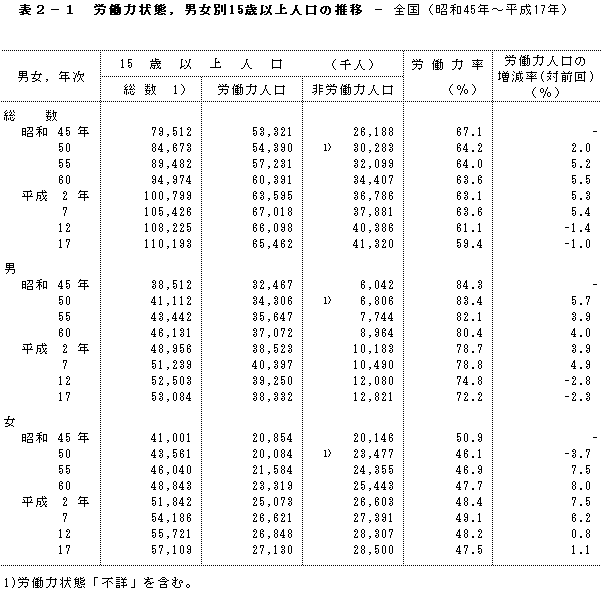
男女別労働力率を年齢階級別にみると,男性は30〜59歳の各年齢階級で90%以上と高くなっている。また,女性は25〜29歳と45〜49歳を頂点とし,30〜34歳を谷とするM字カーブになっている。
女性の年齢階級別労働力率の推移をみると,20〜24歳は平成7年以降低下しているのに対し,25〜59歳の各年齢階級は平成2年以降上昇となっている。M字カーブの谷となっている30〜34歳は,平成17年は4.9ポイント上昇と,他の年齢階級よりも大きく上昇し,M字カーブの緩和が進行している。(表2-2,図2-1)
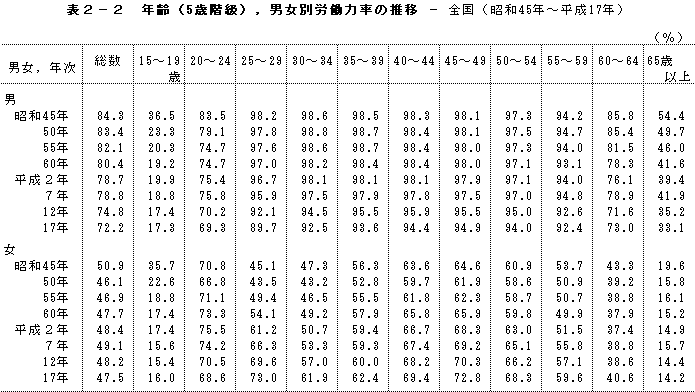
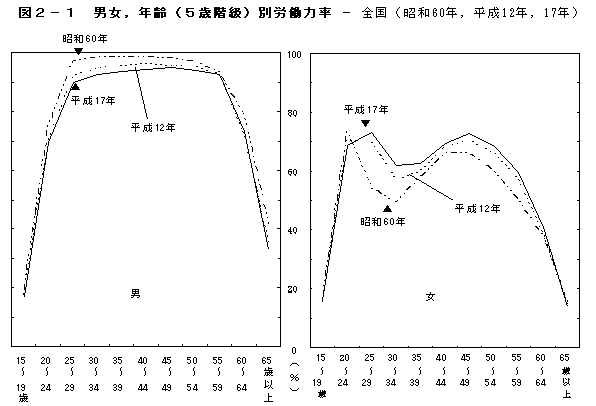
主要先進国の男女別年齢階級別労働力率をみると,我が国のように女性がM字カーブを示す国はみられない。(図2-2)
図2-2 主要先進国の年齢(5歳階級),男女別労働力率
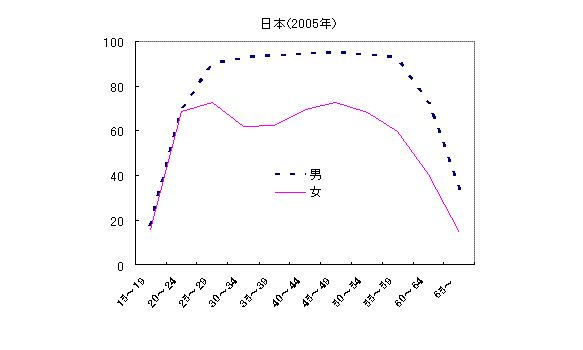
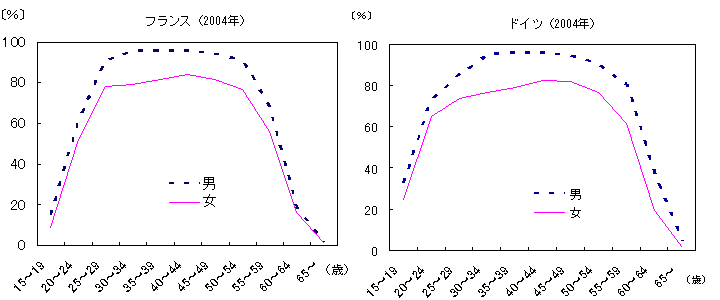
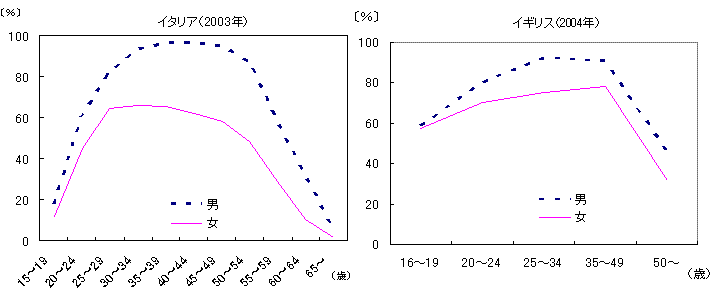
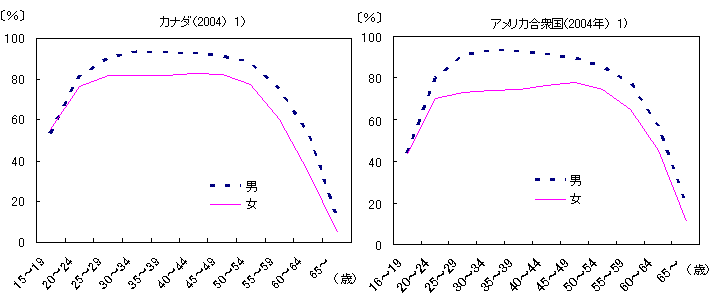
資料:ILO,Yearbook of labour Statistics2003年版,2004年版による。ただし,日本は国勢調査の結果による。
1) 軍人を除く
2 65歳以上の雇用者数が増加
〜我が国の65歳以上の男性の労働力率は主要先進国と比べ高い〜
15歳以上就業者数(6151万人)を従業上の地位別にみると,雇用者(役員を含む。)が5146万人(15歳以上就業者数の83.7%),自営業主(家庭内職者を含む。)が691万人(同11.2%),家族従業者が313万人(同5.1%)で,平成12年と比べると,雇用者,自営業主,家族従業者はそれぞれ1.6%,3.8%,10.7%の減少となっている。
従業上の地位別15歳以上就業者数の推移をみると,雇用者は平成17年に調査開始以来初の減少となっている。自営業主は昭和60年以降減少が続いている。(表2-3)
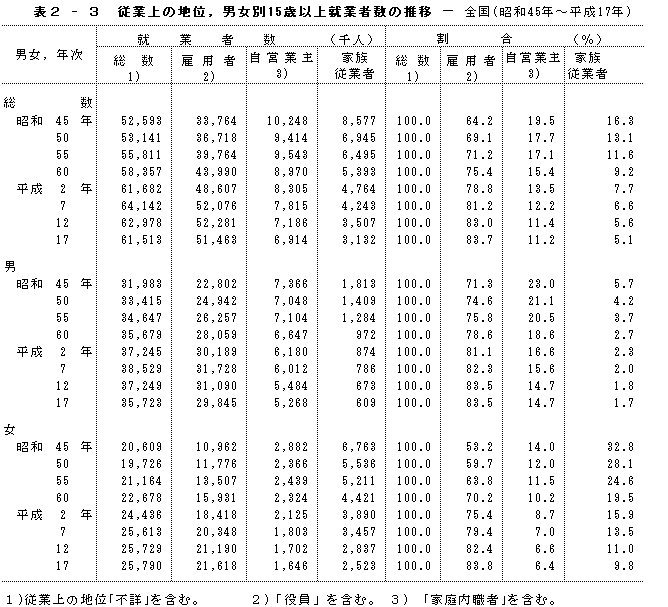
従業上の地位別15歳以上就業者を年齢階級別にみると,65歳以上の雇用者数は252万人で,平成12年と比べると,44万人(20.9%)増となっている。
65歳以上の雇用者を男女別でみると,男性は166万人,女性は86万人となっており,平成12年と比べると,男性は24万人(16.6%)増,女性は20万人(30.1%)増となっている。
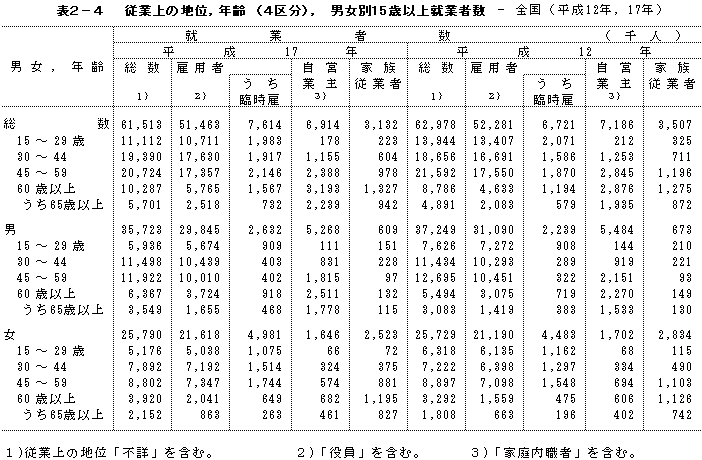
65歳以上の雇用者を前期高齢者(65〜74歳)と後期高齢者(75歳以上)に分けてみると,前期高齢者は214万人と,平成12年と比べ33万人(18.2%)増となっており,後期高齢者は38万人と,12年と比べ11万人(39.1%)増となっている。
65歳以上の雇用者は,前期高齢者,後期高齢者共に男性が女性の約2倍となっている。(表2-5)
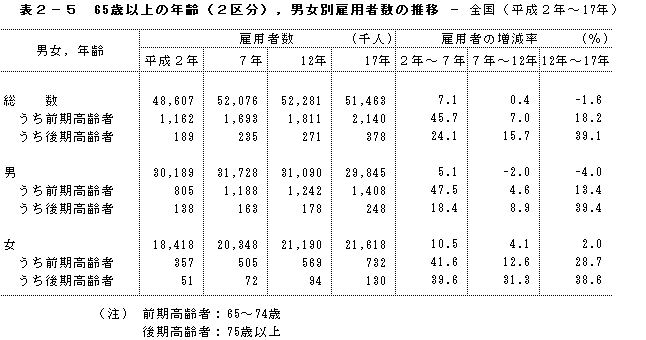
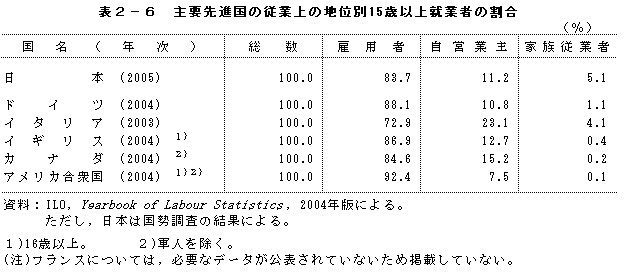
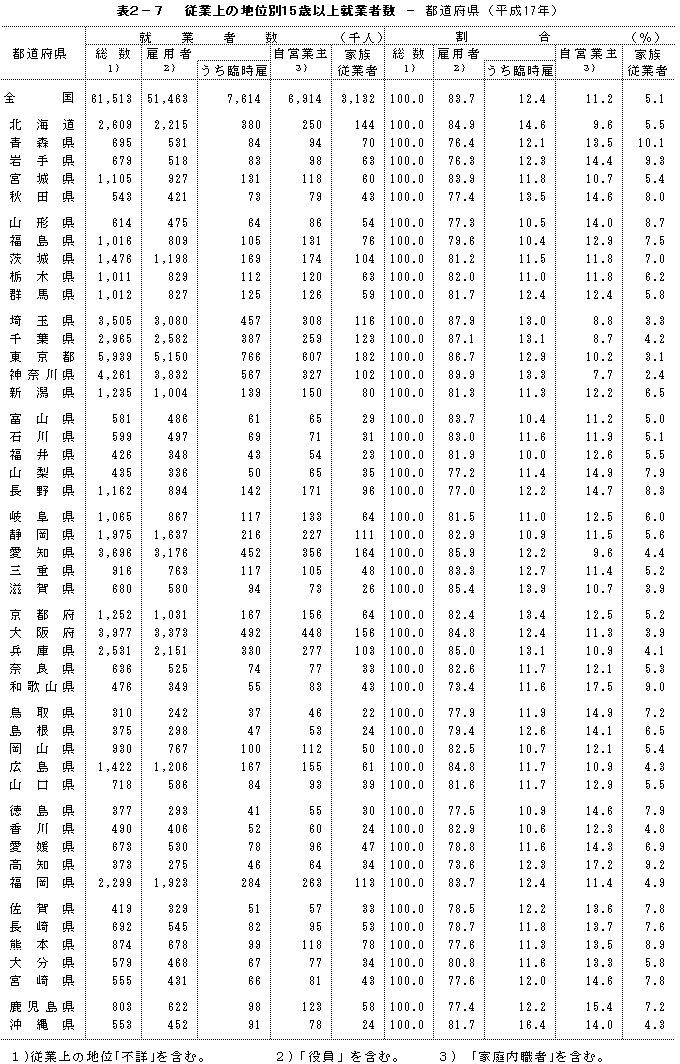
我が国の65歳以上男性の労働力率は,主要先進国に比べ特に高くなっている。(表2-8)
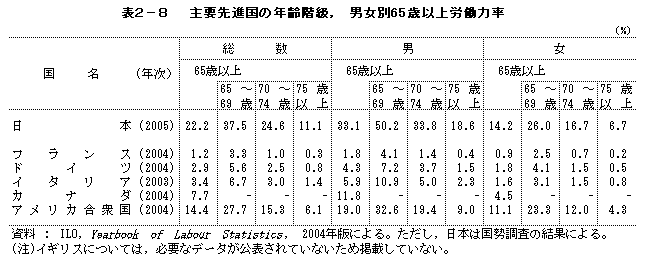
3 臨時雇の雇用者数が増加
〜臨時雇いの雇用者数は第3次産業の割合が大きい〜
15歳以上就業者数(6151万人)が平成12年に比べ147万人(2.3%)減少する中で,臨時雇の雇用者数(761万人)は89万人(13.3%)増加している。
臨時雇の雇用者数を男女別にみると,男性(263万人)が平成12年に比べ39万人(17.6%)増,女性(498万人)が50万人(11.1%)増となっている。(表2-9)
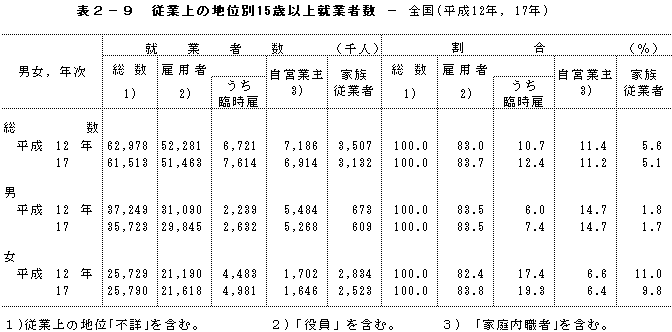
臨時雇の雇用者について産業大分類別に割合をみると,「卸売・小売業」が20.1%と最も高く,次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が17.9%,「医療,福祉」が12.4%などとなっており,第3次産業(注)に含まれる産業の割合が大きくなっている。()
(注) 第3次産業とは,産業大分類が「農業」,「林業」,「漁業」,「鉱業」,「建設業」及び「製造業」以外の産業をいう。
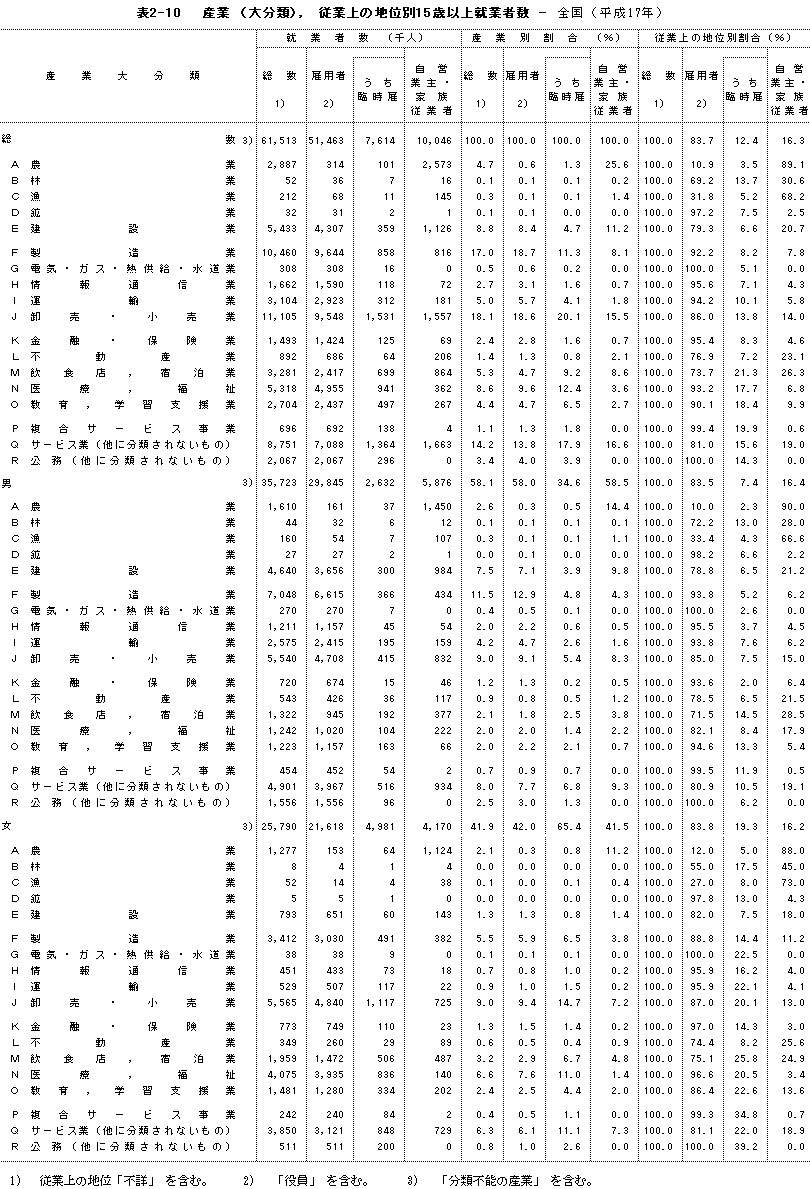
4 平均週間就業時間は41.2時間に減少
〜産業別の就業時間は男性で「運輸業」,女性で「情報通信業」が最も長い〜
15歳以上就業者の平均週間就業時間は41.2時間で,平成12年の42.4時間に比べ1.2時間減少している。男性は45.7時間,女性は34.9時間となっており,男性が女性を10.8時間上回っている。(表2-11)
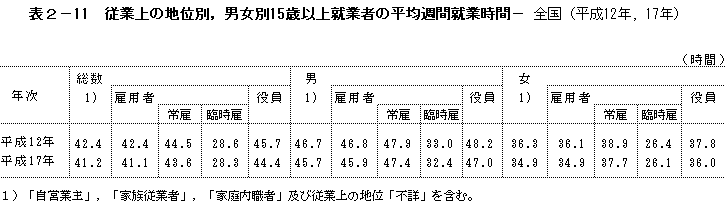
男女別の平均週間就業時間を産業大分類別にみると,男性は「運輸業」が49.5時間と最も長く,次いで「飲食店,宿泊業」が47.5時間,「卸売・小売業」が47.4時間などとなっている。女性は「情報通信業」が39.2時間と最も長く,次いで「鉱業」が37.9時間,「金融・保険業」が37.7時間などとなっている。(図2-3)
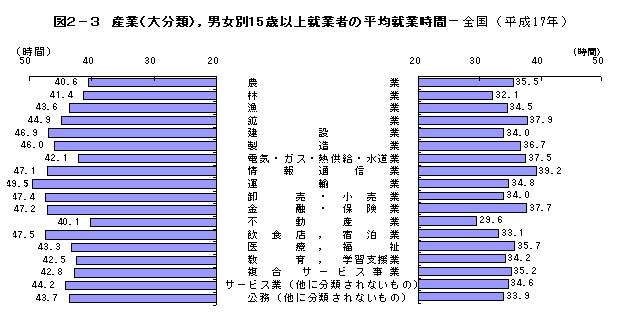
5 都道府県外からの通勤・通学者が多いのは東京都,大阪府,愛知県
〜このうち愛知県への通勤・通学者数は減少から再び増加に〜
昼間人口(注)を都道府県別にみると,東京都が1507万人で最も多く,次いで大阪府が927万人,神奈川県が792万人,愛知県が737万人などとなっている。
また,昼夜間人口比率(夜間人口100人当たりの昼間人口)をみると,東京都が120.3で最も高く,次いで大阪府が105.4,愛知県が101.8などとなっており,これら三大都市圏の中心部を含め17都府県で昼間人口が夜間人口を上回っている。
一方,昼夜間人口比率の低い県をみると,埼玉県が87.8で最も低く,次いで奈良県が88.4,千葉県が88.5などとなっており,上記都市圏の周辺部を構成する県で低くなっている。
昼夜間人口比率が高い東京都,大阪府及び愛知県について都府県外からの通勤・通学者数(流入人口)をみると,東京都への流入人口は301万人で,平成12年と比べると3.4%減,大阪府への流入人口は73万人で6.2%減となっているが,愛知県への流入人口は20万人で6.7%増となっている。これら3都府県への他県からの流入人口の推移をみると,平成12年は3都府県とも減少していたが,17年は愛知県が再び増加になっている。(表2-12,2-13)
(注)昼間人口(従業地・通学地による人口)は,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口をいう。
〔例:A県の昼間人口の算出方法〕
A県の昼間人口 = A県の夜間人口 - A県から他県への通勤・通学者数(流出人口)+ A県への他県からの通勤・通学者数(流入人口)
なお,夜間人口(常住地による人口)は,調査時に調査の地域に常住している人口をいう。