ここから本文です。
平成7年国勢調査 親子の同居等に関する特別集計結果 結果の要約


平成12年9月14日公表
1 親との同居
親との同居率は42.5%
平成7年の全国における人口1億2544万人(年齢「不詳」を除く)のうち親と同居している人は,5330万人で,全国の人口に対する割合,すなわち,親との同居率は42.5%と5割を下回っている。(表1参照)
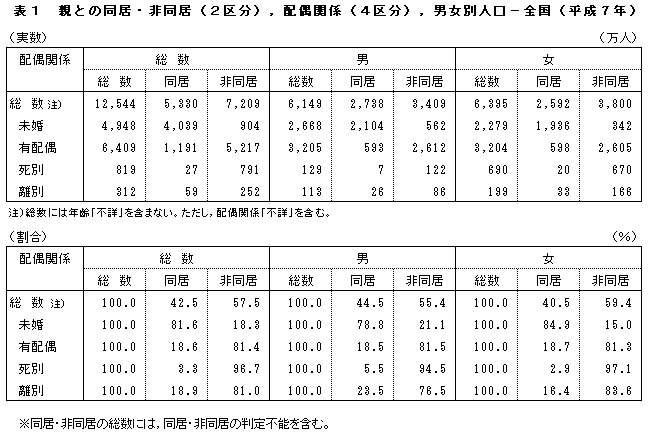
親との同居率は男性44.5%,女性40.5%
男女別にみると,親と同居している人は,男性が2738万人(男性人口の44.5%),女性が2592万人(女性人口の40.5%)となっており,親との同居率は男性の方がやや高くなっている。(表1参照)
未婚の女性は男性に比べると親との同居率が高い
配偶関係別にみると,男性で親と同居している人は,未婚が2104万人(男性の未婚者の78.8%),有配偶が593万人(男性の有配偶者の18.5%),離別が26万人(男性の離別者の23.5%),死別が7万人(男性の死別者の5.5%)となっている。一方,女性で親と同居している人は,未婚が1936万人(女性の未婚者の84.9%),有配偶が598万人(女性の有配偶者の18.7%),離別が33万人(女性の離別者の16.4%),死別が20万人(女性の死別者の2.9%)となっている。親との同居率は,未婚と有配偶では女性の方がやや高くなっているものの,離別及び死別では男性の方が高くなっている。また,未婚の同居率が男女共に8割前後と極めて高い理由は,20歳未満の者が半数以上を占めているためである。一方,死別の同居率が男女共に1割未満と極めて低い理由は高齢者が7割以上を占めているためである。(表1参照)
20〜39歳の未婚者のうち親と同居している人は1185万人で全国の人口の約1割
年齢別にみると,20歳未満で親と同居している人は,2742万人(20歳未満の者の96.0%),20歳以上は2588万人(20歳以上の者の26.7%),うち65歳以上は41万人(65歳以上の者の2.2%)となっている。また,近年の少子化の主な原因の一つは未婚率の上昇であるが,平均初婚年齢に近い20〜39歳の未婚者についてみると,親と同居している人は1185万人(20〜39歳の未婚者の67.6%)と全国の人口の1割近くを占めており,親との同居率もかなり高くなっている。(表2,3参照)
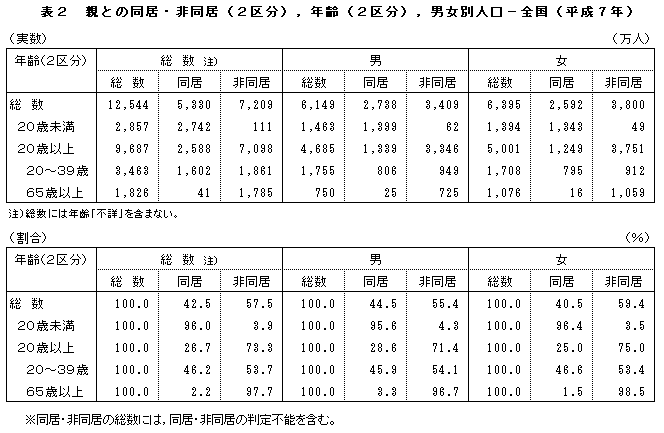
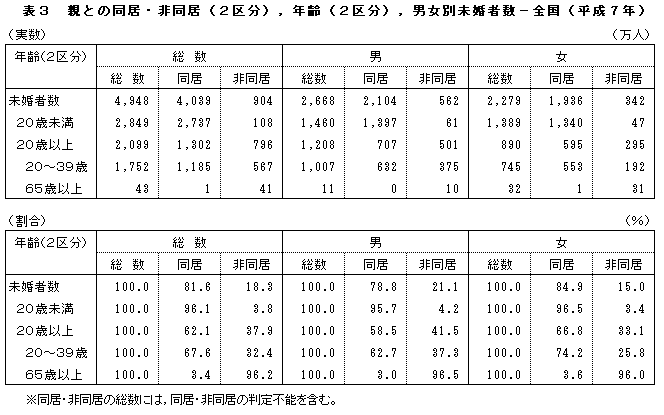
日本海側や東北地方の県で親との同居率が高く,西日本地方や大都市のある都道府県で低い
都道府県別に親との同居率をみると,山形県が53.0%と最も高く,以下,福井県が50.7%,富山県が50.2%,新潟県が50.1%と以上の4県で5割を超えており,日本海側や東北地方の1世帯当たりの延べ面積が比較的広い県で高くなっている。一方,東京都が34.8%と最も低く,以下,鹿児島県が35.8%,北海道が36.6%,高知県が38.8%,神奈川県が39.0%,大阪府が39.1%などとなっており,8都道府県で4割を下回っており,西日本地方や大都市のある都道府県で低くなっている。また,これらの都道府県では1世帯当たりの延べ面積が比較的狭いところが多い。(表4参照)
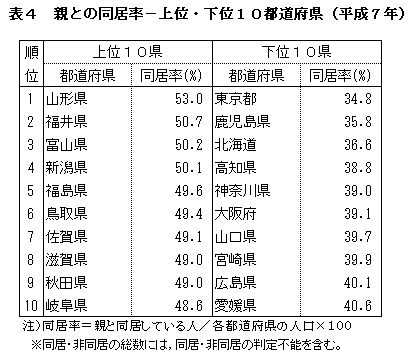
2 子との同居
子との同居率は50歳以上では56.3%
平成7年の全国における50歳以上人口4261万人のうち子と同居している人は,2399万人で,全国の50歳以上人口に対する割合,すなわち,子との同居率は56.3%と5割を超えている。(表5参照)
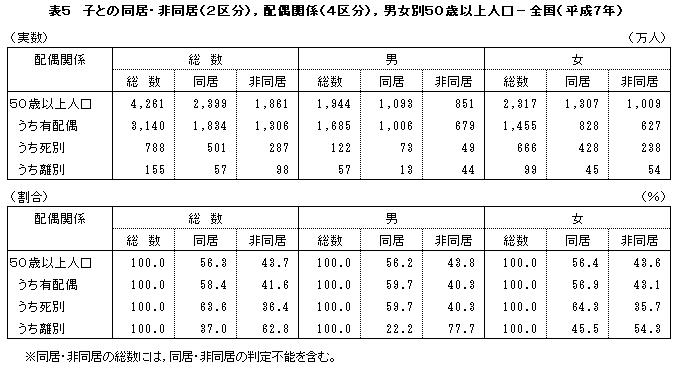
子との同居率は,50歳以上では男性56.2%,女性56.4%
男女別にみると,50歳以上で子と同居している人は,男性が1093万人(男性の50歳以上人口の56.2%),女性が1307万人(女性の50歳以上人口の56.4%)となっており,子との同居率は男女ともほぼ同じになっている。(表5参照)
50歳以上では離別の女性は男性に比べると子との同居率が高い
配偶関係別にみると,50歳以上の男性で子と同居している人は,有配偶が1006万人(男性の有配偶者の59.7%),死別が73万人(男性の死別者の59.7%),離別が13万人(男性の離別者の22.2%)となっている。一方,50歳以上の女性で子と同居している人は,有配偶が828万人(女性の有配偶者の56.9%),死別が428万人(女性の死別者の64.3%),離別が45万人(女性の離別者の45.5%)となっている。子との同居率は,有配偶と死別では男女共に5割を超えており,離別では女性が男性よりもかなり高くなっているものの,5割を下回っている。(表5参照)
高齢になるほど子との同居率は高い
年齢別にみると,65歳以上で子と同居している人は,955万人(65歳以上の者の52.3%),うち75歳以上は427万人(75歳以上の者の59.5%),うち85歳以上は104万人(85歳以上の者の65.6%)となっている。子との同居率は,いずれも5割を超え,高齢になるほど子との同居率が高くなっている。また,女性の方が男性よりやや高くなっている。(表6参照)
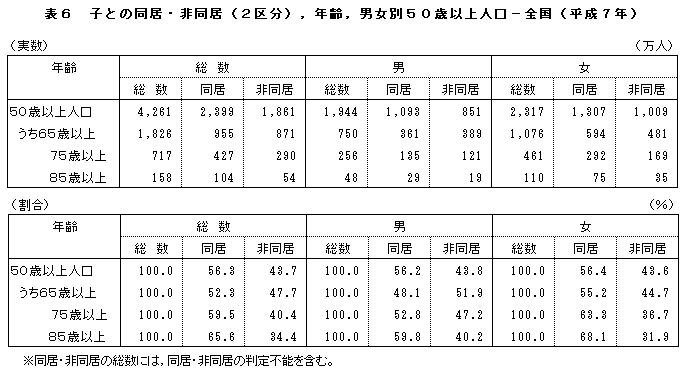
主に日本海側や北関東地方の県で子との同居率が高く,西日本地方や北海道で低い
都道府県別に子との同居率をみると,山形県が69.8%とほぼ7割を占め最も高く,以下,滋賀県が67.1%,茨城県が66.5%,新潟県が66.1%,栃木県が65.9%などとなっており,22県で6割を超え,主に日本海側や北関東地方の1世帯当たりの延べ面積が比較的広い県で高くなっている。一方,鹿児島県が34.0%と唯一4割を下回り最も低く,以下,北海道が41.6%,宮崎県が42.2%,高知県が42.6%,山口県が43.5%などとなっており,9県で5割を下回り,西日本地方や北海道で低くなっている。また,これらの道県では,1世帯当たりの延べ面積が比較的狭いところが多い。(表7参照)
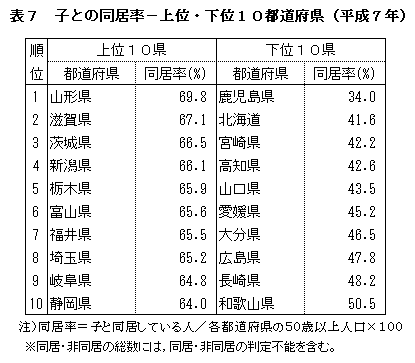
3 3世代以上世帯
3世代以上世帯は493万世帯で,そのうち夫婦のいない3世代以上世帯は34万世帯
平成7年の全国における一般世帯4390万世帯のうち3世代以上世帯は,493万世帯(一般世帯の11.2%)となっている。また,そのうち夫婦のいる3世代以上世帯は,459万世帯(同10.5%)となっており,夫婦のいない3世代以上世帯が34万世帯(同0.8%)となっている。この夫婦のいない3世代以上世帯には,夫婦のいずれかが単身赴任している世帯,夫婦のいずれかが入院中の世帯などが含まれている。(表8参照)
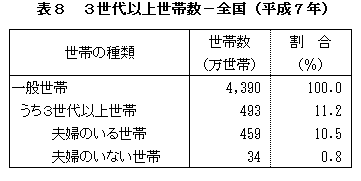
日本海側や東北地方の県で3世代以上世帯の割合が高く,西日本地方の県や大都市などで低い
都道府県別に一般世帯に占める3世代以上世帯の割合をみると,山形県が29.9%(11万世帯)とほぼ3割を占め最も高く,以下,福井県が24.8%(6万世帯),富山県が24.5%(8万世帯),秋田県が23.8%(9万世帯),新潟県が23.5%(18万世帯)などとなっており,11県で2割を超え,日本海側や東北地方の県で高くなっている。一方,東京都が4.4%(22万世帯)と最も低く,以下,鹿児島県が4.7%(3万世帯),大阪府が6.0%(19万世帯),神奈川県が6.3%(19万世帯),北海道が6.7%(14万世帯)などとなっており,14都道府県で1割を下回り,大都市のある都道府県や西日本地方で低くなっている。また,政令指定都市及び東京都特別区部(以下「13大都市」という。)では,最も高い千葉市が9.6%(19万世帯),一方,最も低い札幌市が4.0%(3万世帯)と,すべての都市で1割を下回っている。(表9参照)
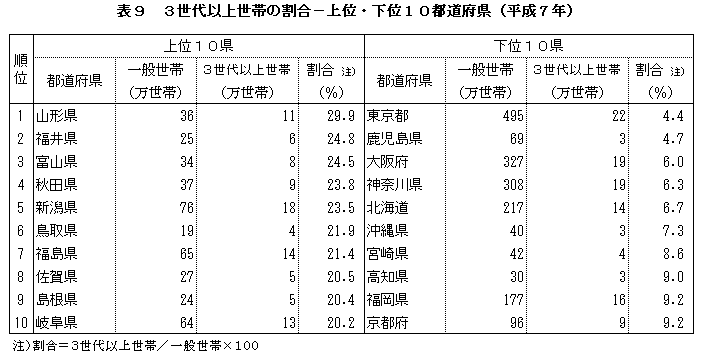
4 専業主婦
専業主婦は1448万人で,有配偶の女性の半数に近い
平成7年の全国における有配偶の女性人口3204万人のうち労働力状態が家事の人,すなわち,専業主婦は1448万人で,有配偶の女性人口の45.2%を占めており,半数近くが専業主婦であることが分かる。(表10参照)
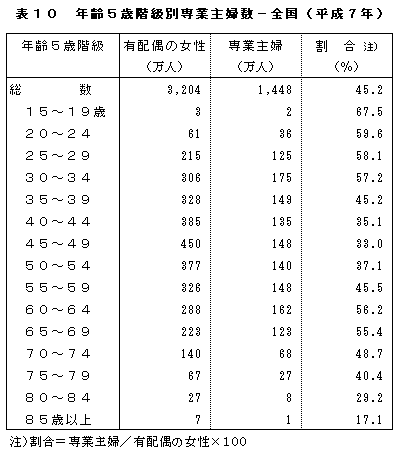
専業主婦は35歳未満と60歳代で割合が高い
年齢5歳階級別に有配偶の女性人口に占める専業主婦の割合をみると,15〜19歳が67.5%(2万人)と最も高く,以下,20〜24歳が59.6%(36万人),25〜29歳が58.1%(125万人),30〜34歳が57.2%(175万人),60〜64歳が56.2%(162万人),65〜69歳が55.4%(123万人)と,以上が5割を超え,35歳未満の若年層と60歳代で割合が高くなっている。(表10参照)
専業主婦の割合は大都市圏に含まれる都道府県で高く,主に日本海側の県で低い
都道府県別に有配偶の女性人口に占める専業主婦の割合をみると,奈良県が56.2%(21万人)と最も高く,以下,大阪府が54.4%(117万人),神奈川県が53.6%(111万人),兵庫県が52.6%(73万人),東京都が50.4%(138万人)などとなっており,5都府県で5割を超え,大都市圏に含まれる都道府県で高くなっている。一方,鳥取県が30.9%(5万人)と最も低く,以下,福井県が31.1%(7万人),富山県が33.0%(10万人)などとなっており,21県で4割を下回り,主に日本海側の県で低くなっている。(表11参照) 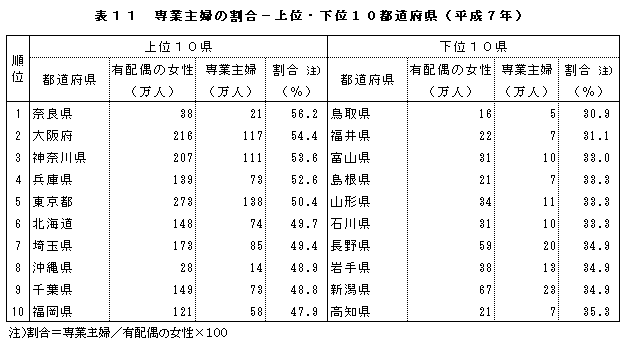
5 単独有配偶者のいる世帯
単独有配偶者とは,夫婦となるべき相手が世帯内にいない有配偶者である。
単独有配偶者のいる世帯は154万世
平成7年の全国における一般世帯4390万世帯のうち単独有配偶者のいる世帯は,154万世帯で,一般世帯の3.5%を占めている。このうち単独世帯には,主に単身赴任者の世帯が含まれており,それ以外の世帯には,主に単身赴任者を送り出している世帯が含まれている。(表12参照)
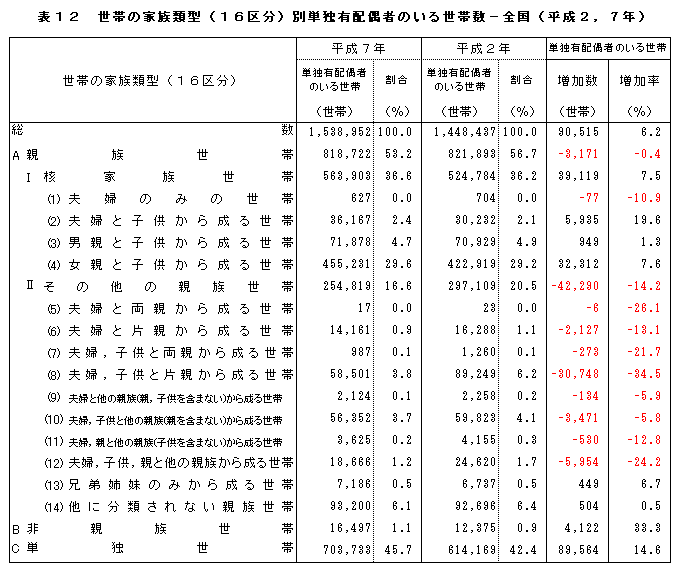
女親と子供から成る世帯が単独有配偶者のいる世帯のうち約3割を占めている
世帯の家族類型別にみると,単独世帯が70万世帯(単独有配偶者のいる世帯の45.7%)で最も多く,以下,女親と子供から成る世帯が46万世帯(同29.6%),他に分類されない親族世帯が9万世帯(同6.1%),男親と子供から成る世帯が7万世帯(同4.7%),夫婦,子供と片親から成る世帯が6万世帯(同3.8%)などとなっている。(表12参照)
単独有配偶者のいる世帯の割合は東北地方などで高く,近畿地方などで低い
都道府県別に一般世帯に占める単独有配偶者の割合をみると,岩手県が6.3%(2万8千世帯)と最も高く,以下,青森県が5.9%(2万8千世帯),沖縄県が5.2%(2万1千世帯)などとなっており,以上の3県で5%を超え,東北地方の県と沖縄県で高くなっている。一方,京都府が2.6%(2万5千世帯)と最も低く,和歌山県が2.7%(1万世帯),奈良県が2.8%(1万3千世帯),埼玉県が2.9%(6万7千世帯),大阪府が2.9%(9万6千世帯)などとなっており,以上の5府県で3%を下回り,近畿地方の府県と埼玉県で低くなっている。(表13参照)
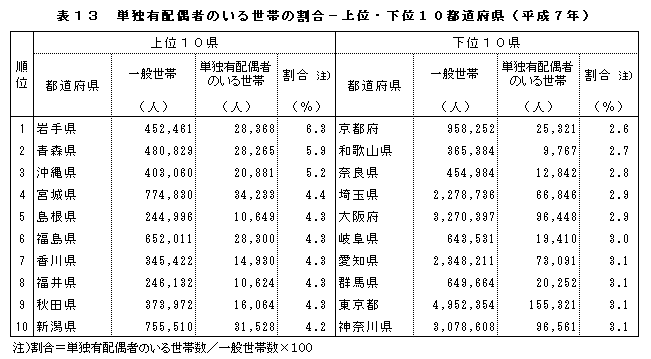
単独有配偶者のいる世帯は平成2年と比べると6.2%の増加
平成2年と比べると,全国では9万1千世帯増(6.2%増)となっている。また,世帯の家族類型別にみると,単独世帯が9万世帯増(同14.6%増)で最も多く,以下,女親と子供から成る世帯が3万世帯増(同7.6%増),夫婦と子供から成る世帯が6千世帯増(同19.6%増),非親族世帯が4千世帯増(同33.3%増)などとなっている。一方,夫婦,子供と片親から成る世帯が3万世帯減(同34.5%減),夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯が6千世帯減(同24.2%減)などとなっている。(表12参照)
6 単独世帯の有配偶の就業者
単独世帯の有配偶の就業者は60万人で男性が85.2%
平成7年の全国における単独世帯(一人世帯)のうち有配偶の就業者は60万人となっており,主に単身赴任者が含まれている。
男女別にみると,男性が51万人(単独世帯の有配偶の就業者の85.2%)で,女性は9万人(同14.8%)となっている。(表14参照)
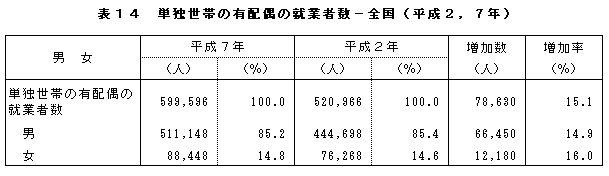
単独世帯の有配偶の就業者は40歳代と50歳代で7割以上を占めている
年齢5歳階級別にみると,45〜49歳が14万人(単独世帯の有配偶の就業者の23.0%)と最も多く,以下,50〜54歳が13万人(同20.9%),55〜59歳が9万人(同14.2%),40〜44歳が8万人(同13.5%)などとなっており,40歳代と50歳代で43万人(同71.7%)と7割以上を占めている。(表15参照)
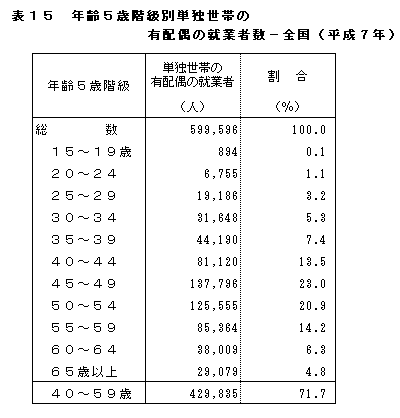
単独世帯の有配偶の就業者はサービス業が最も多い
産業大分類別にみると,サービス業が14万人(単独世帯の有配偶の就業者の23.2%)と最も多く,以下,製造業が12万人(同20.0%),卸売・小売業,飲食店が11万人(同17.8%),建設業が9万人(同14.3%)などとなっている。(表16参照)
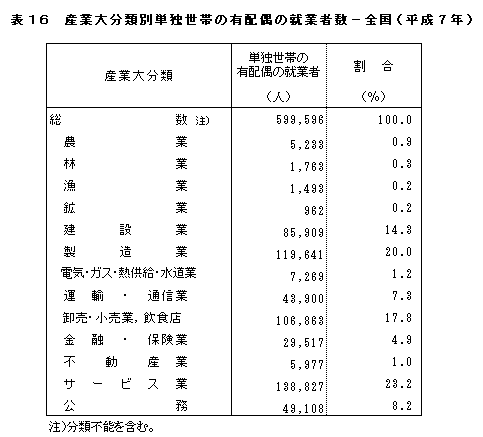
単独世帯の有配偶の就業者は13大都市に全国の4分の1以上が集中している
都道府県別にみると,東京都が6万6千人(全国の11.0%)と最も多く,以下,神奈川県が3万9千人(同6.4%),北海道が3万7千人(同6.2%),大阪府3万6千人(同6.0%),愛知県が3万2千人(同5.3%)などとなっており,5都道府県で3万人を超え,13大都市のある都道府県で多くなっている。一方,鳥取県が2千8百人(同0.5%)と最も少なく,以下,佐賀県が3千3百人(同0.5%),和歌山県が3千4百人(同0.6%),奈良県が3千5百人(同0.6%),徳島県が3千6百人(同0.6%)などとなっており,9県で5千人を下回り,比較的人口の少ない県で少なくなっている。また,13大都市では,東京都特別区部が5万人(同8.4%)と最も多く,以下,名古屋市が1万6千人(同2.7%),横浜市が1万5千人(同2.6%),大阪市1万4千人(同2.4%)などとなっており,4都市で1万人を超えている。一方,北九州市が4千3百人(同0.7%)と最も少なくなっている。また,13大都市の合計は,16万人(同26.3%)となっており,全国の4分の1を超えている。(表17,18参照)
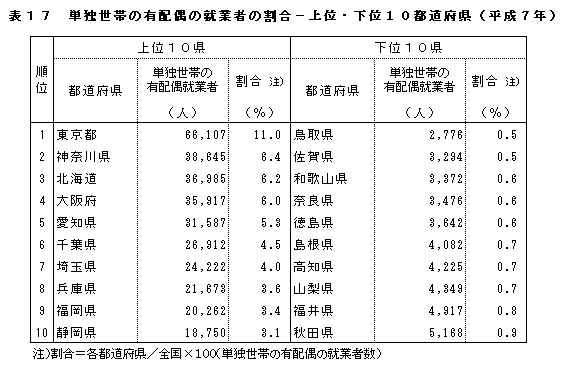
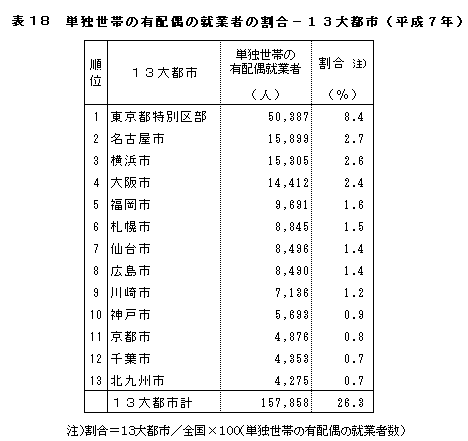
単独世帯の有配偶の就業者は平成2年と比べると15.1%の増加
平成2年と比べると,全国では7万9千人増(15.1%増)と,かなり増加している。また,男女別にみると,男性が6万6千人増(14.9%増),女性が1万2千人増(16.0%増)となっており,女性の増加率の方がやや高くなっている。(表14参照)
