ここから本文です。
統計表で用いられる用語,分類の解説


年齢・平均年齢
年齢は,調査日前日による満年齢です。
ただし,昭和15年及び22年の調査については,満年齢と数え年の両方の集計を行っています。
また,報告書等に掲載している平均年齢の算出は,以下の式によっています。
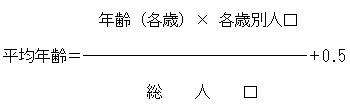
配偶関係
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分しています。
- 未 婚-まだ結婚したことのない人
- 有配偶-妻又は夫のある人
- 死 別-妻又は夫と死別して独身の人
- 離 別-妻又は夫と離別して独身の人
国 籍
平成7年国勢調査では国籍を,「日本」のほか,以下のように10区分に分けています。
10区分───「韓国,朝鮮」「中国」「フィリピン」「タイ」「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」「イギリス」「アメリカ」「ブラジル」「ペルー」「その他」
昭和60年以前については「日本」のほか,「韓国,朝鮮」「中国」「アメリカ」「その他」の4区分としており,平成2年では,この4区分に「フィリピン」「フィリピン以外の東南アジア,南アジア」を加えた6区分としています。
二つ以上の国籍を持つ人の扱いについては,日本と日本以外の国の国籍を持つ人の国籍は「日本」,日本以外の二つ以上の国の国籍を持つ人は,調査票の国名欄に記入された国としています。
ただし,昭和50年以前については,二つ以上の国籍を持つ人について,次のように取り扱っています。
1) 昭和25年は「その他」としています。
2) 昭和30年〜50年は調査票の国名欄の最初に記入された国によっています。ただし,昭和40年の場合,調査票に記入された国の中に韓国,朝鮮があるときは「韓国,朝鮮」とし,韓国,朝鮮がなく中国があるときは「中国」としています。
なお,昭和35年及び40年の沖縄県の調査では,「韓国,朝鮮」が「その他」に含まれています。
世帯の種類
昭和60年以降の国勢調査では,世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しています。
一般世帯とは,次のものをいいます。
1) 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めています。
2) 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者施設等の世帯とは,次のものをいいます。なお,世帯の単位は,原則として下記の1)及び2)は棟ごと,3)は施設ごと,4)は中隊又は艦船ごと,5)は建物ごと,6)は一人一人としています。
1) 寮・寄宿舎の学生・生徒──学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
2) 病院・療養所の入院者──病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり
3) 社会施設の入所者──老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
4) 自衛隊営舎内居住者──自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり
5) 矯正施設の入所者──刑務所及び拘置所の収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり
6) その他──定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
昭和55年以前の国勢調査での世帯の定義,世帯の種類は,昭和60年以降と以下のように異なっています。
昭和55年
昭和55年では,世帯を「普通世帯」と「準世帯」に区分し,次のとおり定義しています。
普通世帯──住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者。
ただし,普通世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なくすべて雇主の世帯に含めています。
準世帯──普通世帯を構成する人以外の人又はその集まり。
なお,準世帯については次のように区分しており,世帯の単位は,原則として下記の1)及び2)は単身者一人一人,3)及び5)は棟ごと,4)は施設ごと,6)及び7)は調査単位ごと,8)は一人一人としています。
1) 間借り・下宿などの単身者
2) 会社などの独身寮の単身者
3) 寮・寄宿舎の学生・生徒
4) 病院・療養所の入院者
5) 社会施設の入所者
6) 自衛隊営舎内居住者
7) 矯正施設の入所者
8) その他
なお,昭和60年国勢調査以降における一般世帯,施設等の世帯の区分と,昭和55年国勢調査での普通世帯,準世帯との対応は下の表のとおりです。
一般世帯と施設等の世帯,普通世帯と準世帯の世帯の区分の対応
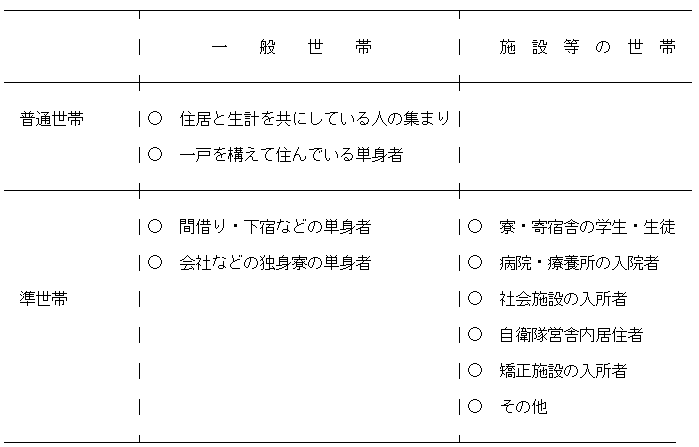
昭和35年〜50年
昭和55年の世帯の定義と異なるのは次の点です。
1) 単身の住み込みの営業使用人は,5人以下の場合は雇主の世帯に含め,これを普通世帯とし,6人以上の場合は,営業使用人だけをまとめて一つの準世帯としています。
2) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎・独身寮などに,起居を共にしている単身の職員を,その寄宿舎・独身寮の棟ごとにまとめて一つの準世帯としています。
ただし,各戸が住宅の要件を備えている場合で,管理人以外に家族から成る普通世帯と単身者(一戸の居住者数は無関係)が同じ棟に居住しているような寮の単身者は,昭和55年の調査と同様に一人一人を一つの普通世帯としています。なお,一戸に単身者二人以上が居住している場合は,一人を「給与住宅」に住む普通世帯,他を一人ずつ「住宅に間借り」の準世帯としています。
昭和30年
昭和30年の普通世帯及び準世帯の定義で昭和35年〜50年の調査と異なるのは次の点です。
1) 単身の住み込みの営業使用人はすべて雇主の世帯に含めています。
2) 間借り又は下宿屋に住み,それぞれ独立して生計を維持している単身者について,一人一人を準世帯とせず,まとめて一つの準世帯としています。
昭和25年
昭和25年の調査では,昭和30年でいう二人以上の普通世帯を「普通世帯」とし,一人の普通世帯を準世帯に含めていますが,昭和25年の報告書では,この普通世帯に一人の準世帯を合わせて「一般世帯」として表章し,二人以上の準世帯を「準世帯」として表章しています。
大正9年〜昭和22年
大正9年〜昭和22年の普通世帯及び準世帯の定義は,昭和30年のものと,次の点を除いて実質的にほとんど同じです。
1) いわゆる素人下宿の単身の下宿人は下宿先の普通世帯に含め,また,間借り自炊している人は間貸主とは別の普通世帯としています。
2) 昭和25年以降,常住地方式により人口を把握しているのに対し,昭和22年以前は現在地方式によって人口を把握しているため,例えば10月1日午前零時をはさんで旅行中の人などは,昭和25年以降では自宅で把握されているのに対し,昭和22年以前は旅館宿泊者の準世帯として把握されているなどの場合があります。
世帯の定義の変遷:大正9年〜平成7年
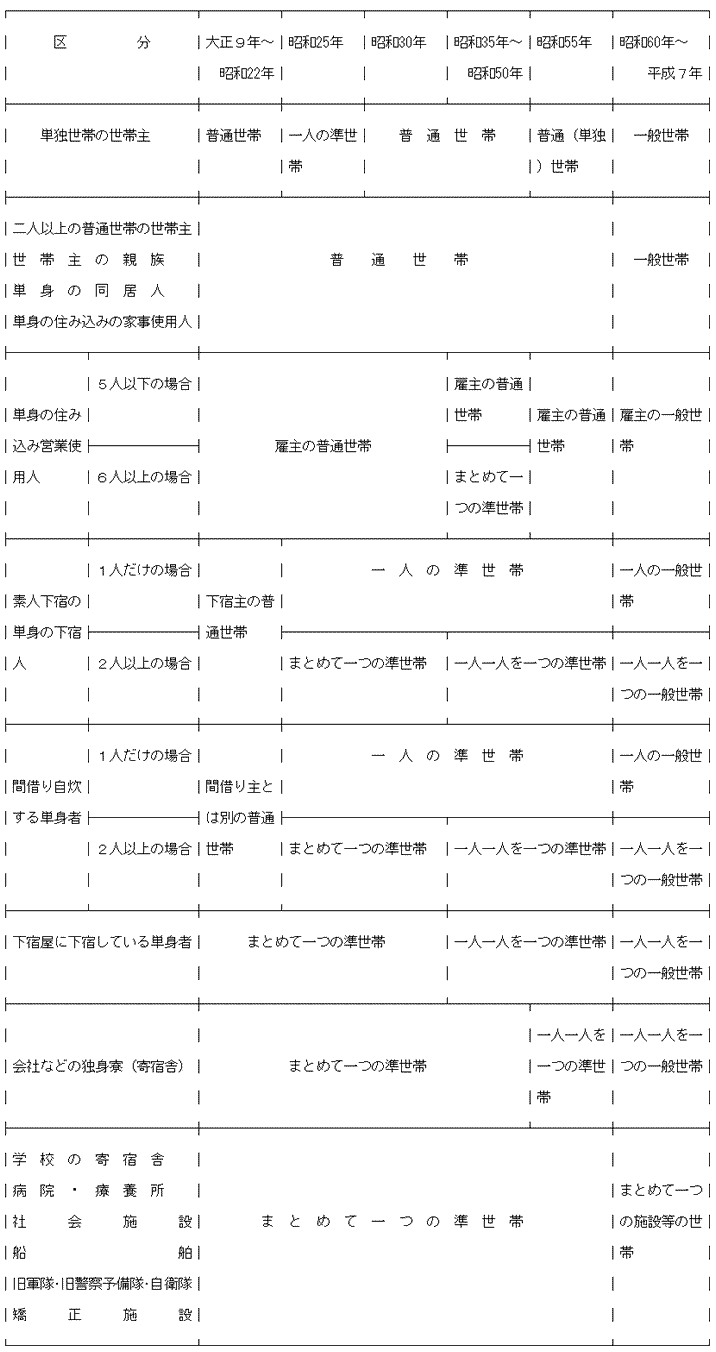
注)「まとめて一つの準世帯」の「まとめて」とは,個々の準世帯において住居,棟など調査単位ごとにまとめるという意味です。
沖縄県の調査における世帯の種類
沖縄県の調査で用いられた世帯の定義のうち,上に記した定義と異なるのは昭和35年の調査における次の点です。その他の年については,上と同一の定義によっています。
1) 普通世帯と住居を共にし,生計を別にしている単身の同居人,間借り人,4人以下の単身の下宿人及び営業使用人は一人一人を一つの普通世帯としています。
2) 準世帯は,「その他の世帯」として表章されており,この中には,普通世帯と住居を共にし,生計を別にしている単身の家事使用人(一人一人を一つの世帯)と5人以上の下宿人,営業使用人(まとめて一つの世帯)を含めています。
