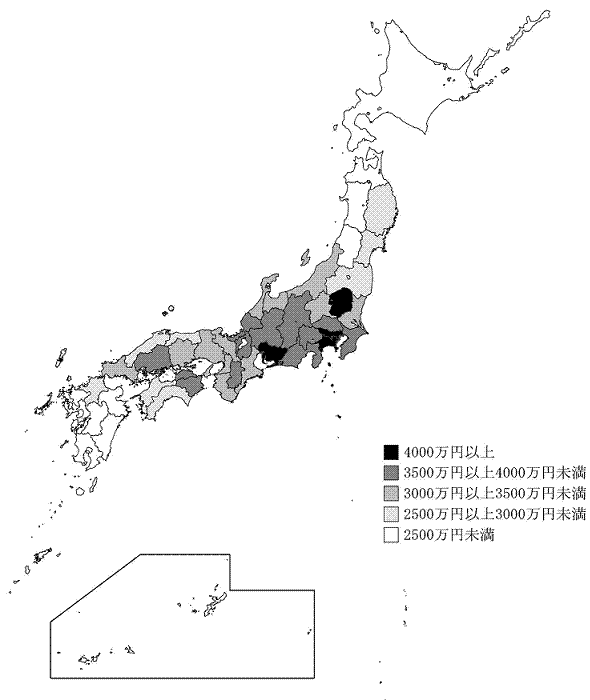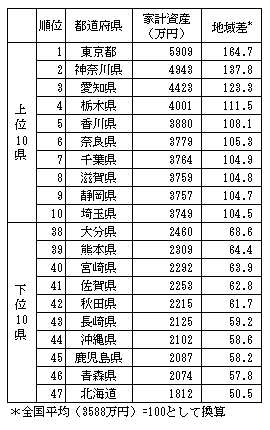ここから本文です。
平成21年全国消費実態調査 家計資産に関する結果の要約
平成23年3月31日 公表
![]() の項目は、政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。
の項目は、政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。
PDFファイルはこちら(PDF:426KB)
<利用上の注意>
1)本文中の家計資産は全て,実物資産のうち住宅及び耐久消費財等の減価償却を考慮し価額評価した「純資産額」を用いています。
2)平成21年と16年では実物資産の価額評価方法が異なるため,前回との比較に用いている16年の数値は,21年の価額評価方法に合わせて遡及集計した数値を用いています。
1 1世帯当たりの家計資産は3588万円,うち約56%が宅地資産
- 二人以上の世帯の平成21年11月末日現在の家計資産は,1世帯当たり3588万円。
- 内訳をみると,宅地資産が1992万円で家計資産の55.5%を占め,そのほか金融資産が947万円,住宅資産が523万円,耐久消費財等資産が127万円。
- 平成16年と比べると,家計資産は6.2%の減少。内訳をみると,宅地資産が8.6%の減少,耐久消費財等資産が13.5%の減少,住宅資産が4.5%の減少,金融資産が0.4%の減少。
表1 1世帯当たり家計資産の内訳 ―平成21年―
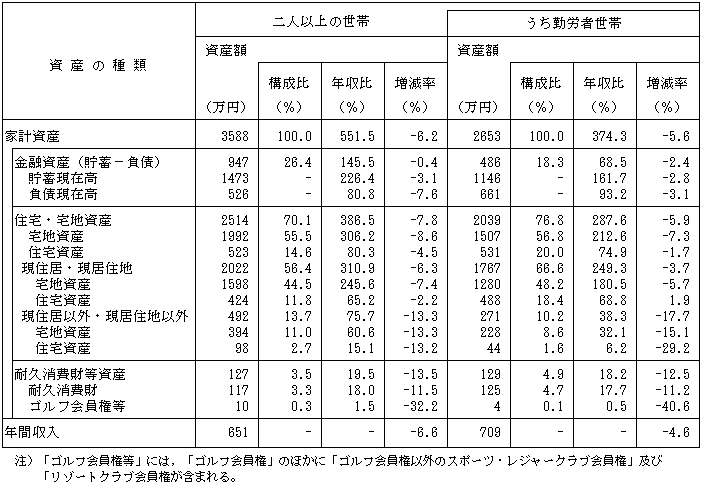
図1 1世帯当たり家計資産の前回との比較(二人以上の世帯)
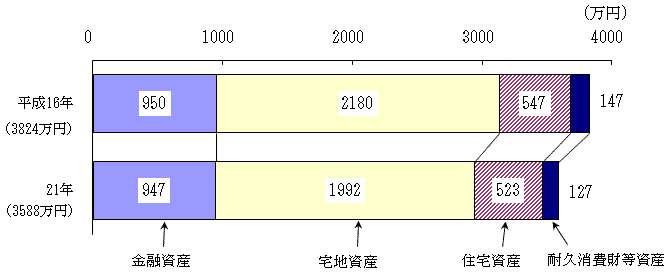
2 家計資産が平均以下の世帯が全体の約3分の2
- 二人以上の世帯の家計資産額階級別の世帯分布をみると,1世帯当たり家計資産は平均値3588万円,中央値2284万円で,平均以下の世帯が全体の66.2%を占め,資産額の低い階級に偏った分布。
- 住宅・宅地資産額階級別の世帯分布をみると,住宅・宅地資産保有世帯の平均値は3064万円,中央値は1960万円。
図2 家計資産額階級別世帯分布(二人以上の世帯)−平成21年−
家計資産
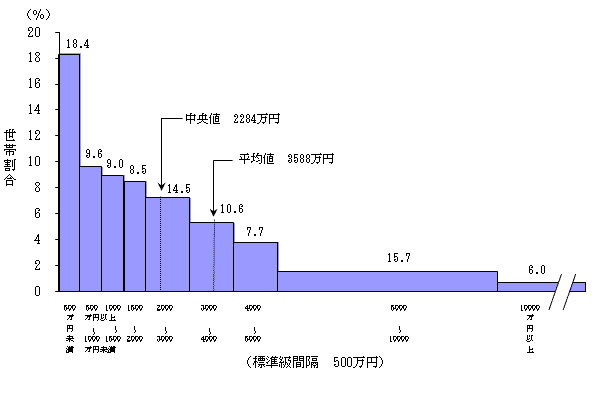
住宅・宅地資産
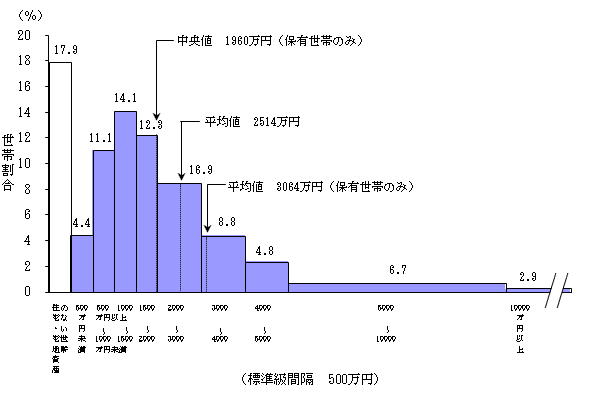
3 家計資産は70歳以上が最も多く,30歳未満の5.9倍
- 二人以上の世帯の1世帯当たり家計資産を世帯主の年齢階級別にみると,30歳未満が854万円,70歳以上が5024万円などとなっており,年齢階級が高い世帯ほど家計資産が多い。
- 平成16年と比べると,家計資産は30歳未満を除く各年齢階級で減少。
表2 世帯主の年齢階級別1世帯当たり家計資産(二人以上の世帯)−平成21年−
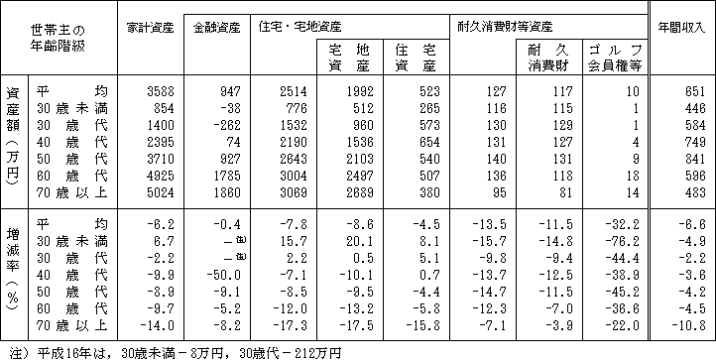
4 単身世帯の家計資産も70歳以上が最も多い
- 単身世帯の1世帯当たりの家計資産は男性が1861万円,女性が2997万円。
- 年齢階級別にみると,男女とも年齢階級が高い世帯ほど家計資産が多い。
図3 男女,年齢階級別1世帯当たり家計資産(単身世帯)−平成21年−
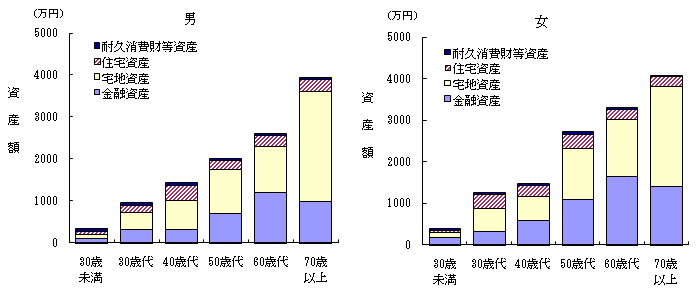
5 年収第X階級の家計資産は第I階級の3.2倍
- 二人以上の世帯の1世帯当たり家計資産を年間収入十分位階級別にみると,第I階級が2181万円,第V階級が3065万円,第X階級が7041万円などとなっており,年間収入が高い世帯ほど家計資産も多い。
- 所得階級間格差(第X階級の第I階級に対する家計資産の比)は3.2倍。資産の種類別にみると,住宅資産が4.7倍,宅地資産及び耐久消費財等資産が3.2倍,金融資産が2.7倍。
- 所得階級間格差を平成16年と比べると,家計資産は3.4倍から3.2倍に縮小。資産の種類別にみると,宅地資産及び耐久消費財等資産は格差が縮小。金融資産及び住宅資産はほぼ横ばい。
表3 年間収入十分位階級別1世帯当たり家計資産(二人以上の世帯)−平成21年−
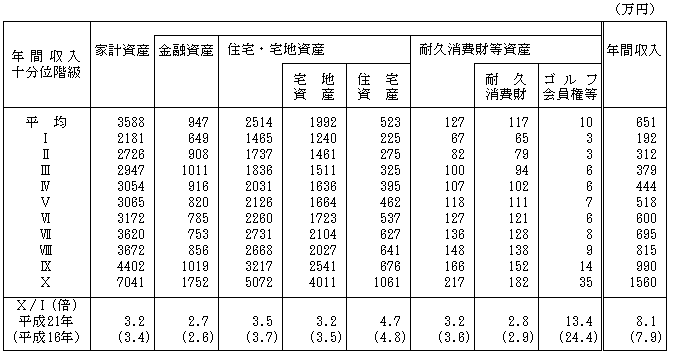
6 1世帯当たり家計資産は東京都が最も多い
- 二人以上の世帯の1世帯当たり家計資産を都道府県別にみると,東京都が5909万円と最も多く,次いで神奈川県,愛知県,栃木県などと続いており,関東地方などで多くなっている。
- 最も少ないのは北海道の1812万円で,次いで青森県,鹿児島県,沖縄県などと続いており,北海道地方,九州地方などで少なくなっている。
図4 都道府県別1世帯当たり家計資産(二人以上の世帯)−平成21年−